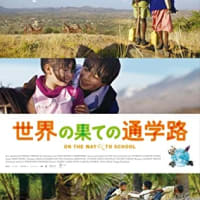表現は
多様(みんな)に受けとめられて
ゆたかに育つ
ことばも感情も
多様(みんな)に受けとめられて
ゆたかに拓く
多様に受けとめられるとは、
どういうことだろう?
多様に受けとめられる場所は、
どんな場所だろう?
6才の子どもにとって、
ありのままの自分を表現できる場所。
子どものつたない表現を、
おおらかに受けとめる大人。
ひとつの表現を幾通りもの可能性として
受けとめてくれる集団。
お互いのおさない表現を受けとめあい、
たしかめあい、わかりあう仲間。
うれしい、かなしい、たのしい、さびしい、
いっしょがいい、ひとりがいい、
だいすきもだいきらいも、
表現の咲き方はひとつではない。
ことばの意味はひとつじゃない。
感情の表現もひとつじゃない。
ことばの咲き方も、
表現の色合いもひと通りではない。
そうだとすれば、
受けとめ方もひとつじゃ足りない。
ことばの受けとめ方も、
感情の受けとめ方も、
受けとる人の気持ちの数だけある。
ことばを豊かに育てるとは、
気持ちを豊かに育てること。
感情の表現を豊かに育てるとは、
受けとめあう関係を豊かに育てるということ。
子どもが表現してくれなければ、
どんな大人も、受けとめることができない。
はじまりは、子ども。
主役は、子ども。 (※1)
だけど、受けとめてくれる人がいないと、
子どもの表現はしおれていく。
関係を豊かに育てることは、個別ではできない。
それは、個の能力では届かない場所にある。
表現されたひとつのことば
表現された一瞬の感情を多様に受けとめあうこと
色とりどりに、色あざやかに受けとめあう場所
表現する子どもも、受けとめる子どもも、
多種多様、雑多にごちゃごちゃいる方がいい。
雑多で多様であることが、豊かであるということ。
そのなかにあってこそ、
ひとりの子どもの表現は、
うまれ、であい、そだち、ひらいていく。
(※1)
【り】 理解はこの子がつくるもの
【り】 理解はあとからついてくる