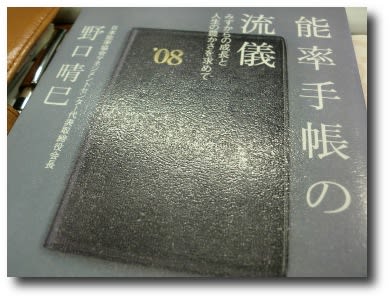高校生のときに生徒手帳のダイアリーとメモ・ページを実用に使い始め、学生時代には大学生協の手帳を愛用しました。これが、実は「能率手帳」だと気づいたのは、いつ頃だったでしょうか。紙質のよさ、時間目盛の入ったレフト式ダイアリーの便利さなど、その後も愛用しました。
ところで、この能率手帳について、発行元の親分が書いた本があるとのことから、本書『能率手帳の流儀』を探しておりましたが、書店にも見当たらない。偶然、某図書館に所蔵されていることを知り、借用して読みました。
本書の構成は、次のようになっています。
ノウハウ本というよりは、著者自身の回顧の中に手帳の果たした役割を位置づけ、ビジネスマンとしての成長のために一般化した本だと言えそうです。
例えば、仕事ができる人はどうやってつくられるのか?という疑問に対し、まわりに優秀な上司や先輩がいたことを共通点として指摘しますが、著者の観察と考察はそれだけにとどまりません。優秀な上司・先輩の下にいた部下の全員が「できる人」になるとは限らないことから、仕事の経験やまわりの人から学べるかどうかの差だととらえ、「振り返りをしているかどうか」の差であると考えます。「読み・書き・考える」ことを根幹に置き、書く、考える、振り返る、気づくための有用な道具として、手帳を位置づける、というわけです。
日本能率協会という性格から、どちらかといえば教育研修的な視点からの言及が多く見られます。例えば、人間国宝・茂山千作さんの言葉
を紹介し(p.59)、お爺さんが孫を指導するやり方を、親子だとできないが孫だと根気よくできる、としています。また、
などという指摘もあります(p.158)。これも、著者の仕事がらに由来するものでしょう。
一方で、手帳に書く習慣の大切さを述べる、「食べたい・行きたい・読みたいリスト」という節では、こんなことも書いています。
功なり名遂げた社長さんには、司馬遼太郎のファンが多く、藤沢周平のファンは少ないのではないかと思っていましたが、どうも著者は、その少ない方の実例なのかもしれません(^o^)/
最近、ある手帳を使えば夢が叶うとか、そんな夢のようなキャッチコピーを帯に大きく書いたノウハウ本を見かけますが、著者は「絶対時間で大樹を目指せ」という章で、絶対的に時間の積み重ねが必要であることを重視し、時代の花は枯れやすいことを指摘しています。これは同感です。逆に、『能率手帳の流儀』ここがヘン、という箇所もありました。例えば、
などと思ってしまいます。
きっと、著者には著者なりの流儀があるのでしょうが、手帳を上手に工夫して使うことの大切さを説いた本として、最近の「一見実用的に見える」ノウハウ本と比較して、かなり普遍性を持った有益な内容が多いと感じました。
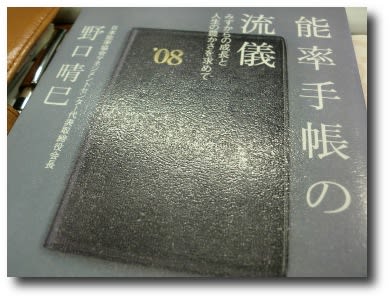
ところで、この能率手帳について、発行元の親分が書いた本があるとのことから、本書『能率手帳の流儀』を探しておりましたが、書店にも見当たらない。偶然、某図書館に所蔵されていることを知り、借用して読みました。
本書の構成は、次のようになっています。
序章 私の成長はすべて手帳が支えてくれた
第1章 手帳にしかできないことがある
第2章 「書く」習慣が人生を変える
第3章 「振り返る」から未来が見える
第4章 絶対時間で大樹をめざせ
第5章 手帳を生かす仕事術
第6章 元祖能率手帳の「こだわり」と「これから」
ノウハウ本というよりは、著者自身の回顧の中に手帳の果たした役割を位置づけ、ビジネスマンとしての成長のために一般化した本だと言えそうです。
例えば、仕事ができる人はどうやってつくられるのか?という疑問に対し、まわりに優秀な上司や先輩がいたことを共通点として指摘しますが、著者の観察と考察はそれだけにとどまりません。優秀な上司・先輩の下にいた部下の全員が「できる人」になるとは限らないことから、仕事の経験やまわりの人から学べるかどうかの差だととらえ、「振り返りをしているかどうか」の差であると考えます。「読み・書き・考える」ことを根幹に置き、書く、考える、振り返る、気づくための有用な道具として、手帳を位置づける、というわけです。
日本能率協会という性格から、どちらかといえば教育研修的な視点からの言及が多く見られます。例えば、人間国宝・茂山千作さんの言葉
「上手に育てたかったら、まず好きにさせることです。自分の仕事が好きになって、本人が努力するのが一番大事だと思います。」
を紹介し(p.59)、お爺さんが孫を指導するやり方を、親子だとできないが孫だと根気よくできる、としています。また、
飢えている人に魚を与えてはいけない。魚の捕りかたを教えるべきだ」という格言があります。研修教育のプログラムを実施するうえで、とても示唆に富む言葉だと思います。
などという指摘もあります(p.158)。これも、著者の仕事がらに由来するものでしょう。
一方で、手帳に書く習慣の大切さを述べる、「食べたい・行きたい・読みたいリスト」という節では、こんなことも書いています。
行きたいリストにしても同様で、藤沢周平のファンなせいか、いつか山形県の鶴岡に行ってみたいと手帳に書いていました。この町は、彼の時代小説の中で「海坂藩」という架空の城下町としてしばしば登場するのです。
そうしたら、先日、出張で行く機会がありました。仕事の合間に町を散策すると、老舗の料亭、町を流れる川や橋、路傍の草花までが小説の世界とダブって見えました。既視感というのでしょうか、じつに楽しい経験でした。(p.94~95)
功なり名遂げた社長さんには、司馬遼太郎のファンが多く、藤沢周平のファンは少ないのではないかと思っていましたが、どうも著者は、その少ない方の実例なのかもしれません(^o^)/
最近、ある手帳を使えば夢が叶うとか、そんな夢のようなキャッチコピーを帯に大きく書いたノウハウ本を見かけますが、著者は「絶対時間で大樹を目指せ」という章で、絶対的に時間の積み重ねが必要であることを重視し、時代の花は枯れやすいことを指摘しています。これは同感です。逆に、『能率手帳の流儀』ここがヘン、という箇所もありました。例えば、
- 「気づき、アイデア、リスト、誰かの言葉、本の引用」などの書き込みで、「6月が終わった時点で早くも満杯になり、7月からは二冊目を使う」ため「手帳が上下二巻に分かれている」(p.172)といいますが、それは単に、手帳の大きさ(判型)か厚さ(ページ数)が合っていないんじゃないか。
- 携帯電話の普及で毎年使わずに残ってしまうアドレス帳の意外な活用法として、行きたい店や泊まってみたい旅館、観たい映画のリストアップに使う(p.165)とありますが、それはアドレス帳じゃなくて補充メモ帳のほうが良いのでは。
などと思ってしまいます。
きっと、著者には著者なりの流儀があるのでしょうが、手帳を上手に工夫して使うことの大切さを説いた本として、最近の「一見実用的に見える」ノウハウ本と比較して、かなり普遍性を持った有益な内容が多いと感じました。