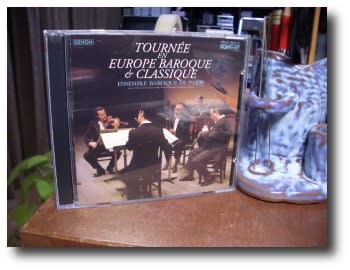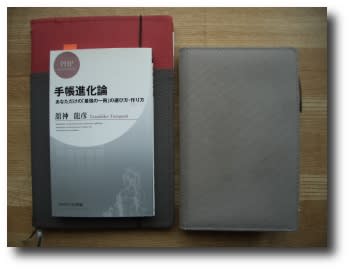万城目学著『プリンセス・トヨトミ』を読みました。万城目という苗字は「まきめ」と呼ぶ(*)のだそうで、本書は2009年の第141回直木賞候補作だそうです。なかなか笑える、肩の凝らないお話です。
会計検査院の調査官3名と、社団法人OJOに代表される豊臣家のプリンセスを守る大阪の男たちの戦いのお話です。会計検査院の調査官である松平と旭の優秀なエリートぶりと、対照的な鳥居のおかしみ、大阪の空堀中学の二年生、性同一性障害に悩む真田大輔と、彼を理解する行動派の橋場茶子、大輔の父親である真田幸一の朴訥な人柄など、物語としての筋立て、道具立ては十分です。
日本国の内部にある二重国家「大阪国」。その秘密は親から子へ、厳粛に伝えられる、という想定です。でもね~。でも、エントロピーは増大するのですよ。物事は乱雑なほうへ向かうのが通例です。口から先に生まれて来て、およそ秘密というものを保つことができない、しゃべりたくってしょうがない大阪人というのが、一定の比率でいると思うのですよ(^o^)/
とても多くの人々の間で、400年間保たれる秘密、という想定はかなり漫画チック。そうか、漫画ならいいのか。たしかに、劇画やアニメにはよく似合いそうな、空前絶後のストーリー展開ではあります(^o^)/
(*):「万城目学」~Wikipedia より
さて、今日は山形交響楽団のモーツァルト定期を聴きにいく予定。ホルン協奏曲には、八木さんがソロで出演の予定。楽しみです。
会計検査院の調査官3名と、社団法人OJOに代表される豊臣家のプリンセスを守る大阪の男たちの戦いのお話です。会計検査院の調査官である松平と旭の優秀なエリートぶりと、対照的な鳥居のおかしみ、大阪の空堀中学の二年生、性同一性障害に悩む真田大輔と、彼を理解する行動派の橋場茶子、大輔の父親である真田幸一の朴訥な人柄など、物語としての筋立て、道具立ては十分です。
日本国の内部にある二重国家「大阪国」。その秘密は親から子へ、厳粛に伝えられる、という想定です。でもね~。でも、エントロピーは増大するのですよ。物事は乱雑なほうへ向かうのが通例です。口から先に生まれて来て、およそ秘密というものを保つことができない、しゃべりたくってしょうがない大阪人というのが、一定の比率でいると思うのですよ(^o^)/
とても多くの人々の間で、400年間保たれる秘密、という想定はかなり漫画チック。そうか、漫画ならいいのか。たしかに、劇画やアニメにはよく似合いそうな、空前絶後のストーリー展開ではあります(^o^)/
(*):「万城目学」~Wikipedia より
さて、今日は山形交響楽団のモーツァルト定期を聴きにいく予定。ホルン協奏曲には、八木さんがソロで出演の予定。楽しみです。