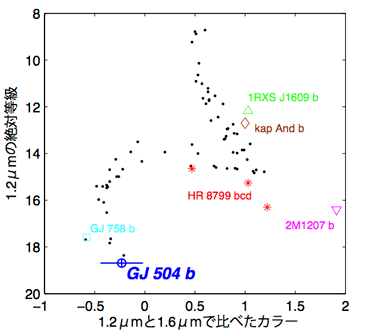(独自動車大手フォルクスワーゲンの車)

3月1日、ドイツが2つのリスクに直面している。米国による自動車輸入関税の大幅引き上げ、そして合意なきブレグジットだ。写真は輸出される独自動車大手フォルクスワーゲンの車。独エムデン港で昨年3月撮影(2019年 ロイター/Fabian Bimmer)
① ""焦点:強国ドイツは景気後退の瀬戸際か、関税と離脱の二重苦で""
2019年3月6日 / 11:38 / 3時間前更新
Michael Nienaber
[ベルリン 1日 ロイター] -
ドイツが2つのリスクに直面している。米国による自動車輸入関税の大幅引き上げ、そして合意なき英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)だ。欧州随一の経済大国にとって、黄金の成長期に終止符を打ちかねないダブルパンチだ。
メルケル首相と閣僚たちは、最悪のシナリオが実現した場合に備え、その影響を緩和すべく水面下で動いている。
ドイツ経済が停滞、あるいはリセッション(景気後退)にまで至ることがあれば、ユーロ圏全体の足かせとなり、欧州中央銀行(ECB)による金融緩和政策からの出口戦略も不透明になってくる。
ドイツ財務省の文書によれば、景気減速により税収がこれまでの試算を下回ることで、ドイツ政府はただでさえ2023年までに最大250億ユーロ(約3兆1700億円)の財政赤字を抱える恐れに直面している。
とはいえ、ドイツ政府高官が匿名を条件にロイターに語ったところでは、ショルツ財務相はリセッションの脅威を重く見て、財政赤字に関する厳格なルールを修正する構えを見せているという。
「二重苦が現実のものになるとすれば、われわれも何かマジックを使いたいところだ」とこの高官は言い、政府が財政出動措置を検討していることを示唆した。
さらにこの高官は、「この状況は、新規起債ゼロと債務ブレーキというわが国の政策にとって試金石となるだろう」と付け加えた。
② ドイツは昨年辛うじてリセッションを免れたものの、米国の自動車輸入関税が25%に引き上げられるリスク、そして英国がEUとの今後の通商関係に関する合意なしに3月29日にEUを脱退するリスクのどちらについても、特にぜい弱な立場にある。
連邦統計局のデータによれば、ドイツの国内総生産(GDP)の半分近くを輸出が稼ぎ出しており、中でも自動車は年間2300億ユーロという圧倒的な主要輸出品だ。
同じデータによれば、昨年、ドイツ車にとって最も重要な輸出先は米国であり、輸出金額は272億ユーロだった。中国の247億ユーロ、英国の225億ユーロがこれに続く。
ドイツ自動車工業連盟(VDA)のデータによれば、台数ベースでは英国が66万6000台で首位、米国が47万台で2位となっている。
「米国第一」の旗印を掲げるトランプ米大統領は、巨額のドイツ貿易黒字を繰り返し非難しており、米国政府がEUとの通商合意に達することができなければ、欧州車に関税をかけると警告している。
2月中旬に米商務省がトランプ大統領に提出した非公表の報告書は、輸入自動車・自動車部品を米国の国家安全保障に対する脅威と指定することにより、これらに関税をかける道を開くものと広くみられている。
トランプ氏はこの勧告に基づいて行動するかどうかを90日以内、つまり5月中旬までに判断することになっている。
一方、合意なきブレグジットという事態になれば、英国は世界貿易機関(WTO)ルールが適用される第3国としての地位に戻ることになる。
すると、ドイツ車に対する英国の輸入関税は約10%に上昇することになる。トラックおよびピックアップトラックに関しては、最高22%の関税が適用される。また、港湾・国境で税関検査が行われることにより、ジャストインタイム方式のサプライチェーンに混乱が生じる可能性が高い。
「合意なきブレグジットというシナリオは、EU27カ国の企業および従業員にとって深刻であり、重大なリスクをもたらすだろう」とVDAの広報担当者は言う。「ロジスティクスが大きく損なわれ、高い通関コストが発生する」
★<悪循環>
コメルツバンクとIFO経済研究所それぞれの試算によれば、2つのシナリオが両方とも現実になれば、複合的な影響により、長期的にはドイツGDP成長率が0.7%ポイント下がる可能性がある。
すでにドイツ政府は、今年のGDP成長率が2018年の1.4%から1%に減速すると予測している。だがこの予測は、米国との通商摩擦のエスカレート、合意なきブレグジットの両方を回避できるという前提に基づいている。
「無秩序なブレグジットの場合、不確実性の増大や調整プロセスなどの短期的な悪影響が予想されるが、これらを数値化することは難しい」と、ある経済関係省庁の広報官は語った。
だがこの広報官によれば、複数の研究では、合意なきブレグジットは、長期的にドイツの成長率に年0.2%ポイントの打撃を与えるという試算が出ているという。ドイツ車に対して米国の関税引き上げが与えるとみられるダメージについては、具体的な数値を示さなかった。
③ 独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)(VOWG_p.DE)のハーバート・ディエス最高経営責任者(CEO)は、英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューの中で、米国の関税引き上げは同社にとって年間25億ユーロのコスト増につながる可能性があると述べた。
IFO経済研究所の試算では、トランプ政権が輸入車に対して25%の関税をかけようとしているのであれば、ドイツ車の対米輸出は長期的に約50%も減少する可能性があるという。
コメルツバンクのエコノミスト、イエルク・クレーマー氏は、「ドイツのGDP成長率を約0.5%ポイント引き下げることになるだろう」と話す。
エコノミストらは、米国の関税引き上げと合意なきブレグジットが重なった場合、企業の景況感と消費意欲にも打撃が及び、ドイツ経済全体が悪循環に陥るだろうとみている。
経済に対する先行き不安が労働市場にも波及するようだと、国内経済の大黒柱である家計消費もぐらついてくる、と市場調査会社GfKのロルフ・ビュークル氏は警鐘を鳴らす。
「年間を通じて、労働者が、自分もいつ解雇されるか分からないという印象を抱くようになれば、消費の雰囲気にも直接的な悪影響が生じる」と同氏は言う。
さらに、成長率の低下は税収の低下を意味することから、経済を悪循環から救い出すような大規模な財政出動を政府が取りまとめる力も限定されることになる。
連立与党の関係者がロイターに語ったところでは、ショルツ財務相は現在、4年間で50億ユーロの優遇税制により、企業の研究開発投資を支援することを狙った法案を策定中だという。
この計画の財源は想定されている財政黒字であり、その分、他の財政出動措置を講じる余地は小さくなる。
「政府がリセッションに対抗するために新たな財政出動措置を提示したいと考えても、選択肢は2つしかない。税金を上げるか、新規国債を発行するかだ」と、メルケル連立政権のある与党議員は匿名でこう語った。
(翻訳:エァクレーレン)
※ 世界経済と外国の経済について、あれこれと情報とデーターをチェックしていますが、
バラ色でなくても明るい展望を書いている記事は、皆無とは言いませんが圧倒的に
少ないです。