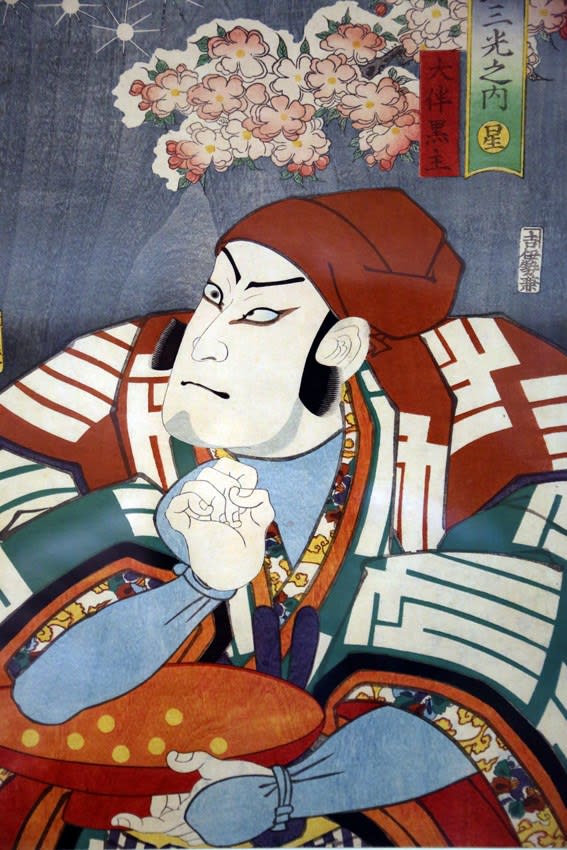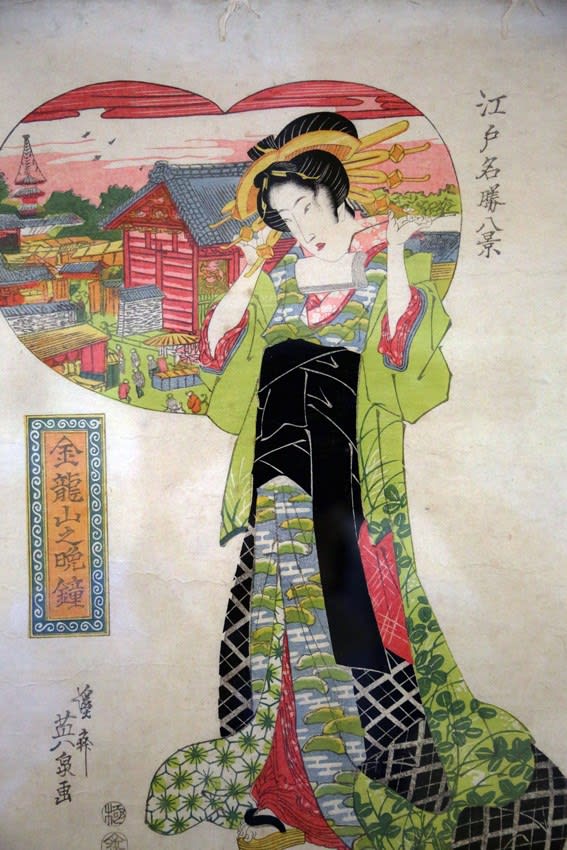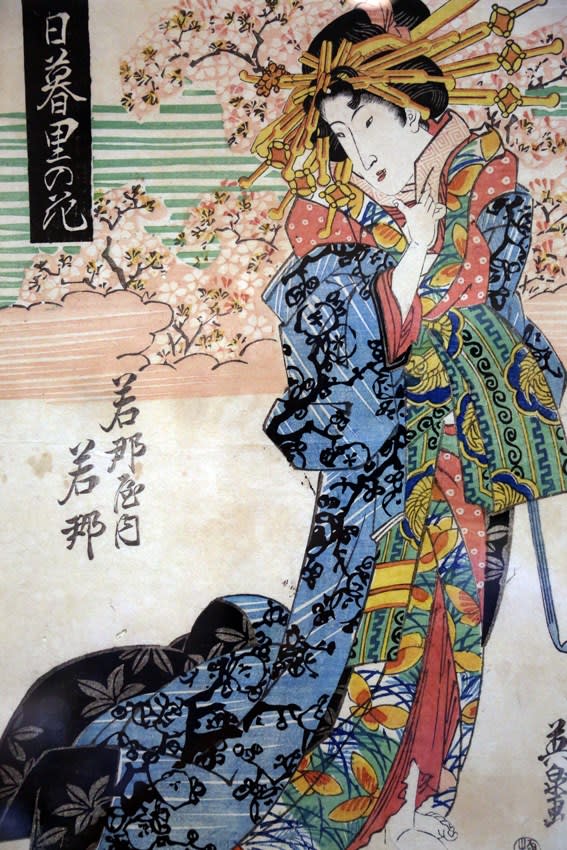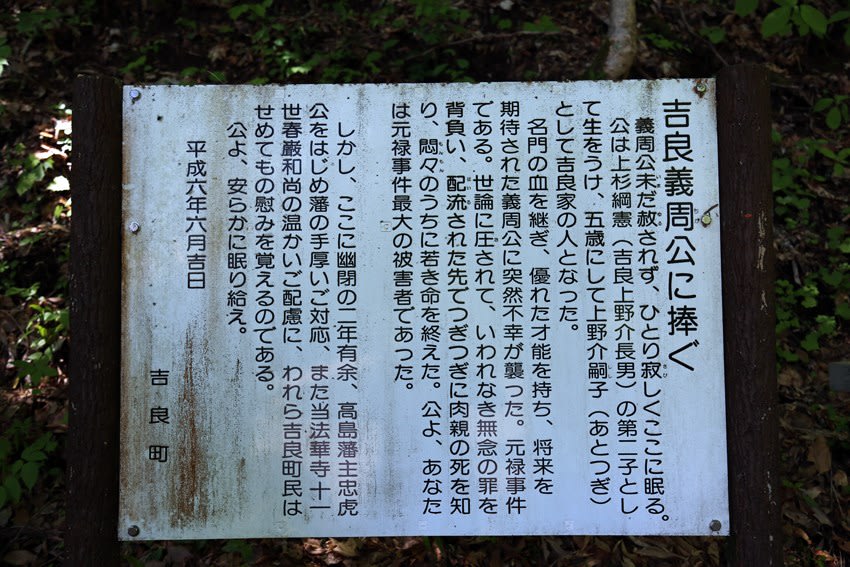崇福山 護国院 安楽寺
国宝の三重塔を所有する寺院である
十数年前に一度訪れたことがあったが三重塔の拝観時間を過ぎていたため観ることができなかった
黒門
安楽寺境内の入口にあたる。扁額は山号の「崇福山」、寛政4年(1792)の建立
黒門の奥に無料駐車場がある

山門
石段を上がると山門が見える

鐘楼

境内の庭木に興味が無い私だが、見事に整備されている

本堂

扁額には寺名の「安楽禅寺」

お堂の内部の様子

経蔵

経本は寛政5年宇治の万福寺より購入した朱塗りの輪蔵に保管してある


傳芳堂(文化財収蔵庫)

木造惟仙和尚坐像(重文)と木造恵仁和尚坐像(重文)が安置されている

私の上半身が写っているが、前に立たなければガラスに反射して見えないのだ


水子地蔵尊

三重塔に近づくには更に石段を上がらなくてはならない

この塔は「八角三重塔」で写真では見たことがあったが、実物を見るのは今回が初めてになる



八角三重塔(国宝)
日本に現存する近世以前の八角塔としては唯一のものである

全高18.75メートル。構造形式は八角三重塔婆、初重裳階付、こけら葺である

四重塔にも見えるが一番下の屋根はひさしに相当する裳階である


この日は日差しが強く、周辺も確認したが、この場所以外での撮影は厳しかった

名残惜しかったが塔を後にした


山門に向かう、庭の好きな人はこの場所にいるだけでも楽しくなるだろう

全国に13ある国宝の三重塔。今回が11番目になる、残り2つとなった

撮影 平成29年5月21日
国宝の三重塔を所有する寺院である
十数年前に一度訪れたことがあったが三重塔の拝観時間を過ぎていたため観ることができなかった
黒門
安楽寺境内の入口にあたる。扁額は山号の「崇福山」、寛政4年(1792)の建立
黒門の奥に無料駐車場がある

山門
石段を上がると山門が見える

鐘楼

境内の庭木に興味が無い私だが、見事に整備されている

本堂

扁額には寺名の「安楽禅寺」

お堂の内部の様子

経蔵

経本は寛政5年宇治の万福寺より購入した朱塗りの輪蔵に保管してある


傳芳堂(文化財収蔵庫)

木造惟仙和尚坐像(重文)と木造恵仁和尚坐像(重文)が安置されている

私の上半身が写っているが、前に立たなければガラスに反射して見えないのだ


水子地蔵尊

三重塔に近づくには更に石段を上がらなくてはならない

この塔は「八角三重塔」で写真では見たことがあったが、実物を見るのは今回が初めてになる



八角三重塔(国宝)
日本に現存する近世以前の八角塔としては唯一のものである

全高18.75メートル。構造形式は八角三重塔婆、初重裳階付、こけら葺である

四重塔にも見えるが一番下の屋根はひさしに相当する裳階である


この日は日差しが強く、周辺も確認したが、この場所以外での撮影は厳しかった

名残惜しかったが塔を後にした


山門に向かう、庭の好きな人はこの場所にいるだけでも楽しくなるだろう

全国に13ある国宝の三重塔。今回が11番目になる、残り2つとなった

撮影 平成29年5月21日