きのう、台風 が来るかもしれないというので、職場のテレビ
が来るかもしれないというので、職場のテレビ を買いに行ってきました(これまで自社専用のテレビがなかった
を買いに行ってきました(これまで自社専用のテレビがなかった )。
)。
事前に、購買担当の人に、家電量販店の法人営業へ価格や在庫を問い合わせてもらったところ、一番の売れ筋という32型のテレビは、その量販店の他の営業所も含めて、在庫ゼロ
結局、在庫が1台だけ残っていたという26型の国産テレビ(BSデジタルにも対応。ただし職場にはBSアンテナがない… )を買ってきました。
)を買ってきました。
自宅の「地デジ化」が今年3月の「家電エコポイント駆け込み」で完了(記事はこちら)していた私、テレビの相場観がすっかり薄れていまして、5万円も出せば(そして在庫があれば)32型のテレビが買えるくらいまで価格が下がっているとは知りませんでした。
今年3月の時点では、
5万円程度で買える他の20型はBSデジタル非対応だし、BSデジタル対応モデルはサイズを落としても7万円前後もします。
結局、何も買わずにとぼとぼと帰宅しました
だったというのに、なんとも恐ろしい価格低下のスピードです (家電エコポイントの終了が価格低下のきっかけだったらしい)
(家電エコポイントの終了が価格低下のきっかけだったらしい)
「地デジ完全移行へ最後の商戦 家電量販店もメーカーもうまみ少なく」と題したSankei Bizの記事によれば、
24日の地上デジタル放送への完全移行(岩手、宮城、福島の3県除く)があと3日に迫り、薄型テレビが“特需”に湧いている。家電量販店ではテレビ売り場の在庫が一掃され、品薄状態が続く。ただ、単価下落は続いており、販売店にとってうまみは少ない。メーカーも出荷数の増加が利益に直接結び付かず、「いくら作ってももうからない」(大手)状態に陥っている。
として、
過当な価格競争はメーカーにも大打撃を与えている。国内シェア首位のシャープは平成22年度、テレビ事業で何とか黒字を死守したものの、片山幹雄社長が「勝っても赤字の市場では戦わない」と言い切るように、もはや大きな収益事業とは位置付けていない。
ソニーの事情も深刻だ。テレビ事業は16年度から7年連続で赤字を計上。今期も東日本大震災の影響などで黒字転換は難しいと見込む。パナソニックも、22年度のテレビ販売台数は2023万台と過去最高を記録したが、テレビ事業は3年連続で赤字だった。
だそうで、まさしく「利益なき繁忙」ってヤツです。
商品を開発する人、生産する人、販売する人(他に管理・物流担当の人)の働きや苦労に見合った価格や商品の価値に見合った価格と、販売価格とのギャップが広がっています。
「安く買えた 」と喜んでいる消費者にしても、こんなデフレが続けば、日本経済がガタガタ&スカスカになって、自分の仕事や収入にも影響してくることでしょう。
」と喜んでいる消費者にしても、こんなデフレが続けば、日本経済がガタガタ&スカスカになって、自分の仕事や収入にも影響してくることでしょう。
やはり、「安ければいいのか?!」(こちらの記事のタイトル)と疑問を呈したい私です。

家のテレビ&レコーダーは地デジ化が完了した私ですが、TV付きナビを積んでいる愛車 はどうかといいますと、
はどうかといいますと、

です… (元ネタはこちら)
(元ネタはこちら)
もともとクルマの中でテレビを見ようと思ったことがほとんどない私にとって(例外中の例外はこのとき)、今のナビだってパッケージとしてテレビ(アナログ)がついていたというだけの話。
私が今のクルマを買った4年前にも、オプションで「地デジチューナー」がありました。でも、

「取付費・消費税込み」で123,900円
いつ・どこで使うあてもなく、必要性も感じられない地デジチューナーに12万円以上も払えますか
 さすがに今は車載用地デジチューナーの価格もこなれているようですが、それでも取付費を考慮すれば4万円はかかるでしょう。
さすがに今は車載用地デジチューナーの価格もこなれているようですが、それでも取付費を考慮すれば4万円はかかるでしょう。
ほぼ毎日3時間以上運転するようになった愛車とはいえ、やはり、クルマの中でテレビを観たいシチュエーションは想像しがたく、愛車の地デジ化は見送りデス
ところで、帰宅時、車内にいくつものテレビ(ディスプレイ?)をつけているクルマを見かけました。
運転席付近に3つくらい、そして、後部座席に向けて、5型くらいの小さなディスプレイが左右にそれぞれ3つくらい取り付けられているのですよ。
まるでテレビ局の副調整室の風情…
う~む、、、この方の嗜好が理解できない…
ちなみに、道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)にこんな規定があります。
五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
つまり、クルマが止まっているときや緊急の場合を除き、携帯電話を操作・通話したり(ハンズフリーを除く)、ナビや車載テレビを注視してはいけない ことになっています。でも、「注視はダメ
ことになっています。でも、「注視はダメ だけれど、チラ見は可
だけれど、チラ見は可 」と解釈できますな
」と解釈できますな
私のアナログテレビ付きナビは、メーカーオプション品ですので、走行中のナビの操作機能・表示機能は限定されていますし、テレビはギアを「N」か「P」に入れてサイドブレーキをかけないと画面が映りません。
「同乗者用」という触れ込みで走行中でも車載テレビを観られるようにするキットが販売されていますが、そんなものを買ってまで、テレビを観たいとは思わない私であります。
 に番宣していた番組
に番宣していた番組 が二つありまして、一つは綾瀬はるか主演の大河ドラマ「八重の桜」で、もう一つが、大沢たかお主演のBS時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」でした(主演2人の組み合わせ、否応なく「JIN -仁-」を思い出します)。
が二つありまして、一つは綾瀬はるか主演の大河ドラマ「八重の桜」で、もう一つが、大沢たかお主演のBS時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」でした(主演2人の組み合わせ、否応なく「JIN -仁-」を思い出します)。 私は「八重の桜」に勝るとも劣ることなく「火怨・北の英雄 アテルイ伝」に期待しておりました
私は「八重の桜」に勝るとも劣ることなく「火怨・北の英雄 アテルイ伝」に期待しておりました
 (ただし、根拠なし…
(ただし、根拠なし… )
) と自宅のブルーレイ・レコーダーで録画予約しておいて、きょう、帰宅
と自宅のブルーレイ・レコーダーで録画予約しておいて、きょう、帰宅 すると早速見始めたのですが…。
すると早速見始めたのですが…。



 も演出
も演出 も、昔見せられた「小中学生用の教育ドラマ」
も、昔見せられた「小中学生用の教育ドラマ」 レベルのデキ…
レベルのデキ…
 ほどで見続けるのが鬱陶しくなってしまいました
ほどで見続けるのが鬱陶しくなってしまいました
 みたいな感じです。
みたいな感じです。












 も作成済みです
も作成済みです
 」
」 として流れる
として流れる だと私は確信
だと私は確信


 の酔いが廻っていましたので、きょう、ライブラリー
の酔いが廻っていましたので、きょう、ライブラリー
 )を含めて、今となってはかなり興味深い内容でした。
)を含めて、今となってはかなり興味深い内容でした。
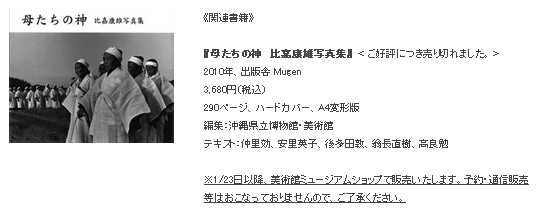






 ある程度予想されたその後の顛末:2012/06/21
ある程度予想されたその後の顛末:2012/06/21 

 しましょう。
しましょう。



 しながら
しながら そんな風に、認識を改めた今年のニューイヤーコンサート、
そんな風に、認識を改めた今年のニューイヤーコンサート、






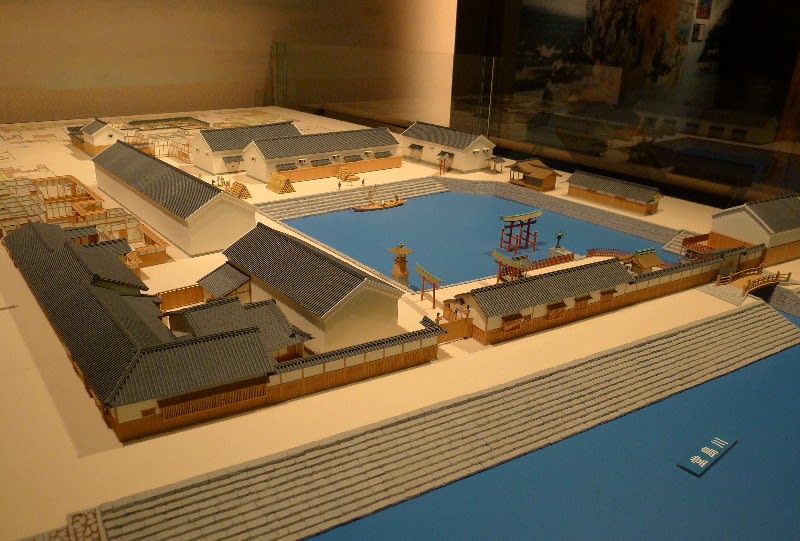

 浴びてTV
浴びてTV

 が来るかもしれないというので、職場のテレビ
が来るかもしれないというので、職場のテレビ )。
)。

 (元ネタは
(元ネタは


 ことになっています。でも、「
ことになっています。でも、「 」と解釈できますな
」と解釈できますな
 」が一つ増えました
」が一つ増えました





