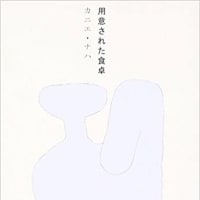このなかで主人公の小説家「古義人」の母親が、ある文学研究者のインタビューに答える言葉が秀逸です。
大変に見事な言葉ですが、これも「ウソ」でせうか?以下は引用です。
「古義人」の書いておりますのは小説です。小説はウソを書くものでしょう?
ウソの世界を思い描くのでしょう?そうやないですか?
ホントウのことを書き記すのは小説よりほかのものやと思いますが・・・・・・
あなたも『不思議な国のアリス』や「星の王子さま』を読まれたでしょ?
あれはわざわざ、実際にはなさそうな物語に作られておりますな?
それでもこの世にあるものなしで書かれておるでしょうか?
「古義人」は小説を書いておるのですから。ウソを作っておるのですから。
それではなぜ、本当にあったこと、あるものとまぎらわしいところを交ぜるのか、と御不審ですか?
それはウソに力をあたえるためでしょうが!
ウソの山のアリジゴクの穴から、これは本当のことやと、紙一枚差し出して見せるでしょうか?
死ぬ歳になった小説家というものも、難儀なことですな!
ここまでが引用です。大分以前、朝日新聞に高橋源一郎が書いた大江健三郎の書評も同時に思い出します。
新聞の切り抜きが行方不明なので、うる覚えのメモですが
「事実にほんの少しの嘘を加えることで、より真実に近ずくのではないか。」というような言葉でした。
なぜ「童子」なのか?小説家「古義人」の幼少年期、こころのなかに二人の童子がいました。
一人は故里の山の樹に行ったまま帰らず、もう一人の残された淋しい童子は故郷を離れてたくさん勉強をしましたし、
旅をしたり、友や家族を愛したり、一生懸命に「ウソ」の小説を書いたのでした。
それはきっともう一人の童子のためでしょう。
それで淋しい童子は、もっと淋しくてなってしまうのでした。
(2002年・講談社刊)