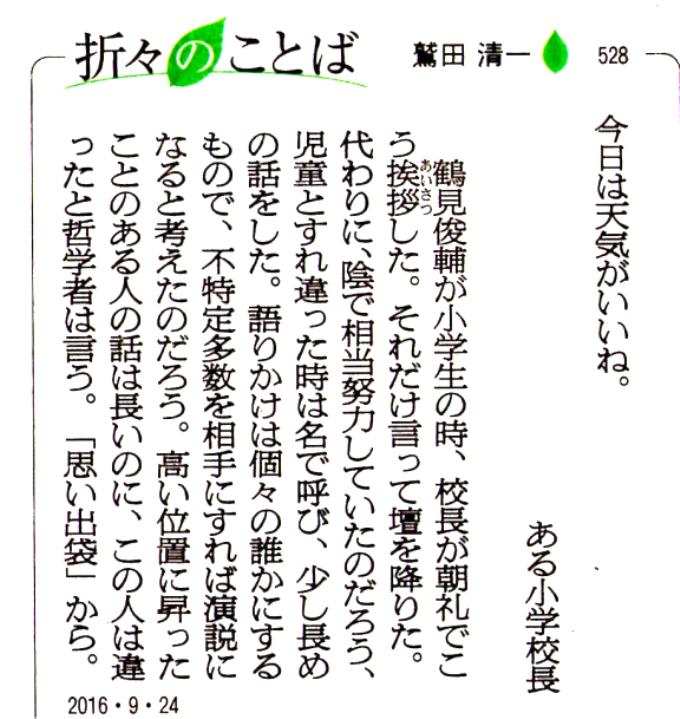この1冊は、詩人石原吉郎の「死」に内村剛介が手向けるために書かれたものである。しかしながら、まさに、良い意味での「死者を鞭打つ」言葉に満ちていたのでした。驚いた。
詩人の言葉の世界は甘いのだと、ロシア文学者が鞭打つ。確かにそうかもしれないと思えてくるのも不思議だ。様々なロシア文学を例に挙げながら、あるいは「鳴海栄吉」の詩を紹介しながら、内村剛介の強い言葉が押し寄せてきました。これには抗う言葉が私にはない。
もしも、生きて石原吉郎がこの言葉の波に、立ち尽くすとしたら、彼は立ち続けることができただろうか?内村剛介の「言葉の強さ」はどこからくるのだろう?
ロシア文学者としての確固たる歴史的視点。抑留者としての石原吉郎との生き方、考え方の相違は大きい。内村剛介の存在を無視して、これからの石原吉郎の言葉を読むことは、私には不可能なことに思えてきました。
これが危険なのかどうか?迷いつつ……。
話題は変わりますが、内村剛介の本「生き急ぐ・スターリン獄の日本人」と「失語と断念―石原吉郎論」の2冊を読んだだけで、「イワン」という名前がこれだけ登場しました。「イワン」とは、何か?
『カラマーゾフの兄弟』 ドストエーフスキー
父親のフョードル・カラマーゾフ
長男のドミートリィ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ
次男の
イワン(イヴァン)・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ
三男のアレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマーゾフ
『イワンの馬鹿』 トルストイ
『イワン・デニーソヴィチの一日』 ソルジェニツィン
『イワン・イリノッチの死』 トルストイ
全部、読まなくてはいけないような気がする。(既読もあるが…)内村剛介の言葉は怖い。けれども、その言葉の勢いに付いて行きたいような魔力がある。
話題はかわりますが、北条民雄の「いのちの初夜」を石原吉郎は愛読していたという。内村剛介もこの本には深い感銘を受けているという。ここに共通点があったことは嬉しい。内村は、北条以前に「いのち」と正面から向き合うような小説を書いた作家はいないとまで言う。
さて、最後に引用します。
『日本の荒廃は戦中の日本軍に日本人の在りようそのものに萌していたのであって、敗戦はそれをあらためてあられもなく示したにすぎない。日本はそして日本人はみずからをすでに裏切っていたのである。そののち石原がシベリアで見たものはもうひとつの世界大の荒廃であったというだけのことだ。だからサンチョ・パンサ石原にとっては戦前・戦中・戦後とかいうかっこいい区分はそもそもナンセンスなのであった。これは書くべき詩を持とうにももはや持ちようもないという自覚でもある。だが、このこと自体を示せば日本はまだ「詩」が出来上がるのであった。この逆説を彼ははじめおずおずと示した。だが、示してしまうとそれは“戦後”日本ではいくぶん新鮮に映るのであった。』
(1979年 思潮社刊)