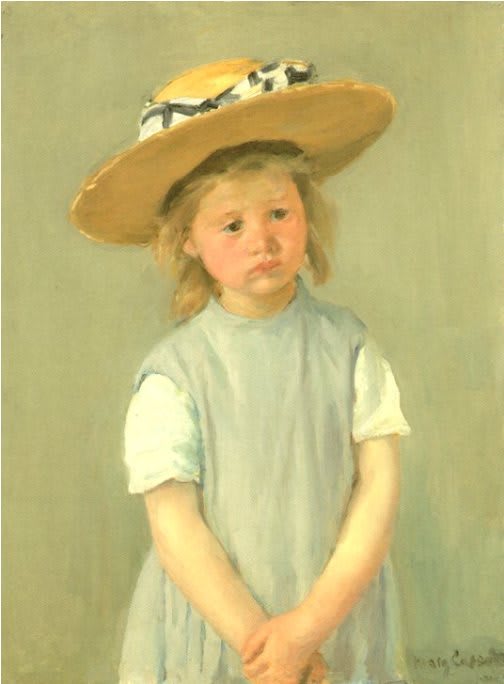
小学校のベテラン教師(と、言ってもいいと思う。)お2人と、吉本隆明氏の対談です。
子供の高学歴、一流社会人を目指す母親たちへの警告であり、
小学生を育て、教育する場合の教師の責任と母親の責任を秤にかければ母親の責任の方が重い
ということを、まず母親は自覚しよう。
子供の人間としての基本的支柱は6歳までにきまると吉本さんはおっしゃる。
犯罪の低年齢化、時代病、あるいはイロイロな心の病。
それはおそらく教師の責任ではないだろう。
教師は児童の規範ではない。つまり本のタイトル通りに子供はすでに知っているのだ。
にもかかわらず、教師は教師たろうとするし、母親はいつまでも母親という主張に終わりがない。
子供は「ぜーんぶわかってる」んだから、
歴史とか科学とか算数とか、国語の基本を教えればいいわけで、
教師は児童の支配者でもなく、さらに母親は子離れをするべき。
子供の潜在的な力を信じるべき。
あああ。わたくしは子育てはとうに終わっているのだが、
それについてのさまざまな論考は果てしなく続く。本も出版される。そしてどれも見落としがある。
(当然、わたくしも我が子育ての経験から考えるしかないのだが…。)
こうした問題がクローズアップされた背景になにがあったのか?
それはおそらく、女性の社会進出によるものだと思える。
男が働いて、女性が家事&育児に専念するという図式の崩壊と同時に、
大家族制度の重圧からの解放が、マイナス面にも表出したからか?
しかし時代は戻ることはできない。
戦後からすでに約70年の歳月は流れた。
新しいとか古いとかという時代ではなく、底に流れる人間の普遍性を見つめていたいと思う。
(2005年・批評社刊)










