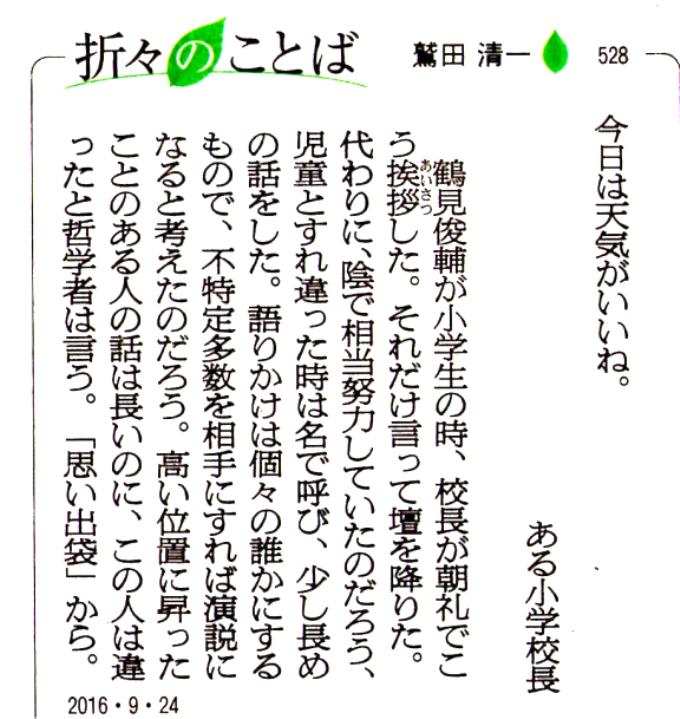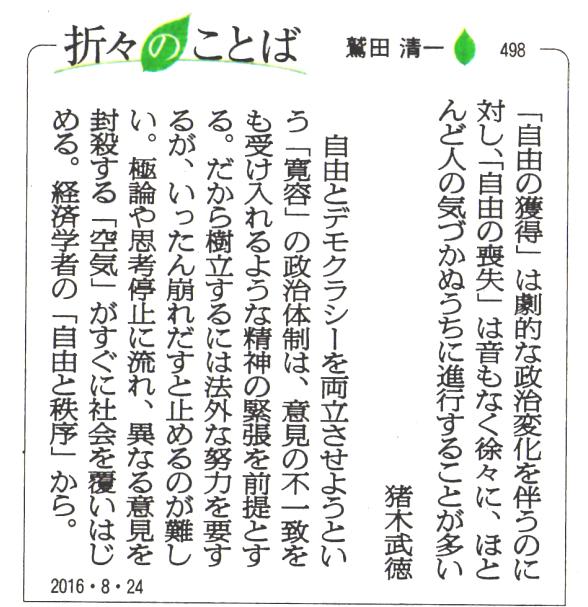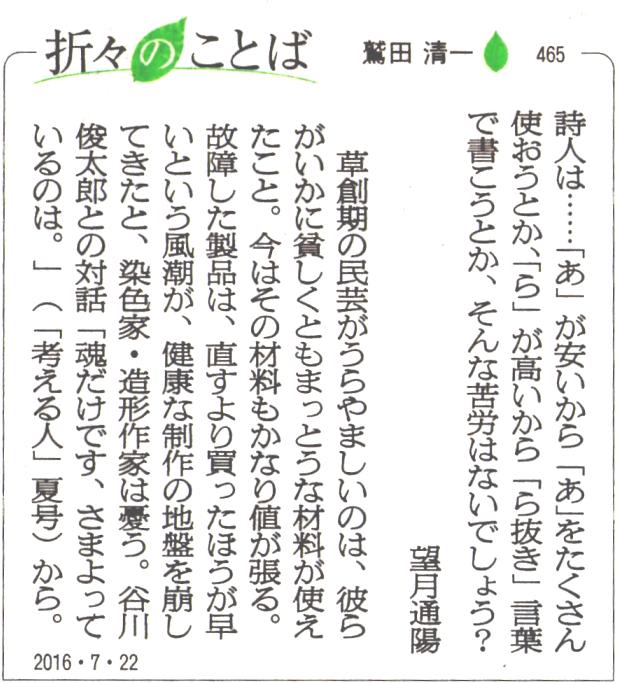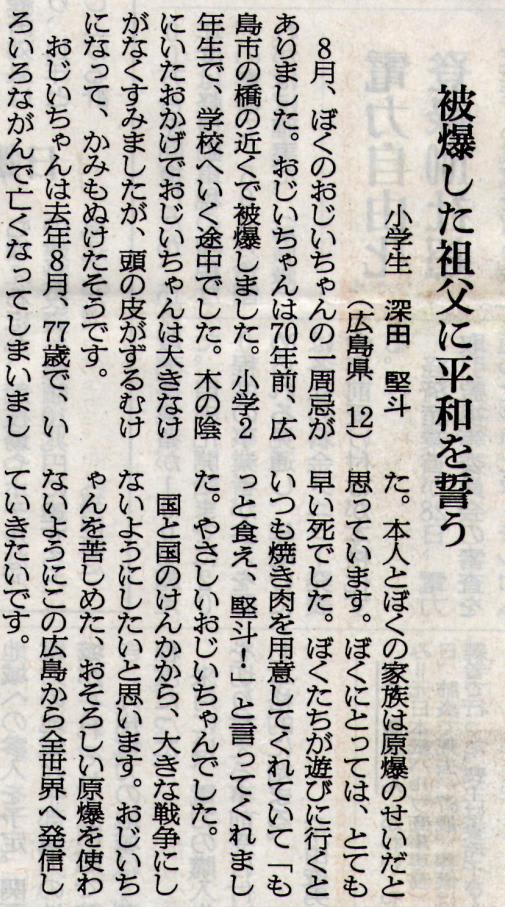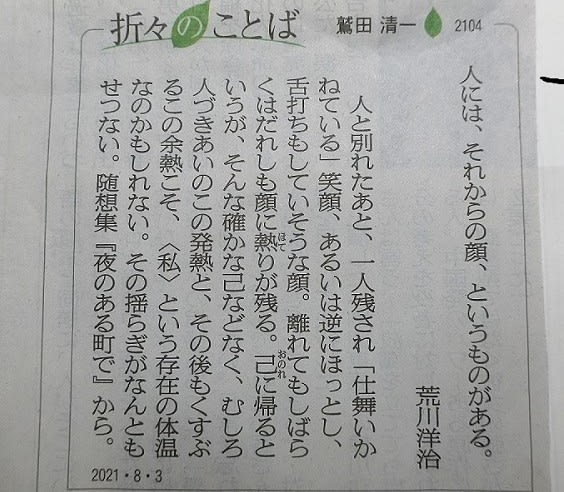
深く納得しました。

オリンピックの柔道の試合を観ながら、亡き父の言葉をしきりに思い出していました。
父は上京後の大学時代は、講道館で柔道の稽古に励み、時には警察官の柔道指導も
やっていたらしいのです。
小柄な父は、オリンピックの柔道の試合が、選手の体重に応じて相手が決められる方法に、
かなり抵抗があったようでした。
それを、懐かしく思い出していました。

深く深く納得しました。
病人にも、それぞれ個性があって、病気との向き合い方に個性が現れる。
病人の看護人への思いも、幼い日からの母親への依存がそのまま表れる。

新しい詩集を出して、後悔と期待がないまぜになっていて、あまりよろしくない心理状態になる。
ひどく、つまらない。いや、これでいい。様々な波が寄せては返す。
このフォスターの言葉に救われるほどに、私は優れた詩人でもなくて、また悲しい。
言葉よ。届け。