
発達は、親や会社や世間に都合のいい「偽りの自分」が育つことではありません。「本当の私」、「ありのままの私」が育つことです。ですから、いつでも何度でも、その「本当の私」との対話、内省が大事になりますよね。
The life cycle completed 『人生の巡り合わせ、完成版』、p59の第4パラグラフから。
このハシゴのライフサイクルの性質が反映することを期待されるのは、今まで示した言葉すべてが、言葉として一貫している、ってことです。そして、実際に、hope「困難があっても、希望を失わないこと」と fidelity「困難があっても、信念に忠実であり続けること」, それから、care「低みに立たされている者を大事にすること」と言った言葉は、言葉そのものに内的な論理がありますが、その内的論理は、発達上の意味を確かに肯定してくれているように思います。hope「困難があっても、希望を失わないこと」は、「期待している願い」ですから、ある種の期待を呼び覚ます経験をする、ハッキリとはしないけれども本能に備わった、人を駆り立てるものと一致する言葉です。しかも、最初の根源的な人間力と自我が発達する根っこが、最初の発達上のアンチテーゼ、すなわち、根源的信頼 と 根源的不信 がぶつかり合う葛藤の結果から生じることとも一致します。
このように、エリクソンが発達に当てはめた言葉は、生涯に渡って一貫しているだけではなくて、発達上の危機、アンチテーゼがぶつかり合う葛藤から生じる結果としても意味があり、それが1つの倫理的な人間力ともなる、という、まあ、実に多義的で贅沢な意味を持つと同時に、具体的に人間像も示しうるものなんですね。実にうまくできていますよね。
それはね、エリクソンが、人間の発達、自分自身の発達を、よくよく見て、繰り返し考え続けた成果だと言えるでしょうね。
倫理的な私は、そのアンチテーゼのぶつかり合い、葛藤から生じる、としたのも、人間をよく知ってますでしょう。べつに、道徳を身につけるために、道徳の時間で勉強したんじゃぁ、ないんですね。葛藤から逃げないで、葛藤を自分では引き受ける中から、倫理的な私は、自ずから生まれるものなんですね。
















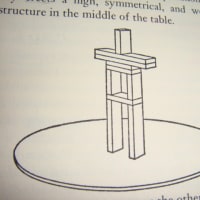










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます