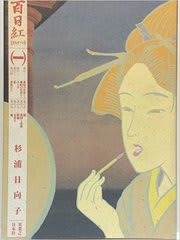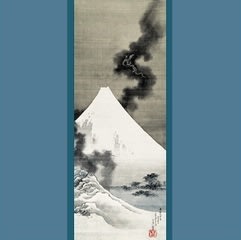久しぶりに、前のCB400SFに乗って、買い出しに行きました。
2週間ぶりだったので、最初はエンジンがかかりにくいでしたが、
チョークを引くとガソリンの独特の匂いと共に始動。
さて、と跨がってスタンドを払うと…。
…重い。
鉄の塊がずごごごごーと動く感じです。
これに比べると、今乗っているCBR250は軽い!
プラスティック製のバイクじゃないか、と思うほどです。
2週間前までは、重いなんて思わなかったのになぁ~。
進化というか、後退というか、ですね。
今日はトランポリンの日でした。
先週、うまくできなかった1回転ジャンプも
地上で練習とイメージトレーニングをしたおかげでできて、
言われている、すべきジャンプも冷静に聞けて(私比…)
進歩した気がした今週でした。
一緒に練習している子どもたちは、保育園の子~小学生までと幅広く、
みんなそれぞれ、2級だ3級だと技のあるジャンプを練習しています。
このくらいの子どもたちは、自分以外の人が練習していても、
それが自分と同じ級であっても、参考のためにじーっと観察したり、
ライバル心で相手はどのくらい?と見るということがあまりなく、
淡々と体育館の床で寝そべって、宿題したり、おしゃべりしたりして過ごしています。
私は、というと、
一番高齢な上に初心者、しかも運動神経は良くはないので、
自分のとき以外も、じーっと観察したり、どんな注意を受けているか聞いたりしています。
子どもたちも、自分がしないときは見たらいいのにねぇ、と思う一方、
自分が子どもの頃も、他の人の技を盗むべく、じっと観察するような子ではなかったな、と思い出しました。
子どもには、体の柔軟性もあるし、練習する時間も取ろうと思えばたくさんあります。
大人と違って、体力もあるし、週1のトランポリンで体が痛いなんてこともないでしょう。
大人は、限られた時間と先の見えつつある寿命を前に、
よく見て、効率的に学ぼうとする姿勢を取りがちなのでしょう。
しかし、子どもはたくさんの時間と体力があり、
できなければ、できるまでしてもいいし、繰り返すための時間がたっぷりあります。
このたっぷりの時間と体力のもと、
何度も失敗し、何度も繰り返すことが子どもの学ぶスタイルなのかもしれませんね。
大人は、時間と体力を有効に使いたくて、
そういうやり方を時として、子どもにも求めているかもしれません。
たっぷり時間と体力のある子どもにとって、
効率というのは、さしたる問題ではないと思います。
子どもが体を使うことに有効さや効率を求めすぎていないかな、
そういうことも、ちょっと考えて行こう、
そんなことも考えたトランポリン教室でした。
さて、大人のおばさんは、地道に且つ有効に練習をつづけるぞ!
とも思った、トランポリン教室でありました。
2週間ぶりだったので、最初はエンジンがかかりにくいでしたが、
チョークを引くとガソリンの独特の匂いと共に始動。
さて、と跨がってスタンドを払うと…。
…重い。
鉄の塊がずごごごごーと動く感じです。
これに比べると、今乗っているCBR250は軽い!
プラスティック製のバイクじゃないか、と思うほどです。
2週間前までは、重いなんて思わなかったのになぁ~。
進化というか、後退というか、ですね。
今日はトランポリンの日でした。
先週、うまくできなかった1回転ジャンプも
地上で練習とイメージトレーニングをしたおかげでできて、
言われている、すべきジャンプも冷静に聞けて(私比…)
進歩した気がした今週でした。
一緒に練習している子どもたちは、保育園の子~小学生までと幅広く、
みんなそれぞれ、2級だ3級だと技のあるジャンプを練習しています。
このくらいの子どもたちは、自分以外の人が練習していても、
それが自分と同じ級であっても、参考のためにじーっと観察したり、
ライバル心で相手はどのくらい?と見るということがあまりなく、
淡々と体育館の床で寝そべって、宿題したり、おしゃべりしたりして過ごしています。
私は、というと、
一番高齢な上に初心者、しかも運動神経は良くはないので、
自分のとき以外も、じーっと観察したり、どんな注意を受けているか聞いたりしています。
子どもたちも、自分がしないときは見たらいいのにねぇ、と思う一方、
自分が子どもの頃も、他の人の技を盗むべく、じっと観察するような子ではなかったな、と思い出しました。
子どもには、体の柔軟性もあるし、練習する時間も取ろうと思えばたくさんあります。
大人と違って、体力もあるし、週1のトランポリンで体が痛いなんてこともないでしょう。
大人は、限られた時間と先の見えつつある寿命を前に、
よく見て、効率的に学ぼうとする姿勢を取りがちなのでしょう。
しかし、子どもはたくさんの時間と体力があり、
できなければ、できるまでしてもいいし、繰り返すための時間がたっぷりあります。
このたっぷりの時間と体力のもと、
何度も失敗し、何度も繰り返すことが子どもの学ぶスタイルなのかもしれませんね。
大人は、時間と体力を有効に使いたくて、
そういうやり方を時として、子どもにも求めているかもしれません。
たっぷり時間と体力のある子どもにとって、
効率というのは、さしたる問題ではないと思います。
子どもが体を使うことに有効さや効率を求めすぎていないかな、
そういうことも、ちょっと考えて行こう、
そんなことも考えたトランポリン教室でした。
さて、大人のおばさんは、地道に且つ有効に練習をつづけるぞ!
とも思った、トランポリン教室でありました。