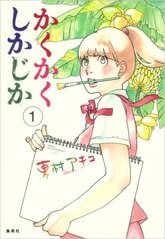2日連続で、祝い事でもないのにケーキを食べました。
ケーキって、子どもの頃は特別だったよなぁ~と思いながら、ぱくぱく。
気のいいいとこが、チーズケーキにハマって、
「世の中にこんなうまいものはない!」と、毎週土曜日に買ってきて、
私にも毎回、分けてくれたなぁ~とか思い出しながら、ぱくぱく。
贅沢な時代じゃ。
今日はフォイヤーシュタインの日でした。
1時間半の遊びやら勉強やらが終わって、保護者の方が私にお茶を出してくださいました。
それと同時に、パックに入った芋餅というものも
「家でゆっくり食べてください。」と言って、くださいました。
すると、一緒に勉強していた子どもさんが
「食べたい!」といい、同じものをまた、保護者の方が出してきてくださいました。
私が保護者の方と話しをしながらお茶を飲んでいると、
「ねー、ねー、まゆたんも食べて!おいしいよ!」と話しかけてきました。
保護者の方は私に気を使われて
「お土産だから、まゆたんはお家で食べるんだよ。」と言ってくださいました。
それでも、「ねー、食べて、食べて!」とかわいらしい顔がこっちを見てきます。
それで、私も頂いた分を開けて食べてみました。
きな粉がたっぷりで、お芋の味と餅のもちもちでとてもおいしい!
「おいしいね、きな粉たくさんで!」というと、
「でしょう!」とドヤ顔で「もう1個たべよ!」と食べています。
自分がおいしいな、と思ったものを人にも食べて欲しいと思う気持ち。
しかも、せっかくなら、一緒に食べたいな、と思う気落ち。
これって、コミュニケーションだなぁ~と思うことでした。
これからも、だれかとおいしいね、って食べたい気持ちを大切に、
こういうところから、色々な方面へできることやだれかと分かち合いたいという気持ちを育んでいけたらな、と
思いながら、芋餅を頬張ることでした。
ケーキって、子どもの頃は特別だったよなぁ~と思いながら、ぱくぱく。
気のいいいとこが、チーズケーキにハマって、
「世の中にこんなうまいものはない!」と、毎週土曜日に買ってきて、
私にも毎回、分けてくれたなぁ~とか思い出しながら、ぱくぱく。
贅沢な時代じゃ。
今日はフォイヤーシュタインの日でした。
1時間半の遊びやら勉強やらが終わって、保護者の方が私にお茶を出してくださいました。
それと同時に、パックに入った芋餅というものも
「家でゆっくり食べてください。」と言って、くださいました。
すると、一緒に勉強していた子どもさんが
「食べたい!」といい、同じものをまた、保護者の方が出してきてくださいました。
私が保護者の方と話しをしながらお茶を飲んでいると、
「ねー、ねー、まゆたんも食べて!おいしいよ!」と話しかけてきました。
保護者の方は私に気を使われて
「お土産だから、まゆたんはお家で食べるんだよ。」と言ってくださいました。
それでも、「ねー、食べて、食べて!」とかわいらしい顔がこっちを見てきます。
それで、私も頂いた分を開けて食べてみました。
きな粉がたっぷりで、お芋の味と餅のもちもちでとてもおいしい!
「おいしいね、きな粉たくさんで!」というと、
「でしょう!」とドヤ顔で「もう1個たべよ!」と食べています。
自分がおいしいな、と思ったものを人にも食べて欲しいと思う気持ち。
しかも、せっかくなら、一緒に食べたいな、と思う気落ち。
これって、コミュニケーションだなぁ~と思うことでした。
これからも、だれかとおいしいね、って食べたい気持ちを大切に、
こういうところから、色々な方面へできることやだれかと分かち合いたいという気持ちを育んでいけたらな、と
思いながら、芋餅を頬張ることでした。