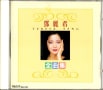10月7日(土)、地元の市民センターでの「歌謡ショー&木管五重奏」による演奏会に行ってきました。
会場に着く前までは、聴きたいのは木管五重奏のほうで、歌謡ショーはおまけのようなものと思っていました。



当日の演奏は3部構成となっていて、1部と3部が東 亜樹さんによる歌謡ショー、そして中間の2部でvivo木管五重奏となっていて、各々のステージは休憩を挟んで各々30分ほどでした。
演奏曲目はチラシにも掲載されていますが、歌謡ショーの中で歌われたのはこの中の3曲だけでしたが、ヨーデル、テレビ番組の主題歌、日本の歌謡ポップス、演歌、それに昔の歌謡曲等々、幅広いジャンルの歌を披露してくれましたが、声量があり何れの曲もしっかりした音程でうまく歌っていました。
その中で、プログラムにもあったトラックの運転手に向けて「いすゞのトラック」の歌を披露してくれました。
また、彼女は今年の7月にハワイで公演を行っていることもあり、岡 晴夫の「憧れのハワイ航路」も歌いましたが、これが一番盛り上がりました。というのも私を含めて高齢者が多かったからです。(笑)
当日配布されたプログラムにはプロフィールが記載されており、会場でも話してくれましたが、カラオケバトルや多数のテレビ、ラジオの放送に出演している実力者であることが分かりました。



3部では歌の他にトークがあり、ステージに投げてもらっては困るものとして「入れ歯」「スリッパ」「靴下」で、投げても良いものは「おひねり」や金目のものだそうで、一同爆笑する場面もありました。



また、聴衆に声かけをして、歌に併せて手拍子やコブシを突き上げる場面もありました。
そして、彼女の誕生日が10月10日であることから、多くのご年配の男性がプレゼントを渡していたのには少々驚きましたが、楽しい歌謡ショーでした。



2部のvivo木管五重奏は、地元の
ママさんによる吹奏楽メンバーの中からピックアップされた5人による演奏でした。
木管楽器の五重奏といえば、フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットとなりますが、今回はオーボエに替わってクラリネット、ホルンに替わってテナーサックス、ファゴットに替わってバスクラリネットによる編成でした。
最初はメンバー紹介と共に、各々の楽器の紹介と音出しがありました。



演奏曲目はプログラム通りで、その他、秋にちなんで「里の秋」「小さい秋みつけた」「紅葉」による唱歌メドレーが演奏されました。



こちらは管楽器のアンサンブルの響きを堪能した演奏で、ママさんたちの実力に感心しましたし、バスクラの響きが特に魅力的でした。
今回は入場料500円で、しっかり元が取れた演奏会でした。