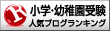Unknownさんへ
いつもコメントありがとうございます
このブログは、将来小学校受験を考えている親御さん、附属小や開智小など埼玉の小学校入試について知りたい方、さらにもっと広く幼児期の子育てに悩んでいる方たちに、私の受験体験談や開智小の生の情報を提供できれば…と思って始めたものです。
それは、受験の時、あまりに情報が少なくて不安になったり、同じ境遇の親御さんとなかなか交流ができなくて悩んだり落ち込んだりした自分自身の実体験があったからです。
でも、コメントを下さる方が、既に受験を終えられ私と同じような経験をされた方が多いので、意外でした。
同じ苦労や葛藤をくぐり抜けてきたところに共感してもらえているのだなーと思います。
このブログを目にした現役受験生のママ・パパたちもきっと共感してくださると信じて、これからも更新がんばりたいと思います
さて、学校選びの続きです。
国立と私立と公立には、それぞれのメリットとデメリットがありますので、「一般的に」はどうか?ということで、まとめてみました。
私立のメリット
・建学の精神に基づいた独特の教育を実践している
・独自のカリキュラムに基づいて授業を行い、成果を上げている(大学合格実績など)
・語学(英語)教育や情報(IT)教育が充実している
・教員の人事異動が比較的少なく、愛校心や情熱を持った教員が多い
・施設(音楽ホール、理科実験室など)や設備(冷暖房、トイレなど)が整っている
・系列校への進学が可能(有利)である
・受験がないため、精神的にゆったりと学校生活を送ることができる
・落ちこぼれを作らないための指導体制(習熟度別クラス編成、補習など)がある
・「いじめ」や「校内暴力」などの問題が比較的少ない
・基本的に塾通いはする必要がない(学校の授業で十分)
・専科の教員が充実している
国立のメリット
・学費が公立並みで安い
・大学と連携した先進的な授業が受けられる
・教員は頻繁に研修が課されるため、比較的指導力が高い
・大学の「附属」というブランド意識(親のプライド)を満たすことができる
公立のメリット
・学費が安い
・学校が近くて通学時間がかからない
・放課後、地域の友達と遊ぶことができる
・公立の中高一貫校であれば、高校受験をしなくて済む
私立のデメリット
・学費が高い(任意が多いが、寄附金もある)
・生徒の入れ替えがないため、友人関係がマンネリ化しやすい
・PTAなどの活動も含め、人間関係が閉鎖的になりがち
・受験がないので、勉強に緊張感が生じにくく間延びしがち
・(バスや電車などによる)通学時間がかかる場合がある
・地元に遊び友達ができにくい
・いったん底辺の成績になると、なかなか這い上がれない
国立のデメリット
・大学の研究機関として親も子も協力しなければならない
・学習指導要領の範囲を超えた教育(先取りなど)は基本的にできない
・教育実習生の未熟な授業が、年間の約3分の1ある
・研究授業のため、教員が留守をすることがあり、自習が多い
・募集枠が少ないため、入試が高倍率(併設の幼稚園があるとさらに高倍率)
・試験に合格しても、抽選で落ちることがある
・附属中・高に上がるときに条件がある場合(内部進学基準)がある
・附属高校がない学校もある(埼玉、千葉、横浜国立など)
・受験をするためには、塾に通わなければならない
・通学範囲に制限がある
・(バスや電車などによる)通学時間がかかる場合がある
公立のデメリット
・学習指導要領を超えた授業はできない
・国や自治体の教育改革に振り回されやすい
・校長も含め、教員の異動が激しく、実践が長続きしない
・愛校心や情熱の乏しい、いわゆる「サラリーマン」教師もいる
・いずれは中学(高校)受験が待っている
・受験をするためには、塾に通わなければならない
・上位と下位の学力差が大きく、「落ちこぼれ」や逆に「吹きこぼれ」を生みやすい
・施設や設備が貧弱だったり、古かったりする学校もある
・少子化により、いずれは統廃合の可能性もある
以上
もちろん、学校によってはあてはまらなかったりする項目もあるので、あくまで「一般論」としてどうか、ということです。
昨年、埼玉大学附属の学校説明会で繰り返し強調されていたこと。
「うちは、いわゆるエリート校ではありません。公立小学校と何ら変わりない教育を行うふつうの国立小学校です。その点を十分ご理解いただいて受験をお決めください!」
「大学の附属校であるという点をしっかり理解していただかないと、あとでトラブルになります。トラブルになるとお互いイヤな思いをします。入学後にこんなはずではなかった…ということにならぬよう、本校の性格をしっかり理解・納得して受験をお決めください!」
「勘違いしている人は迷惑なので受験しないでください!」と言わんばかり、というか、明らかにそう言ってました!
そこまで言うのか…と、少し意外でしたね。
トラブルの件も、次のような具体例を挙げていました。
・自習が多い!と苦情を言う
・私的な事情(たぶん受験のこと)を優先して、行事に参加しない
やっぱりそういう親御さんもいるんですね。
だから、最初からくぎを刺しているんでしょう。
はるか昔の話ですが…
私は小・中・高の教員免許を持っていて、大学の附属校で教育実習を経験しています。
そのとき、自分では納得のいかない授業をしてしまって、こう思ったものです。
「あーあ、こんな実習生の授業を何週間も受けさせられる子どもたちはかわいそうだなー」
でも、結局、附属って、そういう授業をしてもちゃんと勉強できる子どもたちが集まってきているんですよね。
何倍もの難関をくぐってきた子たちですから…
ちなみに、附属がなぜ抽選をするのか…というと…
上位層つまりできる子ばかりを集めたら、「研究対象」としてふさわしくないから。
ある一定の学力水準を満たしていれば、あとは適度にばらけていた方が良い。
だから、定員の3倍程度に絞ってから抽選をするのだ。
大学の時に教授から聞いた話です。
本当かどうかは責任を負えません…
いつもコメントありがとうございます

このブログは、将来小学校受験を考えている親御さん、附属小や開智小など埼玉の小学校入試について知りたい方、さらにもっと広く幼児期の子育てに悩んでいる方たちに、私の受験体験談や開智小の生の情報を提供できれば…と思って始めたものです。
それは、受験の時、あまりに情報が少なくて不安になったり、同じ境遇の親御さんとなかなか交流ができなくて悩んだり落ち込んだりした自分自身の実体験があったからです。
でも、コメントを下さる方が、既に受験を終えられ私と同じような経験をされた方が多いので、意外でした。
同じ苦労や葛藤をくぐり抜けてきたところに共感してもらえているのだなーと思います。
このブログを目にした現役受験生のママ・パパたちもきっと共感してくださると信じて、これからも更新がんばりたいと思います

さて、学校選びの続きです。
国立と私立と公立には、それぞれのメリットとデメリットがありますので、「一般的に」はどうか?ということで、まとめてみました。
私立のメリット
・建学の精神に基づいた独特の教育を実践している
・独自のカリキュラムに基づいて授業を行い、成果を上げている(大学合格実績など)
・語学(英語)教育や情報(IT)教育が充実している
・教員の人事異動が比較的少なく、愛校心や情熱を持った教員が多い
・施設(音楽ホール、理科実験室など)や設備(冷暖房、トイレなど)が整っている
・系列校への進学が可能(有利)である
・受験がないため、精神的にゆったりと学校生活を送ることができる
・落ちこぼれを作らないための指導体制(習熟度別クラス編成、補習など)がある
・「いじめ」や「校内暴力」などの問題が比較的少ない
・基本的に塾通いはする必要がない(学校の授業で十分)
・専科の教員が充実している
国立のメリット
・学費が公立並みで安い
・大学と連携した先進的な授業が受けられる
・教員は頻繁に研修が課されるため、比較的指導力が高い
・大学の「附属」というブランド意識(親のプライド)を満たすことができる
公立のメリット
・学費が安い
・学校が近くて通学時間がかからない
・放課後、地域の友達と遊ぶことができる
・公立の中高一貫校であれば、高校受験をしなくて済む
私立のデメリット
・学費が高い(任意が多いが、寄附金もある)
・生徒の入れ替えがないため、友人関係がマンネリ化しやすい
・PTAなどの活動も含め、人間関係が閉鎖的になりがち
・受験がないので、勉強に緊張感が生じにくく間延びしがち
・(バスや電車などによる)通学時間がかかる場合がある
・地元に遊び友達ができにくい
・いったん底辺の成績になると、なかなか這い上がれない
国立のデメリット
・大学の研究機関として親も子も協力しなければならない
・学習指導要領の範囲を超えた教育(先取りなど)は基本的にできない
・教育実習生の未熟な授業が、年間の約3分の1ある
・研究授業のため、教員が留守をすることがあり、自習が多い
・募集枠が少ないため、入試が高倍率(併設の幼稚園があるとさらに高倍率)
・試験に合格しても、抽選で落ちることがある
・附属中・高に上がるときに条件がある場合(内部進学基準)がある
・附属高校がない学校もある(埼玉、千葉、横浜国立など)
・受験をするためには、塾に通わなければならない
・通学範囲に制限がある
・(バスや電車などによる)通学時間がかかる場合がある
公立のデメリット
・学習指導要領を超えた授業はできない
・国や自治体の教育改革に振り回されやすい
・校長も含め、教員の異動が激しく、実践が長続きしない
・愛校心や情熱の乏しい、いわゆる「サラリーマン」教師もいる
・いずれは中学(高校)受験が待っている
・受験をするためには、塾に通わなければならない
・上位と下位の学力差が大きく、「落ちこぼれ」や逆に「吹きこぼれ」を生みやすい
・施設や設備が貧弱だったり、古かったりする学校もある
・少子化により、いずれは統廃合の可能性もある
以上
もちろん、学校によってはあてはまらなかったりする項目もあるので、あくまで「一般論」としてどうか、ということです。
昨年、埼玉大学附属の学校説明会で繰り返し強調されていたこと。
「うちは、いわゆるエリート校ではありません。公立小学校と何ら変わりない教育を行うふつうの国立小学校です。その点を十分ご理解いただいて受験をお決めください!」
「大学の附属校であるという点をしっかり理解していただかないと、あとでトラブルになります。トラブルになるとお互いイヤな思いをします。入学後にこんなはずではなかった…ということにならぬよう、本校の性格をしっかり理解・納得して受験をお決めください!」
「勘違いしている人は迷惑なので受験しないでください!」と言わんばかり、というか、明らかにそう言ってました!
そこまで言うのか…と、少し意外でしたね。
トラブルの件も、次のような具体例を挙げていました。
・自習が多い!と苦情を言う
・私的な事情(たぶん受験のこと)を優先して、行事に参加しない
やっぱりそういう親御さんもいるんですね。
だから、最初からくぎを刺しているんでしょう。
はるか昔の話ですが…
私は小・中・高の教員免許を持っていて、大学の附属校で教育実習を経験しています。
そのとき、自分では納得のいかない授業をしてしまって、こう思ったものです。
「あーあ、こんな実習生の授業を何週間も受けさせられる子どもたちはかわいそうだなー」
でも、結局、附属って、そういう授業をしてもちゃんと勉強できる子どもたちが集まってきているんですよね。
何倍もの難関をくぐってきた子たちですから…
ちなみに、附属がなぜ抽選をするのか…というと…
上位層つまりできる子ばかりを集めたら、「研究対象」としてふさわしくないから。
ある一定の学力水準を満たしていれば、あとは適度にばらけていた方が良い。
だから、定員の3倍程度に絞ってから抽選をするのだ。
大学の時に教授から聞いた話です。
本当かどうかは責任を負えません…