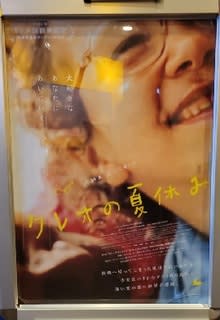(英題:MISSION CROSS )2024年8月よりNetflixから配信された韓国製アクション劇。前半はコメディ・タッチで楽しめるが、中盤を過ぎると、よくある活劇編のレベルに落ち着いてしまう。最後までスタイルに一貫性を持たせた方が良かったと思う。とはいえ、キャストは好調だしテンポも悪くないので、一応ラストまで観ていられる。
ソウル市警に所属する敏腕女刑事カン・ミソンは、仲間内で“ワニ”と呼ばれるほどの強引で手荒な捜査で、周囲から恐れられていた。夫のパク・ガンムは幼稚園の送迎バスの運転手をしながら、主夫として彼女を支える気弱で穏やかな男だ。しかし、実は彼は韓国政府の諜報機関に属していた元特殊要員で、もちろん妻にはそれを隠して結婚したのだった。ある日、ガンムは昔の仲間と再会するが、それを切っ掛けに彼はまたしても国家的陰謀に巻き込まれていく。一方、ミソンは別のヤマ追っていたが、偶然それはガンムが直面している事態と繋がっていた。

男勝りのミソンと恐妻家を装うガンムとの掛け合いが展開する序盤は面白く、ギャグも鮮やかに決まる。さらにガンムが以前の同僚である女性エージェントと会う現場をミソンの同僚たちが目撃し、これは不倫だと早合点するあたりは実に愉快だ。こういうライトな路線で全編進めて欲しかったのだが、主人公夫婦が“共闘”を始める後半に入るとドンパチ主体の単なるアクション劇に移行するのは不満である。
もっとも、活劇の段取りはけっこう良く考えられているとは思うが(特にカーチェイス場面)、それだけではこの映画のストレートな作劇の欠如を補いきれない。あと、敵の首魁の扱いがいたずらにマンガチックで気勢が削がれる。脚本も担当したイ・ミョンフンの演出は、コメディのパートこそ上手くこなしているが、アクションシーンの繰り出し方は意外と平凡だ。結末の付け方も、あまりスマートとは言えない。これでは主人公2人の今後が見通しが掴めないと思う。
とはいえ、主演のファン・ジョンミンとヨム・ジョンアは絶好調。表情の豊かさも身体のキレも、そしてギャグの繰り出し方も満点だ。チョン・ヘジンやチョン・マンシク、キム・ジュホン、キム・ジュンハンら脇の面子も悪くない。
ソウル市警に所属する敏腕女刑事カン・ミソンは、仲間内で“ワニ”と呼ばれるほどの強引で手荒な捜査で、周囲から恐れられていた。夫のパク・ガンムは幼稚園の送迎バスの運転手をしながら、主夫として彼女を支える気弱で穏やかな男だ。しかし、実は彼は韓国政府の諜報機関に属していた元特殊要員で、もちろん妻にはそれを隠して結婚したのだった。ある日、ガンムは昔の仲間と再会するが、それを切っ掛けに彼はまたしても国家的陰謀に巻き込まれていく。一方、ミソンは別のヤマ追っていたが、偶然それはガンムが直面している事態と繋がっていた。

男勝りのミソンと恐妻家を装うガンムとの掛け合いが展開する序盤は面白く、ギャグも鮮やかに決まる。さらにガンムが以前の同僚である女性エージェントと会う現場をミソンの同僚たちが目撃し、これは不倫だと早合点するあたりは実に愉快だ。こういうライトな路線で全編進めて欲しかったのだが、主人公夫婦が“共闘”を始める後半に入るとドンパチ主体の単なるアクション劇に移行するのは不満である。
もっとも、活劇の段取りはけっこう良く考えられているとは思うが(特にカーチェイス場面)、それだけではこの映画のストレートな作劇の欠如を補いきれない。あと、敵の首魁の扱いがいたずらにマンガチックで気勢が削がれる。脚本も担当したイ・ミョンフンの演出は、コメディのパートこそ上手くこなしているが、アクションシーンの繰り出し方は意外と平凡だ。結末の付け方も、あまりスマートとは言えない。これでは主人公2人の今後が見通しが掴めないと思う。
とはいえ、主演のファン・ジョンミンとヨム・ジョンアは絶好調。表情の豊かさも身体のキレも、そしてギャグの繰り出し方も満点だ。チョン・ヘジンやチョン・マンシク、キム・ジュホン、キム・ジュンハンら脇の面子も悪くない。