(原題:La Traviata )82年作品。アレクサンドル・デュマ・フィスの原作によるヴェルディの著名なオペラ「椿姫」の映画化だ。19世紀中頃のパリの社交界を舞台に、真実の恋に生き死んでゆく花形娼婦ヴィオレッタの姿を描く。とにかく、その絢爛豪華な美術に圧倒される。胸を患ったヒロインのヴィオレッタのはかない人生とは対称的に、オペラの中の夜会や仮装舞踏会は華やかで享楽的な空気が横溢しているという設定だ。
もちろん見どころは、この舞踏会のシークエンスである。監督のフランコ・ゼフィレッリとジャンニ・クァランタによる舞台美術、エンニオ・グァルニエリの流麗なカメラワーク、そしてダンスの躍動感は、ゼフィレッリの師匠であるルキノ・ヴィスコンティの「山猫」(63年)の一場面を思い起こさせるほどの、目覚ましいヴォルテージの高さを見せる。ハッキリ言って、この部分だけで入場料のモトは取ってしまうだろう。
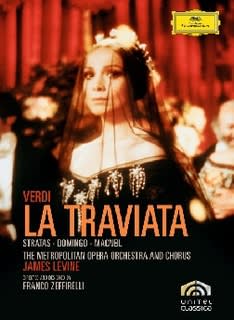
さらに、歌劇とは異なる映画独自の仕掛けが成されていることも見逃せない。本作ではオペラの序曲に当たる部分には、賑々しいクレジットを表示したりはしない。代わりに、昔日の面影のない荒れ果てたヴィオレッタの館から家具や装飾品が運び出される場面が映し出される。ローマのチネチッタのスタジオに組まれた館の広間は、そのあり得ないほどの広さがヒロインの孤独を象徴していると言えよう。
そこに手伝いにやって来た少年がふと壁に目をやると、ヴィオレッタの肖像画が掛かっており、彼はそれに見とれてしまう。すると、誰もいない大広間が、突如として煌びやかな夜会へと変わる。つまり、ラストから先に見せて映画は回想形式で進むという段取りを踏んでおり、それが実に効果的なのだ。
ゼフィレッリの演出はさすが“本職”だけあって、抜かりがない。音楽と映像とのバランスは絶妙で、良く知られた“乾杯の歌”が鳴り響くシーンは大いに盛り上がる。主演者としてテレサ・ストラータスとプラシド・ドミンゴという稀代の歌手を起用しており、他にもコーネル・マクニールやアラン・モンクといったオペラ畑の人材を採用しているが、皆映画俳優としても全く違和感のないパフォーマンスで感心する。ジェームズ・レヴァイン指揮のメトロポリタン歌劇場管弦楽団の演奏も見事なものだ。
もちろん見どころは、この舞踏会のシークエンスである。監督のフランコ・ゼフィレッリとジャンニ・クァランタによる舞台美術、エンニオ・グァルニエリの流麗なカメラワーク、そしてダンスの躍動感は、ゼフィレッリの師匠であるルキノ・ヴィスコンティの「山猫」(63年)の一場面を思い起こさせるほどの、目覚ましいヴォルテージの高さを見せる。ハッキリ言って、この部分だけで入場料のモトは取ってしまうだろう。
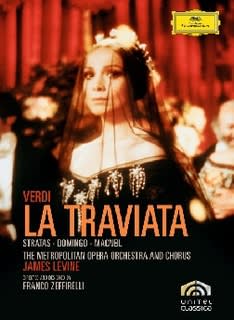
さらに、歌劇とは異なる映画独自の仕掛けが成されていることも見逃せない。本作ではオペラの序曲に当たる部分には、賑々しいクレジットを表示したりはしない。代わりに、昔日の面影のない荒れ果てたヴィオレッタの館から家具や装飾品が運び出される場面が映し出される。ローマのチネチッタのスタジオに組まれた館の広間は、そのあり得ないほどの広さがヒロインの孤独を象徴していると言えよう。
そこに手伝いにやって来た少年がふと壁に目をやると、ヴィオレッタの肖像画が掛かっており、彼はそれに見とれてしまう。すると、誰もいない大広間が、突如として煌びやかな夜会へと変わる。つまり、ラストから先に見せて映画は回想形式で進むという段取りを踏んでおり、それが実に効果的なのだ。
ゼフィレッリの演出はさすが“本職”だけあって、抜かりがない。音楽と映像とのバランスは絶妙で、良く知られた“乾杯の歌”が鳴り響くシーンは大いに盛り上がる。主演者としてテレサ・ストラータスとプラシド・ドミンゴという稀代の歌手を起用しており、他にもコーネル・マクニールやアラン・モンクといったオペラ畑の人材を採用しているが、皆映画俳優としても全く違和感のないパフォーマンスで感心する。ジェームズ・レヴァイン指揮のメトロポリタン歌劇場管弦楽団の演奏も見事なものだ。
















