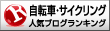オーバーホール後、はじめての実走。
しばらく走らないうちに突然寒くなっており、パールイズミの5度装備で10時に出発。いろいろ不快。
1.冬用ウェアのモコモコと締め付けが鬱陶しい。特にグローブが厚すぎてハンドルのフィーリングが希薄。
2.オーバーホール後で馴染みが出ていないのか、チェーンが擦れているらしくチリチリ鳴る。結局、一日中解消することはなかった上、シフトエラー(ギアが変わらなかったり、忘れた頃に突然変わったり)が頻繁に起こる。来週ショップに持っていくか。
3.ローラー台の上で作ったセッティングで、ハンドルをしゃくり気味にしており、普通のブラケットポジションや登りのシッティングはいいのだが、エアロポジションやダンシングは違和感が大きい。4月のヒルクライムまでは、登り特化ということで諦めるか。
本日のテーマは、新たに導入したバロックギア36T±2 90度のテスト。なので、路面凍結の恐れのない長めの坂ということで大垂水峠へ。
実際に登り坂をバロックギアのシッティングで登ってみると、意外と違和感が少ない(平坦だとすかすかするが)。ペダルを回しやすく、85rpm300w(4倍)ペダリング効率50パーセントが結構簡単に維持できる。普通のギアで登りだと、下死点からグイと脚を持ち上げないといけない感じがあるが、バロックギアだとすっと持ち上げられる。その結果、登りでもケイデンスが維持しやすい。
思うに、通常登りだと慣性が効きにくいため上下死点で一瞬ペダルの回転が遅くなり減速するのを、1時〜4時の間で踏んで加速し、また上下死点でペダル減速という過程を繰り返しているのだが、バロックギアだと上下死点のギアが少ないためペダルの減速が生じず、滑らかに1時〜4時の間で踏むことができる、その結果ケイデンスが上がる、速くなるといったところではないか。敷衍すれば、登りでも、平坦のように慣性が働いているような感覚でペダルを回すことができるのである。この恩恵は、たぶん僕のようなペダリングがへたっぴいな人や体重が重めの人の方が大きいと思う。
まだ使い始めだけれど、バロックギアを使うスキルと必要な筋肉(ノーマルギアとは使う筋肉が変わる)を鍛えれば、登りが速くなりそうな気がする。登りでのダンシングについても特に違和感はなかった。
しかしながら、やはりノーマルのギアとは感覚が少なからず異なるので、慣れの問題かもしれないがなんか気持ち悪い。なので、ノーマルギアでも充分に速い、ヒルクライマーはあえて導入することもないのではないかと思う。僕もヒルクライムが終われば、元に戻すかも。
バロックギアの助力があったとはいえ、さすがに大垂水峠のタイムはダメダメ。もう一本、和田峠を藤野側から登ろうかとしたが、通行止めになっていた、なので大垂水峠を相模湖側からもう一本。
111kmの中くらいのライドで、あんまり自転車に上手く乗れている感じはなかったが、一応TSSは300稼いだ。冬の間の週末の実走トレーニングは、温かい日中にメディオくらいの強度で120kmくらい走れればいいかな。いずれにせよ、あんまり楽しいものではないかも。