2009年3月5日
ほんとにでかいっす、この八村杉。
形がシンプルなだけに、写真見てもピーんとこないかもしれませんが。
遠くから見てもその杉は高かった。

神社の境内に入っていくと、
杉がありました。
「これか、かなりでかい、でも想像の範囲内」
って思っていると、それは八村杉ではありませんでした。
境内の奥にそれはあったんですね。
まじびっくり。
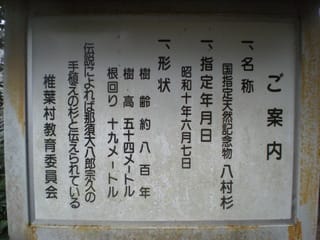
根回り19メートルって、簡単に円周率πで割ると、直径6メートルはあるってことでしょ。
あなたの部屋の大きさは?
そんな円柱が50メートル上空までつったっているんだから。
いやー、見れてよかった。
ほんとにでかいっす、この八村杉。
形がシンプルなだけに、写真見てもピーんとこないかもしれませんが。
遠くから見てもその杉は高かった。

神社の境内に入っていくと、
杉がありました。
「これか、かなりでかい、でも想像の範囲内」
って思っていると、それは八村杉ではありませんでした。
境内の奥にそれはあったんですね。
まじびっくり。
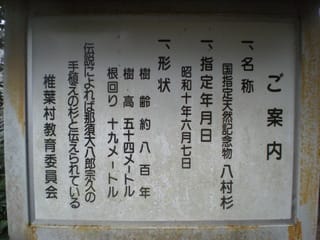
根回り19メートルって、簡単に円周率πで割ると、直径6メートルはあるってことでしょ。
あなたの部屋の大きさは?
そんな円柱が50メートル上空までつったっているんだから。
いやー、見れてよかった。




















