先日(24日)能登のある高校から世界農業遺産「能登の里山里海」をテーマにした講演の依頼があり出かけた。探求の時間という総合教育の一環で、生徒たちはグループごとに地域の文化や自然資源を発掘して観光プランを練っていく。地域の将来を担う高校生はフューチャービルダー、未来請負人でもある。生徒たちから「地域を国際評価の目線で見つめ直すことで新たな気づきや発見があった」と感想が寄せられ、こちらの方がうれしくなった。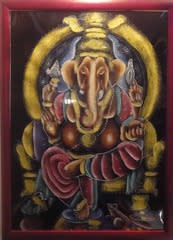 講演後、招いてくださった高校の先生方や地域の若い人と懇談した。特養老人ホームで介護士をしている20歳の女性からは現場での話を聞いた。一番の問題は介護の現場で働く人数が足りないことだという。あと数年もたつと、戦後生まれの、いわゆる団塊の世代が後期高齢者になっていく。内閣府の「高齢社会白書」(平成29年版)によれば、2030年には75歳以上は2288万人と推定される。そこで思う。未来請負人の若い人たちをこれ以上介護の現場に「動員」してはいけない、と。少子高齢化で次世代を担う若者たちはもっと担ってほしい産業分野、たとえば製造、医療、IOT、通信、農林水産業など多々ある。
講演後、招いてくださった高校の先生方や地域の若い人と懇談した。特養老人ホームで介護士をしている20歳の女性からは現場での話を聞いた。一番の問題は介護の現場で働く人数が足りないことだという。あと数年もたつと、戦後生まれの、いわゆる団塊の世代が後期高齢者になっていく。内閣府の「高齢社会白書」(平成29年版)によれば、2030年には75歳以上は2288万人と推定される。そこで思う。未来請負人の若い人たちをこれ以上介護の現場に「動員」してはいけない、と。少子高齢化で次世代を担う若者たちはもっと担ってほしい産業分野、たとえば製造、医療、IOT、通信、農林水産業など多々ある。
酒の勢いもあって、「日本には安楽死法案が必要なのではないか」とつい語ってしまった。いきなりの発言だったので参加者は呆気(あっけ)にとられた顔つきになり、こちらが恐縮した。オランダやスイスは安楽死を合法化している。不治の病に陥った場合に本人の意思で、医師ら第三者が提供した致死薬で自らの死期を早める。似た言葉で尊厳死がある。これも不治の病の延命措置をあえてを断わって自然死を迎える。身内の話だが、92歳で他界した養父は胃がんだった。「90になるまで生きてきた。世間では大往生だろう」と摘出手術を頑なに拒否した。安らかに息を引き取った。今思えば尊厳死だった。
安楽死にしても尊厳死にしても、自らの人生の質(QOL)を確認して最期を迎えたいという願いがある。日本では尊厳死や安楽死に関する法律はまだない。しかしこれは、憲法が保障する基本的人権の一つ、幸福追求権(第13条)ではないだろうか。もちろんさまざまな議論があることは承知している。
話が横にそれてしまった。今後問題化するであろう介護人材の不足をどうカバーするか。考えるに、解決策は2つだろう。1つはアジアなど海外からの人材の受け入れだ。ただ、日本での介護士の免許取得は言葉の問題も含めてハードルが高い。介護の制度設計の見直しが必要だろう。もう1つは、逆にインドネシアやフィリピンなど海外の介護施設との提携だろう。親を海外の施設に送るとなると親戚などから「姨捨山に送った」などと白い目で見られるかもしれないが。
⇒27日(木)夜・金沢の天気 はれ















