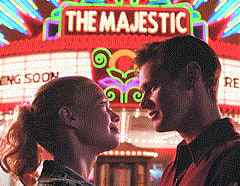2日前、朝日新聞に宮台真司へのインタビュー記事が載ったが、デジタル版と新聞とは見出しが異なる。デジタル版ではタイトルが『宮台真司氏が語る「日本社会の劣等性」』で副題が『象徴はお上にすがる自粛警察』である。紙版ではタイトルが『劣化した日本社会』で副題が『既得権益守る政府 忖度し続ける官僚 お上にすがる市民』である。
ここでは紙版をもとに、宮台の語ったとされることに、とくに、「新自由主義」を中心に論じたい。デジタル版は有料会員向けなので、有料会員でない私は途中までしか読めないので、言及できない。
☆ ☆ ☆ ☆
岸田文雄が「新自由主義からの転換と成長と分配の好循環」を訴えたのは自民党内の「自浄作用」か、という記者の問いかけに対して、宮台はつぎのように応えている。
《違います。そもそも最近の自民党の経済路線を、新自由主義と呼ぶのがデタラメです。》
岸田がいう「新自由主義」とは明らかに小泉純一郎の経済路線を指すのだが、宮台のいう「最近の自民党の経済路線」は安倍晋三の「岩盤規制を破るドリルの刃」を念頭においているのだろうか。「最近の」の時間的範囲がわからない。あいまいである。
が、宮台は、「新自由主義」に評価すべき点があると思っているようだ。
「違います」の証拠として、日本に、米国のIT5社GAFAMのような新しい巨大企業が生まれていないことや、欧州諸国の一部で進むようなエネルギーシフトが起きていないことを、宮台は挙げる。
続く段落で、「産業構造の転換に必要な政策を採れない」のは「日本社会の劣化」のせいだという。
この「劣化」を宮台は「近代の日本社会がもつ『劣等性』です」と言い替える。「劣化」と「劣等性」とは意味が大きく違う。「劣化」は以前より劣ることをさし、「劣等」は他と比べて劣ることをさす。
「近代の」は、いつを指すのかがわからない。インタビューのあとのほうを読むと戦前から続くものであることがわかる。問題は、明治維新からか昭和からかが、わからない。
《都市化と郊外化が進むと、共同体の空洞化が進みます。すると、人々は人間関係に依拠できなくなる。……が、その間 進んだのが感情の劣化と呼ぶべき事態です。不安の原因は『お上』にある、いや『お上に従わない人』にある、と他人を責めるのです。》
ここでの「不安」は人びとの「不安」である。情動で他人を責めるのは「感情の劣化」であると宮台は考えているのだ。
このあとを読むと、既得権益にさわるのが「新自由主義」と考えていることがわかる。そして奇妙な主張に出会う。
《『アベノミクス路線は継承するが、公文書改ざんや官僚とマスコミへの恫喝はしない』というべきです。》
《生活が苦しい若年層や非正規労働者の自公政権支持は根強い。安倍政権下で身軽になった企業が非正規労働者の雇用と所得を少し改善したからです。投票の背後にある感情をくみとれないなら、市民に『同じ世界』を生きていると思ってもらえません。》
《「政治や行政は既存のものを使うから信頼できるでしょう」と言うのが合理的です。安倍政治を批判しておけばいいと考えている野党の稚拙さは、これもまた日本社会の劣化の現われでしょう。》
こうだから、私は社会学者が嫌いだ。私たちをバカにしている。「市民」という言葉も気にいらない。私は市民でない。人である。市民(ブルジョアジー)は特権階級を表わす語だ。
☆ ☆ ☆ ☆
リベラルという言葉には注意がいる。ネオリベラルはもっと問題がある。
宇野重規だと思うが、「リベラル」を「気前のよい」あるいは「こだわらない」というフランス語からきているといっていた。
しかし、政治学者トマス・ホッブズ(1588-1679年)は、彼の『リヴァイアサン』で、“liverty”(自由)と“liverality”(気前がいいこと)を区別している。金持ちは「気前が良く」ないと殺されますよと警告している。
バートランド・ラッセルは、リベラル(自由主義)は個の主張とともに始まると『西洋哲学史』と書いている。ジョン・ロック(1632-1704年)に始まるとする。個人主義は、2000年以上前に始まるが、暴政の前に、政治に参加せず、自分の心の中に中に閉じこもり、心の平和を保つことであった。ところが、17世紀のイギリスに、政治の場で個を主張し、王権に逆らう思想が出てきたと書く。
ロックは、個人の所有を守るのが、政府の責務だとする。当時の財産のもっとも大きいものが土地である。昔は土地は共有であったが、いまは、王のものではなく、個人の所有物になるのが必然の定めであるとする。個人の所有になるのは、個人の労働の成果であるからで、個人の所有になることで、土地が有効に使われると言う。
ロックの「統治論」を読むと、召使いが働いた成果も主人の所有物となる。私はこれにびっくりする。リベラルとは、新しく力をもちだしたブルジョアジー(市民)が王のように個人の自由を謳歌できることなのだ。プロテスタントとかカトリックとかに「こだわらず」に、個を前面に押し出し、自由気ままに振る舞うことが、リベラルなのである。
ホッブズが言うように、貧乏人に殺されないために、「気前のよい」福祉(お金のバラマキ)が必要と考えるリベラルが出てくる。
が、一方で、「個を押し出さないのが悪い。能力がないのが悪い。能力があるもののやることを抑え込むのは悪である。規制を取っ払え」と言う考えが当然出てくる。ミルトン・フリードマン(1912-2006年)やフリードリヒ・ハイエク(1899-1992年)が個人の活動を規制する国家こそ悪だと言い始める。1930年代の大恐慌がきっかけで始めた金融規制、福祉対策を彼らはやり玉にあげ、規制の撤廃、福祉の縮小が始まる。ネオ・リベラリズムである。
個人的なことを言うと、2000年頃、IBMの会社のアジェンダに“use leverage”が出てきて意味がわからず、これがJ. K. ガルブレイス(1908-2006年)の『大恐慌』を読みだしたきっかけである。ガルブレイスは1930年の大恐慌を導いた要因の1つに、“leverage”(てこ)を上げている。これは小さなカネを元に大金を動かすこと言う。これがバブルを導いたという。バブルを起こしたと思われる要因は当然規制の対象になった。州をまたいで金融業務をしない、銀行業務と証券業務を同一会社がしないとか、いろんな規制ができた。
ところが、2000年ごろには規制が大恐慌を起こさないためにあるということを忘れられていた。IBMは、規制緩和がコンピューターやシステムを売り込むチャンスと見たのである。私が戸惑ったアジェンダはこのために書かれてものである。
2000年にアメリカではITバブルが崩壊したが、金融界はバイオとかいろいろな分野にバブルをしかけた。2008年にリーマンショックが起きた。金融企業だけを救って、規制緩和の反省はなされなかった。ネオ・リベラリズムの知性とはそんなものである。
田中拓道は、『リベラルとは何か』(中公新書)で、現代のリベラルを、「価値の多元性を前提として、すべての個人が生き方を自由に選択でき、人生の目標を自由に追求できる機会を保障するために、国家が一定の再分配を行うべきだと考える政治思想と立場」と定義する。
「再分配」という言葉は「私的所有」を前提としている。じっさい、ロック以来、「個人の所有を守る」というリベラルのドグマは変わっていない。それゆえ、財産の共有という「共産主義」をリベラルが宿敵とするのは不変である。私の立場から言えば、本当は「再分配」ではなく、奪われたものを返してもらうのが筋である。
「共有」でとくに重要なのは、土地と生産手段の共有である。ここに注目しないと金持ちはますます金持ちになる。そして、上下ある人間関係、雇用者と被雇用者、上司と部下という関係もつづく。本当は、経営者は単にリーダであって、会社を所有しているのではない。政治家は、「新しい資本主義」でなく、「資本主義」に代わるものがあるということを伝えないといけない。
人は誰でも、個を押し出すことができるわけではない。個を押し出すことのできない人がいることを知らないといけない。個を押し出すことができたのは、自分が運がよかったのだ、と気づいて欲しい。