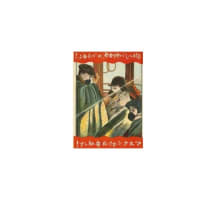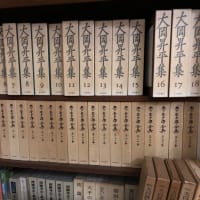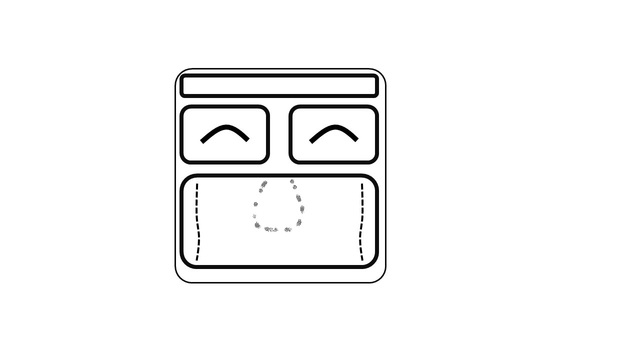日本で年間亡くなる方は約100万人。そのうちがんで亡くなる方は約30万人。そしてそのうちの7割以上の方が感じるとされる痛みは、その方の苦しみを大きく左右する。
厚生労働省もがん対策の中に、がん患者等の生活の質(QOL)の向上のために全国的に緩和医療を提供できる体制を整備することをあげている。
がん性疼痛の9割以上はコントロールが可能であり、コントロールの努力をしないのは医師の怠慢である。病院勤務の私の感覚では比較的多くの医師がその努力をしていると思っていたが、そうでもないらしい。
私の勤務する病院のがん疼痛の専門看護師資格を持つ看護師は、広い地域からの相談を受けているが、在宅ケアを標榜している医師の中に、少なからず痛みのコントロールをきちっとしてくれない医師がいるようだ。
痛みのコントロールに絶大な力を発揮するのは、麻薬。「がんの痛みからの解放―WHO方式がんの疼痛(とうつう)治療法」として世界保健機関(WHO)からもその使用を強く推奨されている。また、痛みのないふつうの人に麻薬を使用する場合に問題となる依存症も、がんなどの痛みがある人に対して投与した場合は、ドーパミンの上昇が抑えられて依存症にはならないことが確認されている。
がん性疼痛に苦しむより、痛みをきちっと取ってもらい、よりよい毎日を送ってもらいたいと心から思う。また、患者の痛みに鈍感な医師は、在宅ホスピスを語る資格は無いと思う。
厚生労働省もがん対策の中に、がん患者等の生活の質(QOL)の向上のために全国的に緩和医療を提供できる体制を整備することをあげている。
がん性疼痛の9割以上はコントロールが可能であり、コントロールの努力をしないのは医師の怠慢である。病院勤務の私の感覚では比較的多くの医師がその努力をしていると思っていたが、そうでもないらしい。
私の勤務する病院のがん疼痛の専門看護師資格を持つ看護師は、広い地域からの相談を受けているが、在宅ケアを標榜している医師の中に、少なからず痛みのコントロールをきちっとしてくれない医師がいるようだ。
痛みのコントロールに絶大な力を発揮するのは、麻薬。「がんの痛みからの解放―WHO方式がんの疼痛(とうつう)治療法」として世界保健機関(WHO)からもその使用を強く推奨されている。また、痛みのないふつうの人に麻薬を使用する場合に問題となる依存症も、がんなどの痛みがある人に対して投与した場合は、ドーパミンの上昇が抑えられて依存症にはならないことが確認されている。
がん性疼痛に苦しむより、痛みをきちっと取ってもらい、よりよい毎日を送ってもらいたいと心から思う。また、患者の痛みに鈍感な医師は、在宅ホスピスを語る資格は無いと思う。