 少なくともクラシック音楽は「楽譜」で現代まで伝わっている。音はほぼ残っていない。
少なくともクラシック音楽は「楽譜」で現代まで伝わっている。音はほぼ残っていない。だから、僕なんて所詮下手くそアマチュア演奏家に過ぎないが、それでもまず、楽譜を見たい。プロの弾いた音は後だ。(と言ったって、自然に聞いている事が多いし、参考になるから聴いた方が良いが。)へんな先入観なしに楽譜を見たい。音楽仲間も、楽譜を配られるとまずプロの音源を探す人が多くてびっくりする。
小説家がすごい悪筆で、編集者なのか解読して活字にしたという話を聞く。だから作曲家の下手くそな自筆だけでなく、出版譜のほうがよかったり、それしかなかったりする。多くの自筆譜のファクシミリとか、初版譜が僕のようなアマチュアでも見ることができて、本当にありがたい時代だと思う。
それから、楽譜に書いてない習慣の問題もある。われわれアマチュアも勉強しなけりゃなあ。困ったことに、そういうわけで、プロも信用できない。良い先生に出会わないととんでもないことになる。
写真は長年愛用している写譜ペン。いったん見つからなくなって、でも出てきた。よかった。










 ラジオの録音はラジオ録音機を買ってあって、
ラジオの録音はラジオ録音機を買ってあって、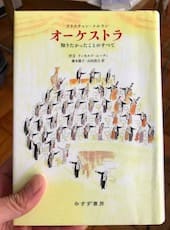 「知りたかったことのすべて」ってのはずいぶん大風呂敷だなあと思うが、6000円もし、500ページを超える。たしかにあらゆることが取り上げられているように思う。
「知りたかったことのすべて」ってのはずいぶん大風呂敷だなあと思うが、6000円もし、500ページを超える。たしかにあらゆることが取り上げられているように思う。


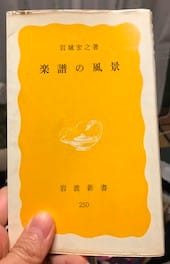 テンポのことは「楽譜の風景」に書いてあることが僕のバイブルだ。「イタリア語の中間搾取」「メトロノームへの不信」。それから、別のところに書いてあるのだけれど、メシアンとのエピソード。まあ、一言で言えば楽譜に書いてある指示をそのままは信用するな、ということに尽きる。ダイナミックスだってそうだし、そう、そもそも楽譜というのは音符一つ一つの始まりはわかるが、どこまで、どうやって伸ばすか、すら厳密には書いてないのだ(アーノンクー ル)。
テンポのことは「楽譜の風景」に書いてあることが僕のバイブルだ。「イタリア語の中間搾取」「メトロノームへの不信」。それから、別のところに書いてあるのだけれど、メシアンとのエピソード。まあ、一言で言えば楽譜に書いてある指示をそのままは信用するな、ということに尽きる。ダイナミックスだってそうだし、そう、そもそも楽譜というのは音符一つ一つの始まりはわかるが、どこまで、どうやって伸ばすか、すら厳密には書いてないのだ(アーノンクー ル)。

 ひさしぶりにガットを取り出して、ひさしぶりに
ひさしぶりにガットを取り出して、ひさしぶりに
 サブウーファーはだいぶまえに買って、なかなか音楽をゆっくり聴くような時間がなかったのだろうか、あまり大きな音を出したりしなかったかもしれない。あらためてあんまりサブウーファーが効いてないなあ、と思って調整しようとしたら、なんと!つながってなかった。まいった。いままで気づかないなんて、なんてぼんくらな耳だ!
サブウーファーはだいぶまえに買って、なかなか音楽をゆっくり聴くような時間がなかったのだろうか、あまり大きな音を出したりしなかったかもしれない。あらためてあんまりサブウーファーが効いてないなあ、と思って調整しようとしたら、なんと!つながってなかった。まいった。いままで気づかないなんて、なんてぼんくらな耳だ!
 皆川達夫さんが亡くなったそうだ。去る19日、4月25日の93歳のご生誕日を目前にしてとのこと。ご冥福をお祈りいたします。
皆川達夫さんが亡くなったそうだ。去る19日、4月25日の93歳のご生誕日を目前にしてとのこと。ご冥福をお祈りいたします。