
高校生の時にホルンを吹いていたが、ものにならなかった。というか、ろくに練習してなかったし、今思うと、肉体というか僕は唇が厚くてホルン向きじゃなかったよね。
当然ダブルタンギングはtktkだった。ちなみにトリプルはtkt、tkt、と、ttk,ttk と使い分けろと言われたが、そんなレベルじゃなかった。
リコーダーではdgdgとか、クヴァンツだったかオトテールだったかtiritiriとかあるいはdid'llとか、なんだかちっともわからない。
現代楽器で使うのはとても速いパッセージを吹くためのもので、バロック時代、特にフランス物の場合はイネガル(不均等奏法)のためのものだろうから、初めから意味が違う。
現代のものは英語基準だと思うのだけれど、バロック時代のタンギングの子音はどんなものなのだろうか?当時のフランス語のlとかrとか、どんな舌の動きなのだろうか?いや、そもそも現代だって人の口の中がどうなっているかわからないじゃないか。他人だけでなく、自分の口の中だって本当のところわからない!
僕のアイドルのひとりと言っても良い有田正広が季刊リコーダーだったか、講座の中でそのクヴァンツだったかのrはどんなものだったのか質問されて「それはとっても専門的な質問ですねえ、気にしなくても良いです」と言うように答えていて、すごーくがっかりしたおぼえがある。とんでもない!最も基本的、根本的な質問じゃないか。
もちろん、そういうわけで、人の口の中は、本当のところわからないのだけれど、当時のフランス語の発音のことでわかっていることを答えて欲しかった。(いや、今でも答えが欲しい)
全然別なところで、フランス語の r は 若干 g に近い、と言う話を聞いた。そういわれて、フランス語のくぐもった発音をまねしてみると、ちょっとわかる気がしない?
あまり追求してもしょうがない。追求すべきは、どうあれ、どんな音が出ているか、聴こえているかだろう。もちろん、どういう意識で吹いてどう聞こえるかだから、どういう子音を意識したときの舌の動きなのか、追求すべきだ、とも言える。
 岩城宏之がCDだったか音楽を聴く事はあまりない、たいてい眠てしまう、と書いている。坂田靖子もチャイコフスキーのピアノ協奏曲が大好きで毎日のように聴いているのだが、眠てしまって最後がどうなってるか知らない、と書いている。我が意を得たり!
岩城宏之がCDだったか音楽を聴く事はあまりない、たいてい眠てしまう、と書いている。坂田靖子もチャイコフスキーのピアノ協奏曲が大好きで毎日のように聴いているのだが、眠てしまって最後がどうなってるか知らない、と書いている。我が意を得たり!









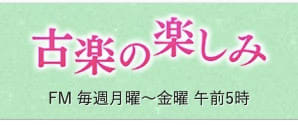
 子供の頃、大人になったら音楽室作って立派なステレオで音楽を楽しむのだと思っていたのだが、人生ままならない。
子供の頃、大人になったら音楽室作って立派なステレオで音楽を楽しむのだと思っていたのだが、人生ままならない。
 「うっせぇわ」は、つまり中島みゆきの
「うっせぇわ」は、つまり中島みゆきの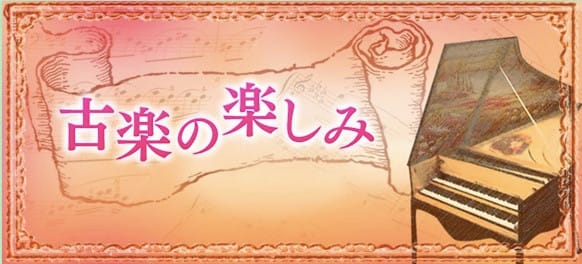
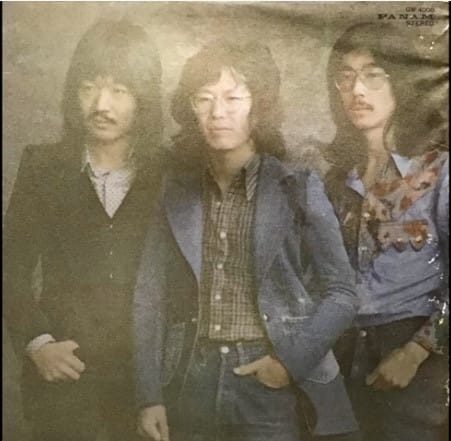
 リコーダーを吹いていると、ヘ音記号の2オクターブ上げと言うか、
リコーダーを吹いていると、ヘ音記号の2オクターブ上げと言うか、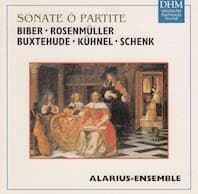

 高校生の時にホルンを吹いていたが、ものにならなかった。というか、ろくに練習してなかったし、今思うと、肉体というか僕は唇が厚くてホルン向きじゃなかったよね。
高校生の時にホルンを吹いていたが、ものにならなかった。というか、ろくに練習してなかったし、今思うと、肉体というか僕は唇が厚くてホルン向きじゃなかったよね。 写真は2本ともアルトだが442と415。半音違うとこれだけ長さが違う。短ければ(音が高く)スズもずいぶん節約できるわけだ。
写真は2本ともアルトだが442と415。半音違うとこれだけ長さが違う。短ければ(音が高く)スズもずいぶん節約できるわけだ。
 10年以上も週に4日くらい、わずか5分だがフラウトトラベルソを吹いていた。それでもなんとか例えばヘンデルなんかはずいぶん楽しめて、バッハは難しくてほんの部分だけれど、ルイエとか初見で楽しめるのだからたいしたものだと思う。(人前で吹くことはあまり考えられない。)
10年以上も週に4日くらい、わずか5分だがフラウトトラベルソを吹いていた。それでもなんとか例えばヘンデルなんかはずいぶん楽しめて、バッハは難しくてほんの部分だけれど、ルイエとか初見で楽しめるのだからたいしたものだと思う。(人前で吹くことはあまり考えられない。)
