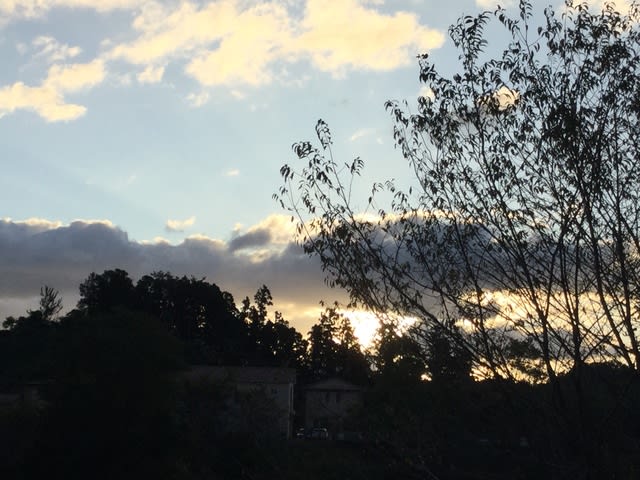上手な介護サービスの活用処方 第30話「認定調査の項目」 〔28〕 
ここでいう「自分の名前を言う」とは、自分の姓もしくは名前のどちらかを答えることである。
1.できる
2.できない
1.質問されたことについて、ほぼ正確な回答ができる場合をいう。
2.質問されたことについて正しく回答できない、あるいは、まったく回答できない場合をいう。
回答の正誤が確認できない場合も含まれる。
旧姓でも、「自分の名前を言う」ことができれば、「できる」になる。
ここの認定調査項目は、ほとんどの方は「できる」であり、余り認知調査項目として必要でないような感じがします。
でも認知症の症状を把握するには、「自分の名前を言う」ことができるかどうか、尋ねることには問題はないが、
調査のなかでは同居されているご家族の名前をどこまで認識されているか、そのことを聞いたりして認知症の進行状態を特記事項に記載しています。
自分の名前を答えることができなくなったときは、認知症の症状は重くなっていると思ってよいでしょう。
※認定調査とは直接関係ありませんが、
同居されていない(大きな)子どもは、
(認知症を患っている)老親に「わたし誰だかわかる」と尋ねる光景を見ることがあります。
自分を生んでくれた親に、名前を憶えているかどうかは、大きな関心事であります。
何故なら離れて暮らしていても、老いても、自分の存在を覚えているかどうか。
でも、認知症を抱えている親にとっては、苦痛なのです。子どであることは、顔を見てわかるが、名前が浮かんでこない。
そう感じられたときは、「太郎だよ」「花子だよ」と自ら助け船を出すことで
親は鸚鵡返しに「太郎だよね」「花子でしょう」と戸惑いから安心の表情に変わります。
試すような言葉かけは、認知症を抱えた人にとって不安や戸惑いを増幅させ、
自分は本当に惚けたのかな、と思い込んでしまうことになるからです。

3-5 自分の名前を言う(能力)
ここでいう「自分の名前を言う」とは、自分の姓もしくは名前のどちらかを答えることである。
1.できる
2.できない
1.質問されたことについて、ほぼ正確な回答ができる場合をいう。
2.質問されたことについて正しく回答できない、あるいは、まったく回答できない場合をいう。
回答の正誤が確認できない場合も含まれる。
旧姓でも、「自分の名前を言う」ことができれば、「できる」になる。
ここの認定調査項目は、ほとんどの方は「できる」であり、余り認知調査項目として必要でないような感じがします。
でも認知症の症状を把握するには、「自分の名前を言う」ことができるかどうか、尋ねることには問題はないが、
調査のなかでは同居されているご家族の名前をどこまで認識されているか、そのことを聞いたりして認知症の進行状態を特記事項に記載しています。
自分の名前を答えることができなくなったときは、認知症の症状は重くなっていると思ってよいでしょう。
※認定調査とは直接関係ありませんが、
同居されていない(大きな)子どもは、
(認知症を患っている)老親に「わたし誰だかわかる」と尋ねる光景を見ることがあります。
自分を生んでくれた親に、名前を憶えているかどうかは、大きな関心事であります。
何故なら離れて暮らしていても、老いても、自分の存在を覚えているかどうか。
でも、認知症を抱えている親にとっては、苦痛なのです。子どであることは、顔を見てわかるが、名前が浮かんでこない。
そう感じられたときは、「太郎だよ」「花子だよ」と自ら助け船を出すことで
親は鸚鵡返しに「太郎だよね」「花子でしょう」と戸惑いから安心の表情に変わります。
試すような言葉かけは、認知症を抱えた人にとって不安や戸惑いを増幅させ、
自分は本当に惚けたのかな、と思い込んでしまうことになるからです。










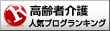


 上手な介護サービスの活用処方 第27話「認定調査の項目」 〔25〕
上手な介護サービスの活用処方 第27話「認定調査の項目」 〔25〕