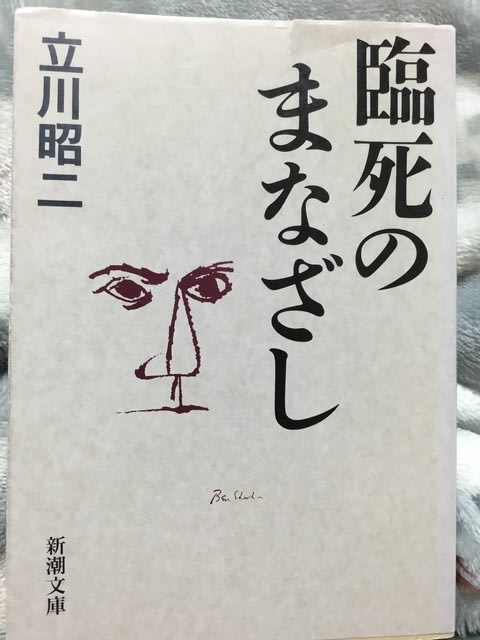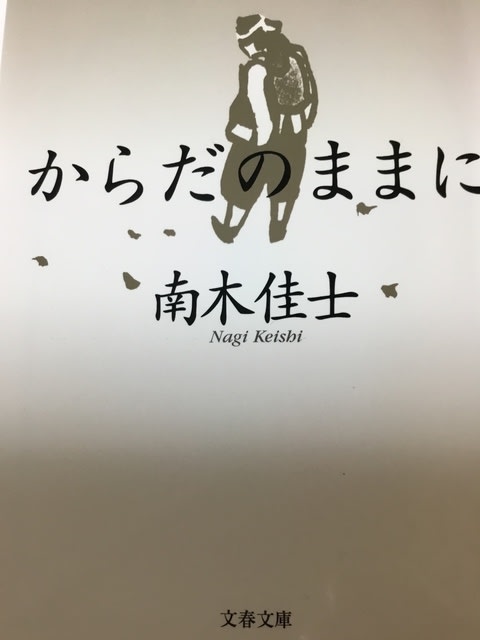死に寄り添う(下)~兄嫁の見送り 勘助~
 『臨死のまなざし』から教えられたこと(5)
『臨死のまなざし』から教えられたこと(5)

1991年2月17日、中勘助の『蜜蜂・余生』に出会い、「蜜蜂」を読み終えた。
今回、立川昭二さんの『臨死のまなざし』を読み、『蜜蜂』を思い出した。
蜜蜂は、働きづめに働いて死ぬ生き物であることを、
稲垣栄洋さんの『生き物の死にざま』で深く知ることができた。
勘助の嫂(あによめ)にあった末子の人生は、
蜜蜂のように命ある限りただひたすら
「家」のために働きづめに働き死んでいった、数え年60歳であった。
昭和17年4月3日 脳溢血で亡くなる。
勘助は『蜜蜂』の23頁~24頁に
「自分には些(いささか)の興味もないこうした面倒を何十年も
つづけながら感謝らしい感謝も、同情らしい同情もうけず、何ら
報いられることなく老い疲れて草の凋(しお)れるように死んで
いったあなたが気の毒でなりません。
詩人的作家である勘助は
雨も悲し
風も悲し
照る日もまた悲しかりけり
・・・・・・
(『蜜蜂』32頁)
9月3日の日記に
あなたのいないことしの秋
きものは人に頼みもしよう
わたしの胸のほころびを
誰が 誰が 縫ってくれる
(『蜜蜂』137頁)
と書き、嫂の死の悲しみを乗り越えるには時間がかかった。
火葬の様子は、『蜜蜂』87頁~88頁に書かれている。
親しい人、大切な人を骨にしたときの思いは、だれも同じである。
四十年苦楽を共にしてきた嫂に対し、
勘助は「記憶」ではなく「体温」として生き残っているのだ」、と
日記に感動的な言葉を綴っていた。
末子は、夫である金一は脳溢血で倒れて以後、33年間夫の介護を続け、
その長年の労苦は心身ともに病みつかれた彼女は、昭和15年、クモ膜
下出血で倒れた。
そのときの勘助の看病日記『氷を割る』を読むと、嫂末子さんの蜜蜂
のような苦労が伝わってくる。
氷を割る
宿命か
げに宿命か
三十年の月日を
半痴半狂の人のみとりに
心身ともに病み疲れて
朽木のごとく倒れし人
その比いなき善良さを思い
いいようもない不幸の一生をおもい
わが更生の恩をおもい
ながしにぽとぽと涙を落としながら
夜ふけの厨に
かちかちと氷をわる
勘助は、家人が寝静まった夜ふけの台所で、錐で氷を割り
嫂の水枕と氷嚢を取り替えるのが日毎夜毎の仕事であった。
兄の看病で疲れた嫂の身の上を思いながら、「かちかち」
と氷を割れば、その氷の上に「ぽとぽと」と勘助の涙が落
ちる情景が浮かび、自分も切なくなってくる。
勘助は、「このつぎに出す本は『蜜蜂』という表題にしようと
思っています。あなたのことですよ、蜜蜂が働き死にに死ぬよ
うにあなたは死んだから。かわいそうな蜜蜂!(『蜜蜂』52頁)
戦前は、いまと違い介護サービスもなく、在宅医療も皆無に近かった。
紙おむつはなく、冬であっても手が凍えちぎれそうになる川の水で
布おむつや下着を洗っていた。末子だけでなく90歳を超えた老人
たちも同じような辛い労苦を乗り越えてきた過去の時代があった。