生理的欲求と介護⑥ 「睡眠」ⅱ 
寝る子は育つ、と言われ
赤ん坊はよく眠る
眠るのが仕事
赤ん坊と変わり
代わりに眠りたい
赤ん坊もよく寝るが老人もよく「眠る」
眠るというよりは寝せている介護の実態がある
80歳、90歳になると
1時間程度の午睡が必要な老人もいる
元気な老人はデイサービスでも寝ずに活動している
あるデイサービス事業所を訪れたら
全員寝かせられ 2時間ほど寝ている
眠りたくなくても寝かせる
その間介護スタッフは何をしているのか
休憩するスタッフと
家族宛の連絡ノートや本日のサービス提供の記載・記録をするスタッフ
しかし2時間も記録にかかるのかといえばそうではない
15人から25人までの定員のデイサービスは
午前中に入浴できるすべての老人お風呂を入れる
お風呂待ちの状態になり
多くは椅子に坐っているだけのデイサービスもある
そして昼食
昼食後は2時間余りの午睡
目が覚めたらおやつの時間 15:00である
おやつを食べ
30分から60分余りの申し訳程度のレクリエーションをこなし
16時から16時半には送迎車に乗り帰宅となる
これは最低のサービス提供である
老人は風呂と昼食を食べれば満足している、と思っているのだろうか
デイサービスでは椅子に坐ってもつまらないので 坐りながら微睡(まどろ)み、いつの間にか寝ている
寝ていると介護員から「寝てはだめよ」と声かけられるも
別に余暇活動のプログラムなし
民放やカラオケの音が流れているだけで
誰も観たり聴いた入りする人はいない
その上午後は2時間の午睡があり
体を動かす時間がないため
夕食後なかなか寝付かれず
22時過ぎても眠れず起きている
認知症老人のなかには
体力が余り夜中に徘徊しだし 困り果てるのは老いた介護者
寝ないということで
かかりつけ医から眠剤が処方され服用
悩みや不安があってどうしても眠れないときは眠剤導入を否定するつもりはない
老人の場合は諸刃の剣であり、眠剤の使い方を誤ると
朝起きても頭が「ぼぉ~」とし、認知症の症状が悪化したり
また、足元がふらつき転倒のリスクもある
眠剤を服用する前にどうしたら眠れるのか
そのことを考えていくことが大切。
上記の流れは、介護施設(特別養護老人ホームなど)においても
そう違いはない。(すべての介護施設がそうだ、書いている訳ではない)
特別養護老人ホームは生活の場であるのだが
「日課表」にそって「介護業務」が流れる
朝眠くても5時過ぎ頃から起こされ、おむつ交換をしたあと車いすに座らせ
ホール(食堂)まで移動しテーブルの前で1時間余り朝食待ちとなる
夜は眠くなくても夕食後には
歯みがき、おむつ交換などを行ったあとベッドに寝せられる
介護の世界において眠る、睡眠をどう位置付けられているのか
朝眠くてなかなか起きれない人は寝かせる
夜はせめて21時位まで起きていたい老人は起きてもいい
眠たいのに起こされる
眠むくないのに寝かせつけられる
生理的欲求に反する睡眠の「ケア」は老人にとり迷惑でしかない
批判するのはたやすい

寝る子は育つ、と言われ
赤ん坊はよく眠る
眠るのが仕事
赤ん坊と変わり
代わりに眠りたい
赤ん坊もよく寝るが老人もよく「眠る」
眠るというよりは寝せている介護の実態がある
80歳、90歳になると
1時間程度の午睡が必要な老人もいる
元気な老人はデイサービスでも寝ずに活動している
あるデイサービス事業所を訪れたら
全員寝かせられ 2時間ほど寝ている
眠りたくなくても寝かせる
その間介護スタッフは何をしているのか
休憩するスタッフと
家族宛の連絡ノートや本日のサービス提供の記載・記録をするスタッフ
しかし2時間も記録にかかるのかといえばそうではない
15人から25人までの定員のデイサービスは
午前中に入浴できるすべての老人お風呂を入れる
お風呂待ちの状態になり
多くは椅子に坐っているだけのデイサービスもある
そして昼食
昼食後は2時間余りの午睡
目が覚めたらおやつの時間 15:00である
おやつを食べ
30分から60分余りの申し訳程度のレクリエーションをこなし
16時から16時半には送迎車に乗り帰宅となる
これは最低のサービス提供である
老人は風呂と昼食を食べれば満足している、と思っているのだろうか
デイサービスでは椅子に坐ってもつまらないので 坐りながら微睡(まどろ)み、いつの間にか寝ている
寝ていると介護員から「寝てはだめよ」と声かけられるも
別に余暇活動のプログラムなし
民放やカラオケの音が流れているだけで
誰も観たり聴いた入りする人はいない
その上午後は2時間の午睡があり
体を動かす時間がないため
夕食後なかなか寝付かれず
22時過ぎても眠れず起きている
認知症老人のなかには
体力が余り夜中に徘徊しだし 困り果てるのは老いた介護者
寝ないということで
かかりつけ医から眠剤が処方され服用
悩みや不安があってどうしても眠れないときは眠剤導入を否定するつもりはない
老人の場合は諸刃の剣であり、眠剤の使い方を誤ると
朝起きても頭が「ぼぉ~」とし、認知症の症状が悪化したり
また、足元がふらつき転倒のリスクもある
眠剤を服用する前にどうしたら眠れるのか
そのことを考えていくことが大切。
上記の流れは、介護施設(特別養護老人ホームなど)においても
そう違いはない。(すべての介護施設がそうだ、書いている訳ではない)
特別養護老人ホームは生活の場であるのだが
「日課表」にそって「介護業務」が流れる
朝眠くても5時過ぎ頃から起こされ、おむつ交換をしたあと車いすに座らせ
ホール(食堂)まで移動しテーブルの前で1時間余り朝食待ちとなる
夜は眠くなくても夕食後には
歯みがき、おむつ交換などを行ったあとベッドに寝せられる
介護の世界において眠る、睡眠をどう位置付けられているのか
朝眠くてなかなか起きれない人は寝かせる
夜はせめて21時位まで起きていたい老人は起きてもいい
眠たいのに起こされる
眠むくないのに寝かせつけられる
生理的欲求に反する睡眠の「ケア」は老人にとり迷惑でしかない
批判するのはたやすい










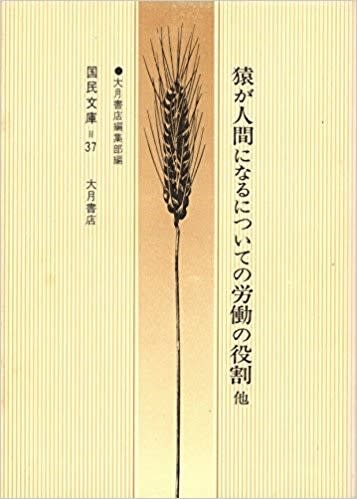
 老いの風景〔4〕 「直立歩行と老人」
老いの風景〔4〕 「直立歩行と老人」





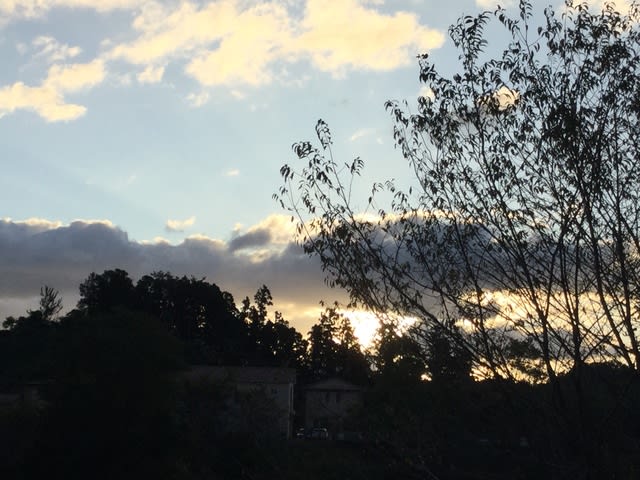

 渇水
渇水


