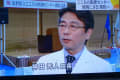------------------
庄内プロジェクト活動報告会2015
日時:平成27年2月28日 16:30~
場所:荘内病院講堂
------------------
プログラムと抄録
今回は、単なる活動報告だけではなく、今後の課題につき意見交換を行いました。
サポートセンターからは、参加者の減少傾向にある「ほっと広場」の今後のありかた、医療者WGからは、医師の研修会への参加の少なさ、啓発WGからは、次年度の市民公開講座をどうするか、連携WGから、それぞれのリーダーが今後の課題について発言し、活発な意見交換が行われました。
【開会あいさつ】
WG、サポートセンター毎に、年間アクションプラン作成し、着実に実行しているとうすばらしい取り組みと評価している。緩和ケアというキーワードで、これだけの多岐にわたる活動を組織的に行っている地域は全国にもないのではないかと思う。これも、皆さんそれぞれの活躍の成果であり、心から敬意を表するものである。
一方で、緩和ケア推進協議会のすべてのWGの活動に言えることだが、「緩和ケア」という枠を超えて、在宅医療、多職種連携、口腔ケア、など地域の医療介護全般に関わる取り組みを行っている。庄内プロジェトは、鶴岡・三川地区の医療・介護プロジェクトともいえる。
一方で、当地区には、地域連携パス推進協議会があり、そこで、疾病単位、例えば、脳卒中、大腿骨近位部骨折、糖尿病、がん、心筋梗塞など、疾病単位での取り組みを行っている。例えば脳卒中、再発率が高いが、どうしたら再発率を下げることができるのかデータを蓄積、解析しながら、その方策を目指した活動を行っている。
また、医師会に設置されている「ほたる」も、在宅医療における医療介護連携を主たる目的として活動しているが、活動内容については重複する部分も多い。
このような背景もあり、来年度は、当地区のさまざまな活動を整理、統合できないか検討することにしている。より、効率的で、各自の負担の少なく、また、実りある成果をあげられる、組織を目指したいと思っている。本日の会が実りあるものであることを期待して挨拶とする。
【活動報告およびディスカッション】
1、緩和ケアサポートセンター鶴岡・三川(富樫さん)

1)相談窓口
2)会議・研修会・イベント等の企画、運営、評価
3)退院カンファレンス
4)緩和ケア情報の集約
ほっと広場
年:6回開催
参加人数(15名~5名):減少傾向、新規が増えない
60-70歳、女性が多い
4月:ハンドベル、6月:フラダンス、8月:ミニコンサート、
10月:朗読会、12月:お抹茶の会、2月;健康チェック
何で知った、ポスター、ちらし
内容:茶話会とイベント
良かったこと、何気ない会話
スタッフの参加が安心感につながっている
課題:参加希望者が増えない
口コミ、グリーフケアなどのときに、家族に周知してはどうか
開催する日時を検討してどうか? 夜間の方が増えたという論文がある
通院している患者さんへのニーズ調査をしてはどうか
2、医療教育WG(鈴木先生)

スキルアップ研修会
知識、困難感、実践のすべての項目において、多く参加すればそれだけ効果があることがOPTIMの報告から分かっている。
問題点
1)医師の参加が少なく、また、減少傾向にある
2)GWでは、極端に参加が少なくなる
課題1
医師の参加を多くするには、どのような工夫が必要か
課題2
どのような内容が良いのか
不得意分野を聞きたいと思うのではないか?
下地づくり(情報発信)が大事
医師は多忙であり、参加数を増やすことは無理ではないか、
むしろ、新規の参加を増やすことを目標にしてはどうか
医師の参加は少なくとも、他の職種が増えれば、それで良いのではないか
医師の参加率をあげるには、医師主体の研修会が効果ある、例えばキャンサーボード鶴岡
緩和ケアを知ってもらうには、キャンサーボードで十分なのではないか?
セミナーの有用性に影響したもの
講義+グループワークが有用
講師は、看護師を入れた方が良い
臨床症状を扱ったものがよい
職種:訪問看護師、診療所医師、緩和家チーム薬剤師
ラーニングピラミッド(左の方ほど知識が深まる)
人に教える>自ら体験>グループ討論>デモンストレーション>視聴覚>読書>講義
3、市民啓発WG(渡辺さん)

・出張講演会
・FBによる情報発信
・緩和ケア市民公開講座
10月5日(日)14:10、参加者255名
4、地域連携WG(瀬尾さん)


・南庄内在宅医療を考える会
課題:医師の参加が増えない
ニーズ調査、開催時間などの検討、他職種
・医療と介護の連携研修会
次年度は、自立支援型ケア会議の設置を予定、
GWで、それぞれの現場を語ることが有効
・医科歯科連携を考える会
本年度は、製薬会社などにお任せするなど自立性に欠けた
次年度は、自主的な企画を考えたい
・つるやくネットワーク
ケアマネとの連携強化を目指したい
・ふらっとの会 年1回
・南庄内食と栄養と考える会 年2回
調理士の技術面でのスキルアップに有用であった
・Net4U
登録する、4万件を突破、
歯科、薬局、事業の参加が増えている
他職種連携と地域連携WG研修会の効果
~介護支援専門員対象のアンケート調査~
負担感:経験が多くなると、負担感も増える傾向がある
医師や看護師に比し、栄養士、歯科医、薬剤師に対する連携意識が低い
連携に対する想いは、人によって異なる
医師は敷居が高いと感じている
研修会に参加しなくても、他職種ができることは分かると思っているケアマネが多い
連携WGへの希望、地域連携の周知>研修会>意見交換の場
研修会などで得た知識を如何に日常業務に生かせるのかが重要、
【展示】






【懇親会】