
常々、江戸城無血開城までの徳川慶喜の不甲斐なさに失望していた。評価には、「臆病者の逆賊」と真逆な「家康以来の英邁」の見方がある。
福沢諭吉が自書「痩我慢の説」に、無血開城を威勢よく批評している。
徳川家の末路に、日本の経済に於いて一時の利益を成したりと雖も、数百千年養い得たる我日本武士の気風を傷うたるの不利は決して少々ならず。
例え多勢にして強敵であろうと、国を立てるために痩せ我慢を張り倒し、断固として抵抗し戦うところに、古来からの日本人の気風があると断ずる。
後に海舟がいったことが山岡鉄舟「武士道」に示されてある。
「一兵も動かさずして、江戸城を官軍に引き渡したことは、やはり武士道から割り出したのだ。」
必敗を期して江戸城を明け渡した。日本国のために徳川八万騎の反乱を抑え切った。朝敵・徳川慶喜の汚名を雪がねばならぬと心に決めた。
この基本スタンスは海舟の自伝「氷川清話」に次のように書いている。
「一時凌ぎに外国から金を借りるということは、例え死んでもやるまいと決心した。借金のために抵当を取られてはならぬと耐えた。手の届く限り借金政略を拒み通した。」
西洋列強の代理戦争としての内戦を避け通した。アヘン戦争で中国が香港を割譲させられた二の舞を恐れた。
坂口安吾の傑作「安吾史讀」の中の「勝夢酔」に次のように福沢諭吉の「痩我慢の説」に反論している。
明治維新に勝った官軍は、幕府を倒すために歩調を合わせる程のことに政治力の限界があった。
ところが、負けた方の総大将の勝海舟は、幕府のなくなる方が日本全体の改良に役立つことに成算あって確信をもって負けた。否、戦争せずに負けることに努力した。
幕府制度の欠点を知悉し、それに代わるにより良き策に理論的にも実際的にも成算があって事をなした人は、勝った官軍の人々ではなく、負けた海舟ただ一人である。理を究めた確実さは彼だけにしかなかった。官軍の誰よりも段違いに幕府なき後の日本の生長に具体的な成算があった。
あの伸るか反るかのときに、江戸を焦土にしてもいい、サムライの意気地を立てて玉砕せよ、との徹底抗戦主義に諸手を挙げて賛同する民衆がどれほどいたことか。太平洋戦争の終末期の8月15日のわれわれ日本人のことを思い合わせてみれば、あまりにも答えは明瞭である。
世界のなかで、無血開城を日本だけが、ただ一度成し得たといえる。
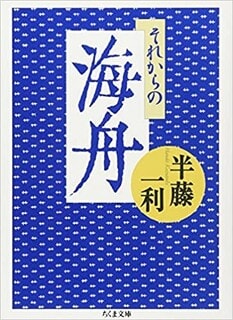 慶喜が大阪城から江戸城に逃げ帰って来たとき、フランス公使ロッシュが謁見を乞い、しきりに再挙をすすめたときの慶喜の返答は立派だった。
慶喜が大阪城から江戸城に逃げ帰って来たとき、フランス公使ロッシュが謁見を乞い、しきりに再挙をすすめたときの慶喜の返答は立派だった。
わが国の国風というのは、朝廷の命令と称して兵を派遣するときは、百令ことごとくそれに従う。勅令には何人も背くことはできない。いま兵を交えて、例えわれらが勝利を得たとしても、それは末代までも朝敵の悪名から免れがたいことになる。徳川家に対する情義からわれに加担する者があるであろうが、そうなっては国内各地に戦闘が起こって、三百年前の如き兵乱の世となり、万民がその害を受け苦しむことになる。これは余のもっとも忍び得ざるところなり。
という見地に立てば、慶喜は偉大な政治家といえよう。

海舟好きを公言する江戸っ子・半藤一利 曰く
「薩長軍は不平不満の貧乏公卿を巧みに利用して年若い天皇を抱き込み、尊皇を看板に、三百年来の私怨と政権奪取の野心によって討幕を果たした無頼の徒にすぎない」
> つづく >>

福沢諭吉が自書「痩我慢の説」に、無血開城を威勢よく批評している。
徳川家の末路に、日本の経済に於いて一時の利益を成したりと雖も、数百千年養い得たる我日本武士の気風を傷うたるの不利は決して少々ならず。
例え多勢にして強敵であろうと、国を立てるために痩せ我慢を張り倒し、断固として抵抗し戦うところに、古来からの日本人の気風があると断ずる。
後に海舟がいったことが山岡鉄舟「武士道」に示されてある。
「一兵も動かさずして、江戸城を官軍に引き渡したことは、やはり武士道から割り出したのだ。」
必敗を期して江戸城を明け渡した。日本国のために徳川八万騎の反乱を抑え切った。朝敵・徳川慶喜の汚名を雪がねばならぬと心に決めた。
この基本スタンスは海舟の自伝「氷川清話」に次のように書いている。
「一時凌ぎに外国から金を借りるということは、例え死んでもやるまいと決心した。借金のために抵当を取られてはならぬと耐えた。手の届く限り借金政略を拒み通した。」
西洋列強の代理戦争としての内戦を避け通した。アヘン戦争で中国が香港を割譲させられた二の舞を恐れた。
坂口安吾の傑作「安吾史讀」の中の「勝夢酔」に次のように福沢諭吉の「痩我慢の説」に反論している。
明治維新に勝った官軍は、幕府を倒すために歩調を合わせる程のことに政治力の限界があった。
ところが、負けた方の総大将の勝海舟は、幕府のなくなる方が日本全体の改良に役立つことに成算あって確信をもって負けた。否、戦争せずに負けることに努力した。
幕府制度の欠点を知悉し、それに代わるにより良き策に理論的にも実際的にも成算があって事をなした人は、勝った官軍の人々ではなく、負けた海舟ただ一人である。理を究めた確実さは彼だけにしかなかった。官軍の誰よりも段違いに幕府なき後の日本の生長に具体的な成算があった。
あの伸るか反るかのときに、江戸を焦土にしてもいい、サムライの意気地を立てて玉砕せよ、との徹底抗戦主義に諸手を挙げて賛同する民衆がどれほどいたことか。太平洋戦争の終末期の8月15日のわれわれ日本人のことを思い合わせてみれば、あまりにも答えは明瞭である。
世界のなかで、無血開城を日本だけが、ただ一度成し得たといえる。
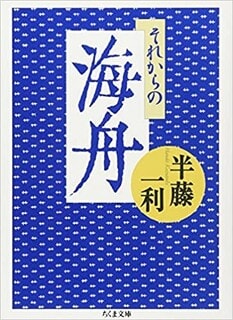 慶喜が大阪城から江戸城に逃げ帰って来たとき、フランス公使ロッシュが謁見を乞い、しきりに再挙をすすめたときの慶喜の返答は立派だった。
慶喜が大阪城から江戸城に逃げ帰って来たとき、フランス公使ロッシュが謁見を乞い、しきりに再挙をすすめたときの慶喜の返答は立派だった。わが国の国風というのは、朝廷の命令と称して兵を派遣するときは、百令ことごとくそれに従う。勅令には何人も背くことはできない。いま兵を交えて、例えわれらが勝利を得たとしても、それは末代までも朝敵の悪名から免れがたいことになる。徳川家に対する情義からわれに加担する者があるであろうが、そうなっては国内各地に戦闘が起こって、三百年前の如き兵乱の世となり、万民がその害を受け苦しむことになる。これは余のもっとも忍び得ざるところなり。
という見地に立てば、慶喜は偉大な政治家といえよう。

海舟好きを公言する江戸っ子・半藤一利 曰く
「薩長軍は不平不満の貧乏公卿を巧みに利用して年若い天皇を抱き込み、尊皇を看板に、三百年来の私怨と政権奪取の野心によって討幕を果たした無頼の徒にすぎない」
> つづく >>

















「それからの海舟」では田町の薩摩藩邸(タイトル写真)での海舟と隆盛の会談から先をドキュメントに描いた。
最後に引用された半藤氏の言葉、「尊王を看板に……」の言葉に大義名分に隠された「三百年来の私怨と政権奪取の野心」がうかがえますね。
欺瞞に満ちた錦旗の御旗もこんな話があります。
考証家田村鳶魚が「夢に見た恭順中の慶喜公」という分でこう言っている。
『錦の御旗は朝廷から薩長軍に与えられたものではない。倒幕の密勅前後に長州藩士品川弥次郎が長州で勝手に私造したものである。品川は国学者で岩倉の腹心だった玉松操の描いた図に基づいて錦旗を4本、菊の御紋のついた紅白の旗を20本こしらえ、半分を山口の城に、半分を京都に持って来て薩摩屋敷に置いてあった。すなわち長州の一武士が私製した急ごしらえの旗が、鳥羽伏見の戦いで錦旗となり、薩長軍が東征の名義を得たのだ、と鳶魚はいう。』
森まゆみ著「彰義隊」の中で紹介されています。錦旗の御旗なんて、誰も見たことがなく、作成するにはそれなりの苦労があったようです。
「慶喜」の再評価も必要な時期が来ているのではないかと思います。
という分でこう言っている。
という文でこう言っている。
と訂正します。
そうすると、いまのような人気作家になっていないということもあり得た
・・・いえいえ、やはり人間の弱さを描く太宰人気に陰りは生じないでしょうね❔
錦の御旗は、にわか作りに仕上げたそうですね。
これを見た幕府側は、戦意を失ったといいますから、この幻の旗が歴史を動かしたといえるでしょう。
将軍の慶喜その人が水戸藩ですから、朝敵の悪名をかぶるのを徹底的に嫌ったことが、江戸城無血開城に奔らせたのですね。
結果的に、多少の血は見たものの日本は西洋列強の植民地化を免れたのですから、徳川慶喜が幼いころから「家康以来の英邁」といわれていたことは当たっていたといえるでしょう。
結果として徳川幕府250年の歴史に幕を下ろしましたが、この英断によって現在の自由で平和な日本が誕生しました。
太平洋戦争のような無謀な出来事もありましたが・・・。
幕府落ち目の時代ですが、どうして政権放棄したのでしょうか?
http://www.photo-make.jp/hm_2/senzoku_katu.html
「あの店は敷居が高い」をよく使った気がします。
問題として出題されると、
二者択一なら (ア) 「相手に不義理などをしてしまい、行きにくい」を選べば正解でありそうです
大河ドラマ「青天を衝け」で草彅剛が慶喜を演じて評判がいいようですね。^^
慶喜は、海舟を新政府とたくらんだと思い、何より相性がよくなかったようです。そのくせ、全権を海舟に委ねます。
海舟も、そんな複雑な慶喜に辟易しています。
海舟の息子が男子を設けぬまま死んだため、跡取りに慶喜の十男・勝精を養子に迎えます。
海舟が慶喜に願い出たときに、はじめて泣いて海舟の至誠を理解したといいます。
大政奉還して天皇の下に幕府主導の新組織を置いて大名の主席としてのリーダーに就く構想だったようです。
『鳥羽伏見の戦い』にありもしなかった錦の旗を持ち出され、敗走してしまい、歯車が狂います。
ここに逆賊の烙印を押されてしまって、慶喜切腹まで迫られてしまいます。
海舟が手を尽くして、なんとか一死を免じられました。
しかし、新政府には人材がなく、幕府の人間を登用して運営したようです。もちろん「二君に仕えず」として浪人した者もいました。