毎日いろんなことで頭を悩ましながらも、明日のために頑張ろうと自分を励ましています。
疲れるけど、頑張ろう!
道具
私の父は大工である。というか大工であった。いや、73歳の今でもやっぱり自分は大工であると思っているだろうから、「大工である」としておこう。その父が自分の大工小屋(大きな建物であったが、そう父と母は呼んでいた)を半分壊して私の塾舎を建ててくれた。したがって、塾舎の奥の建物には今でも父が使っていた大工道具がおいてあるし、ちょっとした作業ならできるようになっている。
父はその一角に自分だけがくつろげる一室を作って、寒い冬にはそこで薪を燃やして暖をとりながら、日がな一日株式市場のラジオを聴きながら、のんびり暮らしている。今でこそ、農民だか隠居だかよく分からない呑気な暮らしをしているが、若い頃は朝早くから夜遅くまで本当によく働いた。私もよく仕事の手伝いについていったことがあるが、仕事を始めたら10時とか3時とか決められた休憩時間以外は、一心不乱に仕事をしていた。よくあんなに根気と体力が続くものだといつも感心していた。私のように面倒くさいことが大嫌いな男には到底真似できないような仕事ぶりであった。そんな父も17年前に母が亡くなってからは全く仕事にやる気をなくしてしまい、たまに気の向いたときに頼まれた仕事をするくらいになってしまったが、それまで人の2倍も3倍も働いてきたのを家族誰もが知っていたので、何も言わずに父のやりたいようにさせてきた。
それでも、ちょっとした仕事くらいなら今でも引き受ける。先日も床を直して欲しいという近所の人の頼みを聞いて3、4日かけて直してきた。その間はいつになく充実した顔をしていて、久しぶりに父の職人顔を見たような気がして私は密かにうれしかった。表立ってうれしそうな顔をすると、他の仕事も引き受けてしまい、体がふらふらになるまで頑張ってしまうから、決してそんな顔はできない。「しんどくない?」と私が聞いても、「これぐらいなんともない」などと元気そうなことを言っていたが、そう言えるだけ幸せなのかもしれない。
そのときに、いつかこのブログで父が長年使ってきた道具の写真を載せて記念に残しておきたいと思いついた。すぐに取り掛かればよかったものを生来の怠け者ゆえ、今日まで延ばし伸ばしになってしまった。昨日やっと写真を撮ったのでいくつか載せてみる。



金槌(かなづち) 鋸(のこぎり) 鑿(のみ)



鉋(かんな) 差金(さしがね) 墨壷(すみつぼ)



釘箱(くぎばこ) 梯子(はしご) 工具(こうぐ)
ここまで載せてきて、こんな手入れのしていない道具の写真を載せたと父が知ったならさぞや怒るだろうと思った。道具を大事にしていた父が、鉋の刃や鑿を砥石で研ぐ音が私は好きだった。父が丹念に何度も何度も研いでいるのを一心に見つめていた。鉋で木を削る音も好きだった。しゃー、しゃーと削られてくる鉋くずが何mも長くなるのを見て、すごいなと感心したものだった。そんな父にとっては錆びた道具の写真など己の恥とするものであろうが、これも現状を正直に物語る記念である。
父はこれらの道具を使っていったい何軒の家を建ててきたのだろう。一度尋ねたことがあるが自分でも正確な数字は分からないようだった。それほどまでに多くの家を建ててきた父と苦楽をともにしてきた道具たち。よく考えれば、この道具たちは家だけではなく、私や妹・弟を育ててきた糧を生み出してくれたものたちだ。
感謝せずにはいられない。
父はその一角に自分だけがくつろげる一室を作って、寒い冬にはそこで薪を燃やして暖をとりながら、日がな一日株式市場のラジオを聴きながら、のんびり暮らしている。今でこそ、農民だか隠居だかよく分からない呑気な暮らしをしているが、若い頃は朝早くから夜遅くまで本当によく働いた。私もよく仕事の手伝いについていったことがあるが、仕事を始めたら10時とか3時とか決められた休憩時間以外は、一心不乱に仕事をしていた。よくあんなに根気と体力が続くものだといつも感心していた。私のように面倒くさいことが大嫌いな男には到底真似できないような仕事ぶりであった。そんな父も17年前に母が亡くなってからは全く仕事にやる気をなくしてしまい、たまに気の向いたときに頼まれた仕事をするくらいになってしまったが、それまで人の2倍も3倍も働いてきたのを家族誰もが知っていたので、何も言わずに父のやりたいようにさせてきた。
それでも、ちょっとした仕事くらいなら今でも引き受ける。先日も床を直して欲しいという近所の人の頼みを聞いて3、4日かけて直してきた。その間はいつになく充実した顔をしていて、久しぶりに父の職人顔を見たような気がして私は密かにうれしかった。表立ってうれしそうな顔をすると、他の仕事も引き受けてしまい、体がふらふらになるまで頑張ってしまうから、決してそんな顔はできない。「しんどくない?」と私が聞いても、「これぐらいなんともない」などと元気そうなことを言っていたが、そう言えるだけ幸せなのかもしれない。
そのときに、いつかこのブログで父が長年使ってきた道具の写真を載せて記念に残しておきたいと思いついた。すぐに取り掛かればよかったものを生来の怠け者ゆえ、今日まで延ばし伸ばしになってしまった。昨日やっと写真を撮ったのでいくつか載せてみる。



金槌(かなづち) 鋸(のこぎり) 鑿(のみ)



鉋(かんな) 差金(さしがね) 墨壷(すみつぼ)



釘箱(くぎばこ) 梯子(はしご) 工具(こうぐ)
ここまで載せてきて、こんな手入れのしていない道具の写真を載せたと父が知ったならさぞや怒るだろうと思った。道具を大事にしていた父が、鉋の刃や鑿を砥石で研ぐ音が私は好きだった。父が丹念に何度も何度も研いでいるのを一心に見つめていた。鉋で木を削る音も好きだった。しゃー、しゃーと削られてくる鉋くずが何mも長くなるのを見て、すごいなと感心したものだった。そんな父にとっては錆びた道具の写真など己の恥とするものであろうが、これも現状を正直に物語る記念である。
父はこれらの道具を使っていったい何軒の家を建ててきたのだろう。一度尋ねたことがあるが自分でも正確な数字は分からないようだった。それほどまでに多くの家を建ててきた父と苦楽をともにしてきた道具たち。よく考えれば、この道具たちは家だけではなく、私や妹・弟を育ててきた糧を生み出してくれたものたちだ。
感謝せずにはいられない。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
女子団体
日曜日、夕食を食べ終えた私は、さつま芋掘りの疲れと飲み始めたビールの酔いのせいでかなり朦朧となりながらも、一人TVを見ていた。いつものようにチャンネルを握り締め、面白い番組はないかとあちらこちらの番組をさまよっていたら、テレビ朝日系で「シンクロワールドカップ2006」がやっているのを見つけた。この番組はSMAPの稲垣吾郎がキャスターをやっていって、スペイン旅行中の吾郎ちゃんの大ファンであるわが娘が録画予約をしていったという番組である。運良く最後のチームの日本の演技がちょうど始まるところだった。テクニカルルーティン(TR)では、ライバルスペインと同点であった日本はフリールーティン(FR)にすべてを託して演技に入った。会場の声援も大きなものがあり、アナウンサーたちの緊張した声を聞いているうちに私の頭もはっきりしてきて、じっと見守り始めた。すると、後方の選手がプールに飛び込む間際に足を滑らせてしまい、右腿を痛打したように見えた。「演技に入る前だから採点には響きません、大丈夫」と解説者は視聴者を安心させようとするが、一番動揺しているのはその解説者のようにも聞こえた。しかし、そんなアクシデントをものともせず、すばらしいチームワークで一人一人の動作が寸分の狂いもないほど一致していて、文字通り「シンクロナイズド」されていた。全く素人の私でも、すばらしい演技であることは分かった。最初に滑った選手も何事もなかったように最後まで演技を続けた。その精神力の強さには驚いたが、得点が発表され、スペインを0.15差で上回り見事銀メダル獲得が決まった瞬間には素顔の女の子に戻って、歓喜の涙で顔をくしゃくしゃにしていたのにも感動した。「マーメードJAPAN」などと聞こえのいい名前を与えて、視聴率を稼ごうというTV局のあざとさが見え隠れはしたが、素直におめでとうと言いたい気持ちになった。
少ししてチャンネルを変えると、フジテレビ系で「柔道ワールドカップ2006国別団体戦・女子」が放送されていた。こちらは俳優の坂口憲二がキャスターをやっていたが、この日の日本女子は準決勝でフランスに敗れてしまい、3位決定戦で韓国と対戦していた。アテネオリンピックで華々しい活躍をした女子柔道チームが連覇に向けて挑む大会などと、宣伝していたようだが、決勝まで進めなかったのはTV局にとっては誤算だっただろう。上野・塚田・谷本という金メダリストが参加していたし、48キロ級には東京・渋谷教育学園渋谷高の中村美里が出場するということで、私も期待はしていたが、あいにくの結果となってしまった。
しかし、柔道という競技は因果なものだ。日本のお家芸として金メダル獲得を宿命付けられている柔道では、3位で銅メダルを獲得してもほとんど評価されない。仕方がないといえばそれまでだが、1位のロシアに勝つことなど最初から度外視して、2位に入ったことで大喜びしてもらえるシンクロチームとは大違いだ。一生懸命戦ったはずの柔道の選手一人一人は本当によくやったと思う。胸を張れとはさすがに言えないけれど、うつむくことなくまっすぐ前を見据えて帰国してほしいものだ。


こうやって写真を並べるまでもなく2つの競技の華やかさの違いは歴然としている。見せる競技と戦う競技との性格の違い、競技者の体型の違い、コスチュームの違い(派手な水着と、白と青しかない柔道着)など、いくつも指摘できるだろう。しかし、今回そんな正反対に見える競技をほぼ同時に見ていて感じたことは、どちらの種目の選手も、持てる力を最大限に発揮しようと、本当に真剣で必死だったということだ。彼女たちの、自分たちが毎日培ってきたものを信じて、一つの目標に向かって全員で力をあわせて挑んでいく、その美しくも尊い姿をTV越しに見ていたら、私の中途半端な眠気なんて全くどこかへ飛んで行ってしまったことは言うまでもない。
やっぱりスポーツ番組は最高だ。
少ししてチャンネルを変えると、フジテレビ系で「柔道ワールドカップ2006国別団体戦・女子」が放送されていた。こちらは俳優の坂口憲二がキャスターをやっていたが、この日の日本女子は準決勝でフランスに敗れてしまい、3位決定戦で韓国と対戦していた。アテネオリンピックで華々しい活躍をした女子柔道チームが連覇に向けて挑む大会などと、宣伝していたようだが、決勝まで進めなかったのはTV局にとっては誤算だっただろう。上野・塚田・谷本という金メダリストが参加していたし、48キロ級には東京・渋谷教育学園渋谷高の中村美里が出場するということで、私も期待はしていたが、あいにくの結果となってしまった。
しかし、柔道という競技は因果なものだ。日本のお家芸として金メダル獲得を宿命付けられている柔道では、3位で銅メダルを獲得してもほとんど評価されない。仕方がないといえばそれまでだが、1位のロシアに勝つことなど最初から度外視して、2位に入ったことで大喜びしてもらえるシンクロチームとは大違いだ。一生懸命戦ったはずの柔道の選手一人一人は本当によくやったと思う。胸を張れとはさすがに言えないけれど、うつむくことなくまっすぐ前を見据えて帰国してほしいものだ。


こうやって写真を並べるまでもなく2つの競技の華やかさの違いは歴然としている。見せる競技と戦う競技との性格の違い、競技者の体型の違い、コスチュームの違い(派手な水着と、白と青しかない柔道着)など、いくつも指摘できるだろう。しかし、今回そんな正反対に見える競技をほぼ同時に見ていて感じたことは、どちらの種目の選手も、持てる力を最大限に発揮しようと、本当に真剣で必死だったということだ。彼女たちの、自分たちが毎日培ってきたものを信じて、一つの目標に向かって全員で力をあわせて挑んでいく、その美しくも尊い姿をTV越しに見ていたら、私の中途半端な眠気なんて全くどこかへ飛んで行ってしまったことは言うまでもない。
やっぱりスポーツ番組は最高だ。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )
さつま芋掘り(2)
2006年09月18日 / 塾
去年の11月7日のこのブログの記事にさつま芋を掘りにいった記事がある。その記事は、『本当に来年も同じようにイモを掘りたいなあ。』と終わっているが、念願かなって、昨日無事にさつま芋堀りに行ってきた。昔の記事を読むことは余りない私だが、去年よりも2ヶ月近く早く掘りに行ったというのには驚いた。生育が早かったというのもあるが、遅くなるといのししに食べられてしまう恐れがあるという父の心配を受けて、この時期に行くことになった。
どうしてこう毎年天気の心配をしなければならないのだろう。台風が近づいていて雨になるかもしれないと数日前から心配していた。朝の新聞を見ても午後から雨と、1時に集合予定をあざ笑うようなことしか書いてない。それでも10時過ぎまでは嘘のように晴れていた。日頃の行いがいいから、などと偉そうなことを思ってもいたのだが、12時近くなると、黒い雲で空が覆われてしまった。いつ降り出してもおかしくない、そんな空模様になったのだが、少雨決行と子供たちには伝えてある。少々の雨なら無理やり行くぞと、気持ちを固めていたのだが、集合時間になっても雨は降ってこない。ラッキーと思いながら、集まった子供たちとバスに乗り込み、畑に向かった。



畑は小高い丘の上にある。上っていくのは結構大変だ。こうした坂を上っていくと日頃の運動不足が如実に現れる。途中で息が切れ始め、ぜいぜい言いながら上っていく。そんな私を尻目に元気な子供たちは走って行ってしまう。写真に収めようにも姿が見えなくなってしまった。年はとりたくないものだ。と、思った瞬間に、こんなところまで、夏の暑い盛りに水遣りや虫取りに何度も往復したであろう父の苦労が心に浮かんできて、何の手伝いもしてこないで収穫だけをしに来るアホな息子の己を恥じた。



畑にたどり着くと、もうさつま芋の葉は刈り取ってあって、掘るばかりになっていた。いつもながら父の配慮には頭が下がる。一人一畝ずつ掘っていけよという私の言葉を合図に全員が掘り始める。半分以上が去年も来たことのある子供たちなので、スムーズに進んでいく。私が備中ぐわで掘り起こす必要もないくらい順調に芋を掘っていく。時期が早い割には大きな芋がいくつもあって、子供たちの歓声が響く。中には自分の顔と同じくらいのものを掘り出す子もいて、しばし大笑いをする。天気は何とかもってくれて、ひと時の楽しみに水を差さないでいてくれた。



掘った分だけは各自が持ってきたビニール袋に詰めて、もって帰れといってあるので、競争のようにして掘る子達もいてなかなか愉快だ。それでも、子供たちが掘り終わった畝を私が備中で掘り返していくと、掘り残した芋が出てくることもある。
出てきた芋を適当に振り分けると皆うれしそうな顔をする。それぞれが掘り終わって、それでも足りない子達にはさらにもう一畝掘らせた。こうやって各人の袋はパンパンに膨れあがった、大収穫だ。


全員で、父にお礼を言って帰ることになったが、こんな大きな袋を持って坂道を下りていくのは大変だ。だが、「気をつけろよ」と叫ぶ私の心配などまるで気にせず、なんとか全員無事にバスのところにたどり着いた。労をねぎらって、帰り道で近くにあった自動販売機で一人ずつに飲み物を買ってやった。
私にとっては毎年恒例の行事であるが、今年もやっぱり去年と同じ楽しい気持ちになった。
『本当に来年も同じようにイモを掘りたいなあ。』
どうしてこう毎年天気の心配をしなければならないのだろう。台風が近づいていて雨になるかもしれないと数日前から心配していた。朝の新聞を見ても午後から雨と、1時に集合予定をあざ笑うようなことしか書いてない。それでも10時過ぎまでは嘘のように晴れていた。日頃の行いがいいから、などと偉そうなことを思ってもいたのだが、12時近くなると、黒い雲で空が覆われてしまった。いつ降り出してもおかしくない、そんな空模様になったのだが、少雨決行と子供たちには伝えてある。少々の雨なら無理やり行くぞと、気持ちを固めていたのだが、集合時間になっても雨は降ってこない。ラッキーと思いながら、集まった子供たちとバスに乗り込み、畑に向かった。



畑は小高い丘の上にある。上っていくのは結構大変だ。こうした坂を上っていくと日頃の運動不足が如実に現れる。途中で息が切れ始め、ぜいぜい言いながら上っていく。そんな私を尻目に元気な子供たちは走って行ってしまう。写真に収めようにも姿が見えなくなってしまった。年はとりたくないものだ。と、思った瞬間に、こんなところまで、夏の暑い盛りに水遣りや虫取りに何度も往復したであろう父の苦労が心に浮かんできて、何の手伝いもしてこないで収穫だけをしに来るアホな息子の己を恥じた。



畑にたどり着くと、もうさつま芋の葉は刈り取ってあって、掘るばかりになっていた。いつもながら父の配慮には頭が下がる。一人一畝ずつ掘っていけよという私の言葉を合図に全員が掘り始める。半分以上が去年も来たことのある子供たちなので、スムーズに進んでいく。私が備中ぐわで掘り起こす必要もないくらい順調に芋を掘っていく。時期が早い割には大きな芋がいくつもあって、子供たちの歓声が響く。中には自分の顔と同じくらいのものを掘り出す子もいて、しばし大笑いをする。天気は何とかもってくれて、ひと時の楽しみに水を差さないでいてくれた。



掘った分だけは各自が持ってきたビニール袋に詰めて、もって帰れといってあるので、競争のようにして掘る子達もいてなかなか愉快だ。それでも、子供たちが掘り終わった畝を私が備中で掘り返していくと、掘り残した芋が出てくることもある。
出てきた芋を適当に振り分けると皆うれしそうな顔をする。それぞれが掘り終わって、それでも足りない子達にはさらにもう一畝掘らせた。こうやって各人の袋はパンパンに膨れあがった、大収穫だ。


全員で、父にお礼を言って帰ることになったが、こんな大きな袋を持って坂道を下りていくのは大変だ。だが、「気をつけろよ」と叫ぶ私の心配などまるで気にせず、なんとか全員無事にバスのところにたどり着いた。労をねぎらって、帰り道で近くにあった自動販売機で一人ずつに飲み物を買ってやった。
私にとっては毎年恒例の行事であるが、今年もやっぱり去年と同じ楽しい気持ちになった。
『本当に来年も同じようにイモを掘りたいなあ。』
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
ジパング
土曜日は、朝から夜遅くまでずっと塾の時間割が詰まっていて、一週間で一番忙しい日だ。しかし、昨日は遠隔地の生徒が欠席すると連絡があったので、バスで迎えに行く必要がなくなり、20分ほど時間が空いてしまった。バスに乗ったまま、道端で時間をつぶすのもつまらないから、何かいい暇つぶしはないかと考えてみたところ、「プールを見に行こう」と思い立った。市の東部の山間に25mプールがあり、子供の頃はよく泳ぎに行った。横を流れる川をせき止めてちょっとした自然のプールも作られているので、夏には涼を求めて家族連れでにぎわうちょっとした名所だ。私はたまたま8月の中旬にそこを通りかかったことがあるので、そのときの様子が写真に収めてあった。


今見ると暑かった日々が懐かしく感じられるほど、ここ数日はめっきり涼しくなった。雨がちな天気も多く、秋の空気が漂い始めている。そんな日にあのプールの今の様子を見に行くのも面白いかなと思ったのだ。車に乗っていけばさほど遠くない、ちょうど時間つぶしにはもってこいだ。早速塾バスで向かったのだが、国定公園に指定されているにもかかわらず、一年半ほど前に開通した東海環状道路という高速道路が近くを通っている。高架されていて、圧倒的なコンクリートの塊は周りの景観に全くそぐわない。大して利用する人もいない道路なのに、全く税金の無駄遣いだ、などと近くを通るたびに思ってしまう。


私は2、3度利用したことがあるが、通行車両が少なくてすいすい走っていける。これでは、また不良債権化するしかないだろうな、などとこの道路の行く末を案じてしまった。建設中は大型ダンプが市内をひっきりなしに走っていたが、さすがに今は随分静かになった。万博会場の建設とあわせて、特需の続いた地元建設業界は今どうなっているんだろう、などと余計なことまで考えてしまう。
プールにはすぐに着いた。当たり前のことといえども、まったく誰もいない。雨がしとしとと降っていたから余計にもの寂しい気がしたのかもしれないが、とにかく静まり返っていた。


8月末まではプールも開いていたはずだから、わずか2週間でこれほど中の水が緑になってしまうものかと驚いたが、川のせせらぎの音も聞こえてくるくらいの静寂の中では、この緑の水も時の流れを映すものとして趣深かった。
などと感慨にばかりふけっていられないので、バスで塾に戻っていったのだが、その途中で見事な景色に出会った。一帯が黄金色に輝いている。「おお、もう稲が実っているのか!」思わずバスを止め何枚か写真を撮った。



まさしく、「黄金の国ジパング」。マルコ・ポーロは実際に日本には来ていないようだが、こんな景色を見たら「地面が黄金でできている!」と「東方見聞録」に書き綴ったではなかろうか、そんな気がするほど見事に実っている。よく見ると、周りには刈り取った田もいくつかあったから、もう十分に収穫できるのだろう。それにしても随分早い気がする。それほど今年は稲の生育がよかったのだろうか。バスを降りて、田まで歩いていって写真を撮ってみた。

「実るほど頭をたれる稲穂かな」こんなありきたりな句しか浮かんでこないほど、立派に実っていた。


今見ると暑かった日々が懐かしく感じられるほど、ここ数日はめっきり涼しくなった。雨がちな天気も多く、秋の空気が漂い始めている。そんな日にあのプールの今の様子を見に行くのも面白いかなと思ったのだ。車に乗っていけばさほど遠くない、ちょうど時間つぶしにはもってこいだ。早速塾バスで向かったのだが、国定公園に指定されているにもかかわらず、一年半ほど前に開通した東海環状道路という高速道路が近くを通っている。高架されていて、圧倒的なコンクリートの塊は周りの景観に全くそぐわない。大して利用する人もいない道路なのに、全く税金の無駄遣いだ、などと近くを通るたびに思ってしまう。


私は2、3度利用したことがあるが、通行車両が少なくてすいすい走っていける。これでは、また不良債権化するしかないだろうな、などとこの道路の行く末を案じてしまった。建設中は大型ダンプが市内をひっきりなしに走っていたが、さすがに今は随分静かになった。万博会場の建設とあわせて、特需の続いた地元建設業界は今どうなっているんだろう、などと余計なことまで考えてしまう。
プールにはすぐに着いた。当たり前のことといえども、まったく誰もいない。雨がしとしとと降っていたから余計にもの寂しい気がしたのかもしれないが、とにかく静まり返っていた。


8月末まではプールも開いていたはずだから、わずか2週間でこれほど中の水が緑になってしまうものかと驚いたが、川のせせらぎの音も聞こえてくるくらいの静寂の中では、この緑の水も時の流れを映すものとして趣深かった。
などと感慨にばかりふけっていられないので、バスで塾に戻っていったのだが、その途中で見事な景色に出会った。一帯が黄金色に輝いている。「おお、もう稲が実っているのか!」思わずバスを止め何枚か写真を撮った。



まさしく、「黄金の国ジパング」。マルコ・ポーロは実際に日本には来ていないようだが、こんな景色を見たら「地面が黄金でできている!」と「東方見聞録」に書き綴ったではなかろうか、そんな気がするほど見事に実っている。よく見ると、周りには刈り取った田もいくつかあったから、もう十分に収穫できるのだろう。それにしても随分早い気がする。それほど今年は稲の生育がよかったのだろうか。バスを降りて、田まで歩いていって写真を撮ってみた。

「実るほど頭をたれる稲穂かな」こんなありきたりな句しか浮かんでこないほど、立派に実っていた。
コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )
旅
この前の土・日、わが市でお祭りが開かれた日、私の妻は娘と連れ立ってSMAPのコンサートを観るため東京に出かけていた。これで今年は確か4回目だったと思うが、名古屋公演のときに肋骨を痛めていた(とヲタの間ではもっぱらの噂)リーダー中居君が、あろうことか今度は足に肉離れをおこしてしまい、杖をついた状態でステージに現れ、全く踊ることができなかったそうだ。そのときの模様を写した写真がネットオークションで売られているのをパソコン上で見たが、なんでも商売に変えてしまうしたたかさと、どんな怪我をしていても決してステージに穴を開けたりしないプロ根性の見事さとが、同時に見られて複雑な気持ちにさせる写真だった。
お祭り2日目は、息子が名古屋の予備校で模試を受けた。朝早く起きて会場まで車で送ってやったのだが、妙な仏心がわいてきて、帰りも迎えに来てやろうという気になった。5時近くに息子を拾った私は、どうせなら妻も名古屋駅まで迎えに行ってやろうかと思い立って、妻の携帯に電話してみた。
「もしもし、今どこにいるの?」
「品川。水族館に行ってきた」
「えっ?まだ東京なの?もう5時過ぎてるよ」
「うん、今からご飯食べて、それから駅に行くつもり」
「ふ~ん、じゃあ、自分で帰って来いよ。迎えにはもう行かないから」
「分かった」
このときが5時半近く。それから私は家に帰って、適当に夕食の用意をして、息子と父の3人で食べた。後片付けをした後は、ビールを飲みながら、塾舎であれこれ作業をしていたのだが、ふっと気づくと10時近く、持ってきておいたビールも全部飲んでしまったので、冷えたビールを家まで取りに行った。すると、風呂から出てきた妻とばったり出会った。
「えっ?どうして?何でもういるの?早過ぎない?」
「だってもう10時だよ。9時半前には帰ってきてたよ」
「さっき電話したのが5時半だろ。そのときはまだ東京だったし、おかしくない?」
「6時20分頃ののぞみに乗って8時少し前に名古屋に着いた。それから地下鉄と電車に乗れば9時過ぎには帰ってこれるじゃん」
「そうなの、のぞみってめちゃくちゃ早いね」
「品川から名古屋まで、1時間半ぐらいかな」
品川は東京駅よりも名古屋寄りにあるから少しは近いのかもしれないが、それにしても東京までが1時間半・・ものすごい速さだ。私は京都までなら何回かのぞみに乗ったことがあるが、確かに速い。大げさに言えば弾丸のように空気を切り裂いて行く。私が大学生の頃よく乗ったひかりは、名古屋・京都間が約50分かかった。それがのぞみでは10分短縮されて40分で着く。本当にあっという間についてしまう。私の家から名古屋駅まで、車で1時間くらいかかるので、家から名古屋駅まで行くほうが時間がかかってしまう。おかしな話だ。
それにしてもこれだけ速いと、旅などではなく、点と点を結ぶ単なる移動手段にすぎない。途中で外の風景を楽しむとか、そこはかとない旅情に浸ってみるとかそんな心に潤いをもたらすような時間は与えてくれない。余りに効率的過ぎて、座席に座ったら外を眺めるよりも眠ってしまったほうがいい、そんな気さえするのではないだろうか。旅客ではなく貨物になってしまったような、そんな気が・・・
などと私のようにほとんど旅行などしたことのない者がしたり顔で言うのもおかしなものだが、ちょうど今娘がスペイン旅行の真最中だからそう思うのかもしれない。関西空港からアムステルダム経由でバルセロナ・グラナダ・セビリア・マドリッドを回って戻ってくる予定だが、こんな短期間で長い距離を移動して、果たしてスペインに対してどんな印象を抱いて帰ってくるのだろうか。「ああ、疲れた」などと言うくらいなら、行かなきゃいいのにと思わないでもないが、もし、「ただいま」とでも電話がかかってきたら、「疲れなかったか?大丈夫?」などと聞いてしまうだろうな、きっと。
お祭り2日目は、息子が名古屋の予備校で模試を受けた。朝早く起きて会場まで車で送ってやったのだが、妙な仏心がわいてきて、帰りも迎えに来てやろうという気になった。5時近くに息子を拾った私は、どうせなら妻も名古屋駅まで迎えに行ってやろうかと思い立って、妻の携帯に電話してみた。
「もしもし、今どこにいるの?」
「品川。水族館に行ってきた」
「えっ?まだ東京なの?もう5時過ぎてるよ」
「うん、今からご飯食べて、それから駅に行くつもり」
「ふ~ん、じゃあ、自分で帰って来いよ。迎えにはもう行かないから」
「分かった」
このときが5時半近く。それから私は家に帰って、適当に夕食の用意をして、息子と父の3人で食べた。後片付けをした後は、ビールを飲みながら、塾舎であれこれ作業をしていたのだが、ふっと気づくと10時近く、持ってきておいたビールも全部飲んでしまったので、冷えたビールを家まで取りに行った。すると、風呂から出てきた妻とばったり出会った。
「えっ?どうして?何でもういるの?早過ぎない?」
「だってもう10時だよ。9時半前には帰ってきてたよ」
「さっき電話したのが5時半だろ。そのときはまだ東京だったし、おかしくない?」
「6時20分頃ののぞみに乗って8時少し前に名古屋に着いた。それから地下鉄と電車に乗れば9時過ぎには帰ってこれるじゃん」
「そうなの、のぞみってめちゃくちゃ早いね」
「品川から名古屋まで、1時間半ぐらいかな」
品川は東京駅よりも名古屋寄りにあるから少しは近いのかもしれないが、それにしても東京までが1時間半・・ものすごい速さだ。私は京都までなら何回かのぞみに乗ったことがあるが、確かに速い。大げさに言えば弾丸のように空気を切り裂いて行く。私が大学生の頃よく乗ったひかりは、名古屋・京都間が約50分かかった。それがのぞみでは10分短縮されて40分で着く。本当にあっという間についてしまう。私の家から名古屋駅まで、車で1時間くらいかかるので、家から名古屋駅まで行くほうが時間がかかってしまう。おかしな話だ。
それにしてもこれだけ速いと、旅などではなく、点と点を結ぶ単なる移動手段にすぎない。途中で外の風景を楽しむとか、そこはかとない旅情に浸ってみるとかそんな心に潤いをもたらすような時間は与えてくれない。余りに効率的過ぎて、座席に座ったら外を眺めるよりも眠ってしまったほうがいい、そんな気さえするのではないだろうか。旅客ではなく貨物になってしまったような、そんな気が・・・
などと私のようにほとんど旅行などしたことのない者がしたり顔で言うのもおかしなものだが、ちょうど今娘がスペイン旅行の真最中だからそう思うのかもしれない。関西空港からアムステルダム経由でバルセロナ・グラナダ・セビリア・マドリッドを回って戻ってくる予定だが、こんな短期間で長い距離を移動して、果たしてスペインに対してどんな印象を抱いて帰ってくるのだろうか。「ああ、疲れた」などと言うくらいなら、行かなきゃいいのにと思わないでもないが、もし、「ただいま」とでも電話がかかってきたら、「疲れなかったか?大丈夫?」などと聞いてしまうだろうな、きっと。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
ガソリン
ガソリンの値段が高い。なんとなくは知っていたが、どれくらい高いものかさほど気にもしてなかった。塾生をバスで送迎しているため、ガソリンが今1ℓいくらするかくらいは把握しておいて当然なのに、はっきりとは知らなかった。というのも、ガソリンは掛売りで買っており、一か月ごとに請求書を作ってもらって、そこに書いてある金額をまとめて払っているだけだからだ。もう20年近くもずっと月ごとに支払う金額に注目するだけで、細かな明細はほとんど見たことがない。しかも、昨年の夏から、それまでは少し離れたスタンドまで行っていたのを、家の近くのスタンドも利用するようになったため、1軒あたりの請求書の金額が見かけ上は少なくなり、情けないことに、2軒合わせて支払っている金額の多さに気づかないで来てしまったようだ。
それが今月のはじめにガソリン代を払おうと2軒の請求書の金額を見たら、今まで見たことのない額が書かれていた。2軒合わせたら、とんでもないような額になってしまう。さすがにびっくりして請求書を細かく見なおしてみた。先月は夏休みで一日中走り回っていたため、ガソリンの消費が普段よりも多いのは当たり前だ。しかし、驚いたのが1ℓあたりの単価だ。1軒は137円、もう1軒は128円だったのが月の途中で136円に変わっている。びっくりした。ガソリンて今こんなに高いのか、全く知らなかった・・・
これはすごいことだと、今年の1月の同じスタンド(136円の方)の請求書を探してみたところ、121円と書いてあった。8ヶ月余りの間に、15円も値上がりしている。パーセントに直すと12.5%も上昇したことになる。と言ってもよく分からない、そこで、満タンに50ℓ入れたとすると、1月は6050円だったのが、8月になると6800円になり、満タン1回で、750円も値上がりしたことになる。私の家では、塾のバスだけでも、1ヶ月で合計10回近く給油するから7500円、さらに自家用車の給油まで考えれば、1万円以上の負担増になる。おお、すごい!何がすごいって、金額もさることながら、こんなに支出の多寡を計算までして調べたことなんて初めてなのだ。いつもどんぶり勘定ばかりで、お金がないないと文句ばかり言っている人間にしては上出来だ。
これを妻に報告すると、「何言ってるの、今頃。まだ上がってるんじゃないの?」と脅したので、少々心配になって給油がてら現在のガソリン価格を調べてきた。

おい、おい、本当だ。今現在は1ℓ=144円だ!赤字で小さく書いてあるように、私は会員割引がきくだろうから、142円。先月よりも5円上昇したことになる。う~ん、これは困った・・・いくら何でも高すぎる。バスの送迎は原則的に無料でやってきているため、ガソリン価格の高騰は実に痛い。
しかし、どうしてこんなに上がるのだろう。中東情勢が不安定で原油の輸出が減っているのだろうか。それともアメリカあたりが買い占めているのだろうか。中国の産業が発展を続け石油の消費量が増え、原油の生産が追いつかないのだろうか?などと、素人考えを並べてみても仕方ない。きっと私などでは理解できない複合的な要素が絡んでいるのだろう。
ちょっと調べてみたら、日本のガソリンの小売価格には、原油価格や精製・輸送コスト、国内石油元売り会社やスタンドの利益分だけでなく、原油を輸入する際にかかる関税や石油税、ガソリン税なども含まれていることが分かった。それは、1ℓ=130円で試算してみると、税金分は約62円にもなるという。なんと半分近くが税金だ、これはたまったものじゃない.
消費税など目に見える税金の増税もきついが、こうした隠れた税金というものも私たちは相当負担しているのだろう。「増税をいう前に、公的機関の無駄遣いを減らせよ」と、税金の問題で腹が立ってくると叫びたくなる。
それが今月のはじめにガソリン代を払おうと2軒の請求書の金額を見たら、今まで見たことのない額が書かれていた。2軒合わせたら、とんでもないような額になってしまう。さすがにびっくりして請求書を細かく見なおしてみた。先月は夏休みで一日中走り回っていたため、ガソリンの消費が普段よりも多いのは当たり前だ。しかし、驚いたのが1ℓあたりの単価だ。1軒は137円、もう1軒は128円だったのが月の途中で136円に変わっている。びっくりした。ガソリンて今こんなに高いのか、全く知らなかった・・・
これはすごいことだと、今年の1月の同じスタンド(136円の方)の請求書を探してみたところ、121円と書いてあった。8ヶ月余りの間に、15円も値上がりしている。パーセントに直すと12.5%も上昇したことになる。と言ってもよく分からない、そこで、満タンに50ℓ入れたとすると、1月は6050円だったのが、8月になると6800円になり、満タン1回で、750円も値上がりしたことになる。私の家では、塾のバスだけでも、1ヶ月で合計10回近く給油するから7500円、さらに自家用車の給油まで考えれば、1万円以上の負担増になる。おお、すごい!何がすごいって、金額もさることながら、こんなに支出の多寡を計算までして調べたことなんて初めてなのだ。いつもどんぶり勘定ばかりで、お金がないないと文句ばかり言っている人間にしては上出来だ。
これを妻に報告すると、「何言ってるの、今頃。まだ上がってるんじゃないの?」と脅したので、少々心配になって給油がてら現在のガソリン価格を調べてきた。

おい、おい、本当だ。今現在は1ℓ=144円だ!赤字で小さく書いてあるように、私は会員割引がきくだろうから、142円。先月よりも5円上昇したことになる。う~ん、これは困った・・・いくら何でも高すぎる。バスの送迎は原則的に無料でやってきているため、ガソリン価格の高騰は実に痛い。
しかし、どうしてこんなに上がるのだろう。中東情勢が不安定で原油の輸出が減っているのだろうか。それともアメリカあたりが買い占めているのだろうか。中国の産業が発展を続け石油の消費量が増え、原油の生産が追いつかないのだろうか?などと、素人考えを並べてみても仕方ない。きっと私などでは理解できない複合的な要素が絡んでいるのだろう。
ちょっと調べてみたら、日本のガソリンの小売価格には、原油価格や精製・輸送コスト、国内石油元売り会社やスタンドの利益分だけでなく、原油を輸入する際にかかる関税や石油税、ガソリン税なども含まれていることが分かった。それは、1ℓ=130円で試算してみると、税金分は約62円にもなるという。なんと半分近くが税金だ、これはたまったものじゃない.
消費税など目に見える税金の増税もきついが、こうした隠れた税金というものも私たちは相当負担しているのだろう。「増税をいう前に、公的機関の無駄遣いを減らせよ」と、税金の問題で腹が立ってくると叫びたくなる。
コメント ( 15 ) | Trackback ( 0 )
松井、松井、松井、松井!
絶対に目が覚める自信があった。目覚ましなどセットしなくとも、試合の始まる朝8時前には必ず目が覚めると信じていた。前夜、2時過ぎに缶ビールを1本飲んで、松井が復帰戦で活躍できるよう祈って、布団に入った。
当然のごとく、8時少し前に目が覚めた。すぐにTVを点けたら、前夜セットしたはずのDVDレコーダーが作動していない。松井が骨折して以来、4ヶ月近くも録画をセットなどしたことがなかったので、手順を間違えたのかもしれない。大急ぎでセットしなおしたが、試合前の松井のインタビューが終わったところからの録画になってしまった。それでも何とか間に合って、画面を見るとピンストライプのユニフォーム姿の松井がアップになっている。「おお、松井、おかえり・・」などと感慨にふける間もなく試合が始まった。だが、松井は守備につかずベンチで座っている。「ああ、DHだったな」そう思い出して、「ならば打順は?」と気にはなったが、デビルレイズの攻撃が終わるまで、松井の打順は分からなかった。「8番」、それを知ったときは「ええ?」とは思ったが、最初はこのくらいから肩慣らしをしていったほうがいいだろうと思い直したが、さすがに初回には登場しないだろうと思った。ところが、ヤンキースの猛攻はすさまじいものがあり、あっという間に松井まで打順が回ってしまった。1アウト1・3塁。どうしてこういうめぐり合わせになるのだろう。復帰後最初の打席が早く見る者をワクワクさせる場面になってしまう。
「ああ、久しぶりだ、野球を見ながらこんなにどきどきするのは。やっぱり松井がいなけりゃいけない」などと思いながらも、松井がバッターボックスに入りかけると目頭が熱くなってしまった。「やっと・・」そういう思いは、ヤンキースタジアムに集まった観客すべても同じだったのだろう、打席に入る松井を全員が立ち上がってスタンディングオベーションで迎えた。球場が割れんばかりの拍手だ。その声援に、少し気恥ずかしそうにヘルメットを外して応える松井、「ああ、松井は本当にニューヨークの人々に愛されているんだな」と胸まで熱くなってしまった。

初球ストライク。2球目ボール。3球目ファウル。2ストライク1ボールからの4球目、カーブをとらえてセンター前タイムリーヒット!
おお、ヒット!ヒット!ヒット!!思わず雄たけびを上げてしまった私とは対照的に少しばかりうれしそうな顔を見せながらも、1塁ベース上でいたって冷静な松井の姿を見て、「松井って本当にすごい男だなと」改めて思った。昨年、足首を捻挫しながらも強硬出場した第1打席でホームランを打ったのもすごかったが、今日の第1打席のヒットもそれ以上に私を感動させた。はじめは3ヶ月ほどで戦列復帰できるものと思われていたのが、両手を使ったバッティング練習の許可がなかなか下りずに周りをやきもきさせながらも、平然としていた松井だからこそ、どんな場面に立っても自分の持てる最大限の力が出せるのだと、今さらながら再認識した。焦らずひたすら己を信じてリハビリに励んできた成果を、第1打席で出してしまうのだから、もう私などには想像もできないような精神力の持ち主なのだろう。


その後、先頭打者で迎えた3回の第2打席では、真ん中低めのストレートをうまくはじき返し、ライト前ヒット。4回1死走者なしでの第3打席では、甘く入ったストレートを逆らわずに打ち、センター前ヒット。6回またも1死走者なしで迎えた第4打席は、外角のチェンジアップをたたき、センター前ヒット。開幕試合以来の4安打を放つと、観客は総立ちで松井秀の健闘をたたえた。8回、2死走者なしでの第5打席はフルカウントから6球目のボール球を見送って四球。ここで代走を送られ、松井秀は8回の攻撃で退いたが、この日は4打数4安打1打点の活躍で、打率は2割8分5厘となった。
全くすごい、すごすぎる!こんなことが起こっていいものかと思うくらいの大活躍だ。両ひざを曲げる角度を骨折以前よりも深くし、どっしりと構えていた。下半身にためた力をボールに伝えようという意図を持った打撃フォームの改造のようだが、5打席とも違うピッチャーと対し、緩急をつけた投球に惑わされることなく、軸がぶれることもなくボールを呼び込んで鋭く振りぬいていた。
長打が1本出ていればもっとうれしかったとは思うが、贅沢を言ってはいけない。そんなものすぐに打つに決まっている。それよりも何よりも、まずは松井が帰ってきてくれて、すぐに活躍できたことを祝おうではないか!!!
当然のごとく、8時少し前に目が覚めた。すぐにTVを点けたら、前夜セットしたはずのDVDレコーダーが作動していない。松井が骨折して以来、4ヶ月近くも録画をセットなどしたことがなかったので、手順を間違えたのかもしれない。大急ぎでセットしなおしたが、試合前の松井のインタビューが終わったところからの録画になってしまった。それでも何とか間に合って、画面を見るとピンストライプのユニフォーム姿の松井がアップになっている。「おお、松井、おかえり・・」などと感慨にふける間もなく試合が始まった。だが、松井は守備につかずベンチで座っている。「ああ、DHだったな」そう思い出して、「ならば打順は?」と気にはなったが、デビルレイズの攻撃が終わるまで、松井の打順は分からなかった。「8番」、それを知ったときは「ええ?」とは思ったが、最初はこのくらいから肩慣らしをしていったほうがいいだろうと思い直したが、さすがに初回には登場しないだろうと思った。ところが、ヤンキースの猛攻はすさまじいものがあり、あっという間に松井まで打順が回ってしまった。1アウト1・3塁。どうしてこういうめぐり合わせになるのだろう。復帰後最初の打席が早く見る者をワクワクさせる場面になってしまう。
「ああ、久しぶりだ、野球を見ながらこんなにどきどきするのは。やっぱり松井がいなけりゃいけない」などと思いながらも、松井がバッターボックスに入りかけると目頭が熱くなってしまった。「やっと・・」そういう思いは、ヤンキースタジアムに集まった観客すべても同じだったのだろう、打席に入る松井を全員が立ち上がってスタンディングオベーションで迎えた。球場が割れんばかりの拍手だ。その声援に、少し気恥ずかしそうにヘルメットを外して応える松井、「ああ、松井は本当にニューヨークの人々に愛されているんだな」と胸まで熱くなってしまった。

初球ストライク。2球目ボール。3球目ファウル。2ストライク1ボールからの4球目、カーブをとらえてセンター前タイムリーヒット!
おお、ヒット!ヒット!ヒット!!思わず雄たけびを上げてしまった私とは対照的に少しばかりうれしそうな顔を見せながらも、1塁ベース上でいたって冷静な松井の姿を見て、「松井って本当にすごい男だなと」改めて思った。昨年、足首を捻挫しながらも強硬出場した第1打席でホームランを打ったのもすごかったが、今日の第1打席のヒットもそれ以上に私を感動させた。はじめは3ヶ月ほどで戦列復帰できるものと思われていたのが、両手を使ったバッティング練習の許可がなかなか下りずに周りをやきもきさせながらも、平然としていた松井だからこそ、どんな場面に立っても自分の持てる最大限の力が出せるのだと、今さらながら再認識した。焦らずひたすら己を信じてリハビリに励んできた成果を、第1打席で出してしまうのだから、もう私などには想像もできないような精神力の持ち主なのだろう。


その後、先頭打者で迎えた3回の第2打席では、真ん中低めのストレートをうまくはじき返し、ライト前ヒット。4回1死走者なしでの第3打席では、甘く入ったストレートを逆らわずに打ち、センター前ヒット。6回またも1死走者なしで迎えた第4打席は、外角のチェンジアップをたたき、センター前ヒット。開幕試合以来の4安打を放つと、観客は総立ちで松井秀の健闘をたたえた。8回、2死走者なしでの第5打席はフルカウントから6球目のボール球を見送って四球。ここで代走を送られ、松井秀は8回の攻撃で退いたが、この日は4打数4安打1打点の活躍で、打率は2割8分5厘となった。
全くすごい、すごすぎる!こんなことが起こっていいものかと思うくらいの大活躍だ。両ひざを曲げる角度を骨折以前よりも深くし、どっしりと構えていた。下半身にためた力をボールに伝えようという意図を持った打撃フォームの改造のようだが、5打席とも違うピッチャーと対し、緩急をつけた投球に惑わされることなく、軸がぶれることもなくボールを呼び込んで鋭く振りぬいていた。
長打が1本出ていればもっとうれしかったとは思うが、贅沢を言ってはいけない。そんなものすぐに打つに決まっている。それよりも何よりも、まずは松井が帰ってきてくれて、すぐに活躍できたことを祝おうではないか!!!
コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )
「悪魔のささやき」
作家・加賀乙彦といえば「宣告」。これは大江健三郎の「個人的な体験」と並んで、現代日本文学の2大傑作だと、勝手に思い込んでいる私だが、もう20年以上も前に読んだきりなので、「どうすごいのか」とたずねられても返事に窮してしまう。ならば、偉そうに知ったかぶりするなよと、言いたくもなるが、先日加賀乙彦の新刊「悪魔のささやき」(集英社新書)を読んだものだから、どうしても触れずにいられない。さすがに、小説家の文章は読みやすく、多くの新書を読むときの表現の退屈さはいささかも感じられず(正確には口述筆記らしいのだが)、200ページ余りを一気に読み通すことができた。
久しぶりに加賀の文章に触れ、この人の考えは「宣告」以来変わっていないんだなと、懐かしい思いも抱いた。それなら、この本を若い人はどう読むのだろうかと、ユリカリさんにお尋ねしたところ、あっという間に読まれてブログにその感想まで書いてくださった。その迅速さには、さすが現役大学院生と舌を巻くばかりであるが、加賀乙彦の思いを的確にまとめてあり、さらに示唆に富む指摘まで書いてくださったのには感服した。お若いながら、「知の旅人」であるユリカリさんの旺盛な知識欲は、日々更新されるブログの記事からも理解していたつもりであったが、こうした文章にまとめられたものを読んで、改めて、敬意を表したいと思う。
したがって、「悪魔のささやき」の概要はユリカリさんのブログの記事に任せるとして、ここでは私の心にとまった箇所について少し述べてみたい。
第4章で、近年増加している子供たちによる凶悪犯罪について、安易に殺人まで犯してしまう理由を次の3つあげている。
①死というものの本質(恐ろしさ・苦しさ・醜さ)を子供たちが知らなすぎる。
②大人たち全体に対する抜きがたい不信の念を子供たちが根底に持っている。
③肉体を介したコミュニケーションが減っている。
これはよく目にする論調であるとは思うが、ここからさらに一歩踏み込んで、こうした精神的背景を持った子供たちが、己を抑制できず(キレてしまって)、ほんの些細な理由からいとも簡単に殺人に走ってしまう原因を『社会の刑務所化によって増大したストレス』だと、いかにも加賀乙彦らしい分析をしているが、それをまとめると以下のようになる。
鉄とコンクリートで作られたマンション・学校・オフィスビルで暮らし、「画一的な大量生産品」の食料を食べ衣類をまとっている現代生活は、徹底的に管理された刑務所の生活と似ている。「毎日決まった時間に起きて職場や学校に行き、決められたスケジュールに従って仕事や勉強をこなす。夜、帰宅すると、テレビ局が提供する決まりきった番組を眺める。休日には、大企業が準備した映画館やテーマパークやデパートを、これまた決まりきったやり方で利用する・・・」われわれの社会は自由に見えながらも、刑務所よりも自由がないのかもしれない。このように刑務所化した社会では、刑務所で起こるのと同じような問題が発生しかねない。
加賀は刑務所の医師として囚人たちを何人も見てきた経験から、こうした社会で生活するうちに拘禁反応(刑務所など強制的に自由を阻害された環境下で見られるノイローゼの一種)が起こって、「心理学で言う爆発反応―ほんの些細な刺激で突然キレて、予想外の行動をとることは大いにあり」、「大人以上に環境の影響を受けやすい子供たちなら、なおさら」だと述べる。
確かに私たちの生きている現代社会はとどまることなく常に動いている。どこに向かっているのか誰も知らないように見えるが、一刻もとどまることがないため、誰もがその流れから振り落とされないよう絶えず緊張している。そうした緊張感を持ち続けていなければ、流れから振り落とされてしまい、一度落ちてしまったら元には戻れない、そうしたプレッシャーを常に感じながら生きているように思われる。そうした状況の下、私も、大きな声を上げたくなることがよくある。未熟だからかもしれないが、一応世間的にはいい大人だと目される私でさえこうなのだから、子供たちが行き場のないストレスを心にもち続け、ふとしたことで爆発してしまう可能性は誰にだってあるように思えてしまう。
加賀はそうした「悪魔のささやき」に子供たちが負けないようにするには、「子供たちから死を遠ざけるのをやめて、できるだけ本物の死の怖さ、苦しさ、悲しさをリアルに実感するチャンスを増やしてやることが大切だ」と述べる。「死ぬと人はどうなるか、一人の人間の死が周囲の人々にどれほど心理的な影響をおよぼすかを、きちんと教える。子供たちと一緒に死について語り、考えていく」ことが必要だと。
そのとおりだと思う、まったく異論はない。ただ一言付け加えるなら、もうちょっと「我慢すること」を子供だけでなく、大人も学ばなけりゃいけないだろうとは思う。現代の日本、余りに忍耐力というものが弱くなっているような気がして仕方がない。
久しぶりに加賀の文章に触れ、この人の考えは「宣告」以来変わっていないんだなと、懐かしい思いも抱いた。それなら、この本を若い人はどう読むのだろうかと、ユリカリさんにお尋ねしたところ、あっという間に読まれてブログにその感想まで書いてくださった。その迅速さには、さすが現役大学院生と舌を巻くばかりであるが、加賀乙彦の思いを的確にまとめてあり、さらに示唆に富む指摘まで書いてくださったのには感服した。お若いながら、「知の旅人」であるユリカリさんの旺盛な知識欲は、日々更新されるブログの記事からも理解していたつもりであったが、こうした文章にまとめられたものを読んで、改めて、敬意を表したいと思う。
したがって、「悪魔のささやき」の概要はユリカリさんのブログの記事に任せるとして、ここでは私の心にとまった箇所について少し述べてみたい。
第4章で、近年増加している子供たちによる凶悪犯罪について、安易に殺人まで犯してしまう理由を次の3つあげている。
①死というものの本質(恐ろしさ・苦しさ・醜さ)を子供たちが知らなすぎる。
②大人たち全体に対する抜きがたい不信の念を子供たちが根底に持っている。
③肉体を介したコミュニケーションが減っている。
これはよく目にする論調であるとは思うが、ここからさらに一歩踏み込んで、こうした精神的背景を持った子供たちが、己を抑制できず(キレてしまって)、ほんの些細な理由からいとも簡単に殺人に走ってしまう原因を『社会の刑務所化によって増大したストレス』だと、いかにも加賀乙彦らしい分析をしているが、それをまとめると以下のようになる。
鉄とコンクリートで作られたマンション・学校・オフィスビルで暮らし、「画一的な大量生産品」の食料を食べ衣類をまとっている現代生活は、徹底的に管理された刑務所の生活と似ている。「毎日決まった時間に起きて職場や学校に行き、決められたスケジュールに従って仕事や勉強をこなす。夜、帰宅すると、テレビ局が提供する決まりきった番組を眺める。休日には、大企業が準備した映画館やテーマパークやデパートを、これまた決まりきったやり方で利用する・・・」われわれの社会は自由に見えながらも、刑務所よりも自由がないのかもしれない。このように刑務所化した社会では、刑務所で起こるのと同じような問題が発生しかねない。
加賀は刑務所の医師として囚人たちを何人も見てきた経験から、こうした社会で生活するうちに拘禁反応(刑務所など強制的に自由を阻害された環境下で見られるノイローゼの一種)が起こって、「心理学で言う爆発反応―ほんの些細な刺激で突然キレて、予想外の行動をとることは大いにあり」、「大人以上に環境の影響を受けやすい子供たちなら、なおさら」だと述べる。
確かに私たちの生きている現代社会はとどまることなく常に動いている。どこに向かっているのか誰も知らないように見えるが、一刻もとどまることがないため、誰もがその流れから振り落とされないよう絶えず緊張している。そうした緊張感を持ち続けていなければ、流れから振り落とされてしまい、一度落ちてしまったら元には戻れない、そうしたプレッシャーを常に感じながら生きているように思われる。そうした状況の下、私も、大きな声を上げたくなることがよくある。未熟だからかもしれないが、一応世間的にはいい大人だと目される私でさえこうなのだから、子供たちが行き場のないストレスを心にもち続け、ふとしたことで爆発してしまう可能性は誰にだってあるように思えてしまう。
加賀はそうした「悪魔のささやき」に子供たちが負けないようにするには、「子供たちから死を遠ざけるのをやめて、できるだけ本物の死の怖さ、苦しさ、悲しさをリアルに実感するチャンスを増やしてやることが大切だ」と述べる。「死ぬと人はどうなるか、一人の人間の死が周囲の人々にどれほど心理的な影響をおよぼすかを、きちんと教える。子供たちと一緒に死について語り、考えていく」ことが必要だと。
そのとおりだと思う、まったく異論はない。ただ一言付け加えるなら、もうちょっと「我慢すること」を子供だけでなく、大人も学ばなけりゃいけないだろうとは思う。現代の日本、余りに忍耐力というものが弱くなっているような気がして仕方がない。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
パン
朝起きると、すぐに水をコップ1杯飲む。朦朧とした頭を少しばかりしゃきっとさせるには、冷たい水が一番だ。ぐっと一気に飲み干して次に私がすることは、朝食に食べるパンを物色することだ。パンといっても、食パンを焼いてトーストにして・・などと面倒なことはしたことがない。朝食には、いつも買い置きしてある菓子パンを1つ食べる。もうずいぶん長い間、こうした朝を迎えているので、食べるパンの種類はほぼ決まっている。アンパンは必ず週に1回か2回は食べるが、それ以外には「~サンド」と呼ばれる、棒状の柔らかなパンの中に色んな種類のクリームがはさんであるパンを好んで食べている。その中でも、定番と呼んでいいものをいくつか載せてみようと思う。


まずはチョコレートサンド。これは子供のときから食べてきた。チョコレートが柔らかくべたべたしていて、口の周りについたりしたことが、子供のときにはよくあったが、さすがに今はそこまでだらしない食べ方はしてないはずだ・・・と思う。


「ダブルバナナ」と言う名は、バナナクリームが2本平行に挟まれているからだ。バナナの量が多いのだろう、封を空けた瞬間にバナナの香りがしてきて食欲をそそる。甘くて実においしい。


ダブルと言えば、この「ダブルメロン」も絶品だ。メロンのおいしさがそのまま封じ込まれたようなクリームが2重でたっぷり入っている。メロン本来よりも甘いが、甘すぎるほどではなく、私が今一番好きな「サンド」である。今どのパンが食べたい?ときかれたら、ためらいなくこの「ダブルメロン」を選ぶだろう。


このピーナツサンドも、チョコサンドと同じくらい私にとっては昔から馴染み深いパンである。ピーナツが細かく砕かれて、粒々感が味わえるようになったのが昔と違うところであるが、味としては昔のままであり、安心して食べられるパンだ。


やはり真打はこの「小倉&ネオマーガリン」だ。あんことマーガリンがこれほど合うものかと初めて食べたとき、本当に体中が感動で震える気がした。もうずいぶん昔のことだが、今でも食べるたびにそのときの感動がよみがえる。私にとっては永遠の、なくてはならない伴侶のようなパンである。

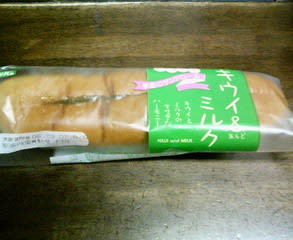
さらにこれらは、季節限定物と呼ばれるパンであるが、こうした謂わば番外編のようなパンも時によると買ってきてある。冒険心が薄れつつある私としては、無難に定番のパンで十分なのだが、買ってきた妻の手前、食べないわけには行かない。無理やり食べてみたのだが、キウイのサンドはなかなか刺激的な味がして、眠気を一瞬吹き飛ばしてくれた。巨峰サンドは、さほどインパクトはなかったが、私なりのおいしさの基準はクリアーしていた。
これらを毎朝、いい加減なローテーションで食べている。この中のものだったら、何を食べてもおいしいから選ぶのに大して苦労はしない。最初に触ったものから食べることにしている。


まずはチョコレートサンド。これは子供のときから食べてきた。チョコレートが柔らかくべたべたしていて、口の周りについたりしたことが、子供のときにはよくあったが、さすがに今はそこまでだらしない食べ方はしてないはずだ・・・と思う。


「ダブルバナナ」と言う名は、バナナクリームが2本平行に挟まれているからだ。バナナの量が多いのだろう、封を空けた瞬間にバナナの香りがしてきて食欲をそそる。甘くて実においしい。


ダブルと言えば、この「ダブルメロン」も絶品だ。メロンのおいしさがそのまま封じ込まれたようなクリームが2重でたっぷり入っている。メロン本来よりも甘いが、甘すぎるほどではなく、私が今一番好きな「サンド」である。今どのパンが食べたい?ときかれたら、ためらいなくこの「ダブルメロン」を選ぶだろう。


このピーナツサンドも、チョコサンドと同じくらい私にとっては昔から馴染み深いパンである。ピーナツが細かく砕かれて、粒々感が味わえるようになったのが昔と違うところであるが、味としては昔のままであり、安心して食べられるパンだ。


やはり真打はこの「小倉&ネオマーガリン」だ。あんことマーガリンがこれほど合うものかと初めて食べたとき、本当に体中が感動で震える気がした。もうずいぶん昔のことだが、今でも食べるたびにそのときの感動がよみがえる。私にとっては永遠の、なくてはならない伴侶のようなパンである。

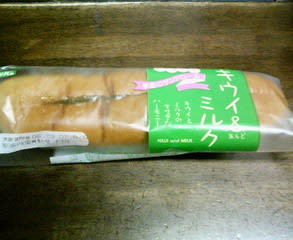
さらにこれらは、季節限定物と呼ばれるパンであるが、こうした謂わば番外編のようなパンも時によると買ってきてある。冒険心が薄れつつある私としては、無難に定番のパンで十分なのだが、買ってきた妻の手前、食べないわけには行かない。無理やり食べてみたのだが、キウイのサンドはなかなか刺激的な味がして、眠気を一瞬吹き飛ばしてくれた。巨峰サンドは、さほどインパクトはなかったが、私なりのおいしさの基準はクリアーしていた。
これらを毎朝、いい加減なローテーションで食べている。この中のものだったら、何を食べてもおいしいから選ぶのに大して苦労はしない。最初に触ったものから食べることにしている。
コメント ( 27 ) | Trackback ( 0 )
一期一会
高校の卒業アルバムに、生徒の一言メッセージを載せる箇所があった。私は「早く所帯を持って落ち着きたい。でも、それで落ち着けるのだろうか。何もわからない」などと、今思えば意味不明のコメントを書いてしまったのだが、何を書いたらいいのか分からない友人から代筆を頼まれた。まあ、他人のことだから適当に書いておけばいいやと、その朝新聞で目に留まった「一期一会」と言う言葉を使って、正確な意味も分からぬまま、「一期一会を大切に」と書いてやったら、その友人は大喜びで、「ありがとう」などと言ってくれたのだが、内心は穏やかならぬものがあった。一生の記念に残る卒業アルバムに、いい加減な思いつきで文言を書いていいのかと後悔もした。
「一期一会」・・・茶の湯で、茶会は毎回、一生に一度だという思いをこめて、主客とも誠心誠意、真剣に行うべきことを説いた語。転じて、一生に一度しかない出会い。一生に一度かぎりであること。(「大辞泉」より)
しかし、ある程度の意味は理解していたからさほど無礼なことをしたわけではないかもしれない。「一生に一度しかない出会い」というのは出会いを大切にしろという意味なのだろうが、その出会いを一生一度のものにするか、永続的なものにするかは出会った者同士がどう接するかによって決まってくるように思う。出会いはどこにでもある。しかし、それが長く続くことは稀であり、多くは一度きりの出会いで終わってしまう。それを縁がなかったと片付けるのは容易だが、果たしてそうだろうか。縁があるかどうか、それは結果論でしかない。うまく関係が続けられれば縁があった、うまくいかなかったら縁がなかったで済ましてしまったら、人の出会いとはすべて偶然の産物によるものとなってしまうだろう。
しかし、それでは余りに寂しい。すべてを偶然に委ねてしまったら、人智の介入する余地などなくなってしまう。人がある人に出会う、それは確かに偶然かもしれない。しかし、出会ったときにその相手が自分の存在にとって大切な人であるかどうかは本能的に見分けることができると思う。それができなければ人間という動物はここまで生き延びてこられなかったはずだから。しかし、そうした本能に導かれた後は人智を働かせねばならない。大切だと思った人と永続的な関係を築き上げるためにはそれなりの努力が必要だ。そのためには、己を相手に知ってもらうこと、ありのままの自分を相手に知ってもらうことが必要だと思うし、己がどれだけの人間であるか、それをどれだけ相手にさらすことができるかによってその関係の深さが決まる、そう思えて仕方がない。
9月11日は、アメリカに航空機を使った同時テロが仕掛けられた日だ。あれから5年たって、アメリカの専横さばかりが目立って、アメリカのイラク戦争に踏み出した「テロとの戦い」というキャッチフレーズも色あせて見えるが、それにしてもあの事件は衝撃的であった。あれから5年もたつのかと時の流れの速さを憂いても仕方ないのだが、私にとっての9月11日は昨年から同時テロとは別の、特別な日になった。それはこの日がゴジ健さんの誕生日だからだ。
ゴジ健さんとは、ヤフーの掲示板・松井トピで知り合いになったのだが、ひょんなことから私のこのブログにも訪ねてくださるようになり親交が深まった。その後お互いに胸襟を開いて語り合うようになって、彼から色々なアドバイスを頂いたり、教えていただくこともしばしばだった。私が迷惑をおかけすることばかりで、申し訳なく思っている。同じ昭和33年生まれながら、私のほうがはるかに精神的に劣っていることを痛感させられることばかりであったが、ゴジ健さんは愛想もつかされずここまで付き合ってくださった。感謝の気持ちは言葉で言い表しようもないほどだ。
私が一方的に一期一会を悪用しただけの関係のような気もするが、それもすべて包み込むようなおおらかさがゴジ健さんにはある。ネットの功罪はいくつもあるだろうが、私はゴジ健さんと知り合えたことだけでも、ネットはすばらしい世界を私たちに与えてくれるものだと思っている。この出会いは一生の宝としてこれからも大切にしていかねばならない。
Happy Birthday Mr.Godziken!!!


「一期一会」・・・茶の湯で、茶会は毎回、一生に一度だという思いをこめて、主客とも誠心誠意、真剣に行うべきことを説いた語。転じて、一生に一度しかない出会い。一生に一度かぎりであること。(「大辞泉」より)
しかし、ある程度の意味は理解していたからさほど無礼なことをしたわけではないかもしれない。「一生に一度しかない出会い」というのは出会いを大切にしろという意味なのだろうが、その出会いを一生一度のものにするか、永続的なものにするかは出会った者同士がどう接するかによって決まってくるように思う。出会いはどこにでもある。しかし、それが長く続くことは稀であり、多くは一度きりの出会いで終わってしまう。それを縁がなかったと片付けるのは容易だが、果たしてそうだろうか。縁があるかどうか、それは結果論でしかない。うまく関係が続けられれば縁があった、うまくいかなかったら縁がなかったで済ましてしまったら、人の出会いとはすべて偶然の産物によるものとなってしまうだろう。
しかし、それでは余りに寂しい。すべてを偶然に委ねてしまったら、人智の介入する余地などなくなってしまう。人がある人に出会う、それは確かに偶然かもしれない。しかし、出会ったときにその相手が自分の存在にとって大切な人であるかどうかは本能的に見分けることができると思う。それができなければ人間という動物はここまで生き延びてこられなかったはずだから。しかし、そうした本能に導かれた後は人智を働かせねばならない。大切だと思った人と永続的な関係を築き上げるためにはそれなりの努力が必要だ。そのためには、己を相手に知ってもらうこと、ありのままの自分を相手に知ってもらうことが必要だと思うし、己がどれだけの人間であるか、それをどれだけ相手にさらすことができるかによってその関係の深さが決まる、そう思えて仕方がない。
9月11日は、アメリカに航空機を使った同時テロが仕掛けられた日だ。あれから5年たって、アメリカの専横さばかりが目立って、アメリカのイラク戦争に踏み出した「テロとの戦い」というキャッチフレーズも色あせて見えるが、それにしてもあの事件は衝撃的であった。あれから5年もたつのかと時の流れの速さを憂いても仕方ないのだが、私にとっての9月11日は昨年から同時テロとは別の、特別な日になった。それはこの日がゴジ健さんの誕生日だからだ。
ゴジ健さんとは、ヤフーの掲示板・松井トピで知り合いになったのだが、ひょんなことから私のこのブログにも訪ねてくださるようになり親交が深まった。その後お互いに胸襟を開いて語り合うようになって、彼から色々なアドバイスを頂いたり、教えていただくこともしばしばだった。私が迷惑をおかけすることばかりで、申し訳なく思っている。同じ昭和33年生まれながら、私のほうがはるかに精神的に劣っていることを痛感させられることばかりであったが、ゴジ健さんは愛想もつかされずここまで付き合ってくださった。感謝の気持ちは言葉で言い表しようもないほどだ。
私が一方的に一期一会を悪用しただけの関係のような気もするが、それもすべて包み込むようなおおらかさがゴジ健さんにはある。ネットの功罪はいくつもあるだろうが、私はゴジ健さんと知り合えたことだけでも、ネットはすばらしい世界を私たちに与えてくれるものだと思っている。この出会いは一生の宝としてこれからも大切にしていかねばならない。
Happy Birthday Mr.Godziken!!!



コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |





