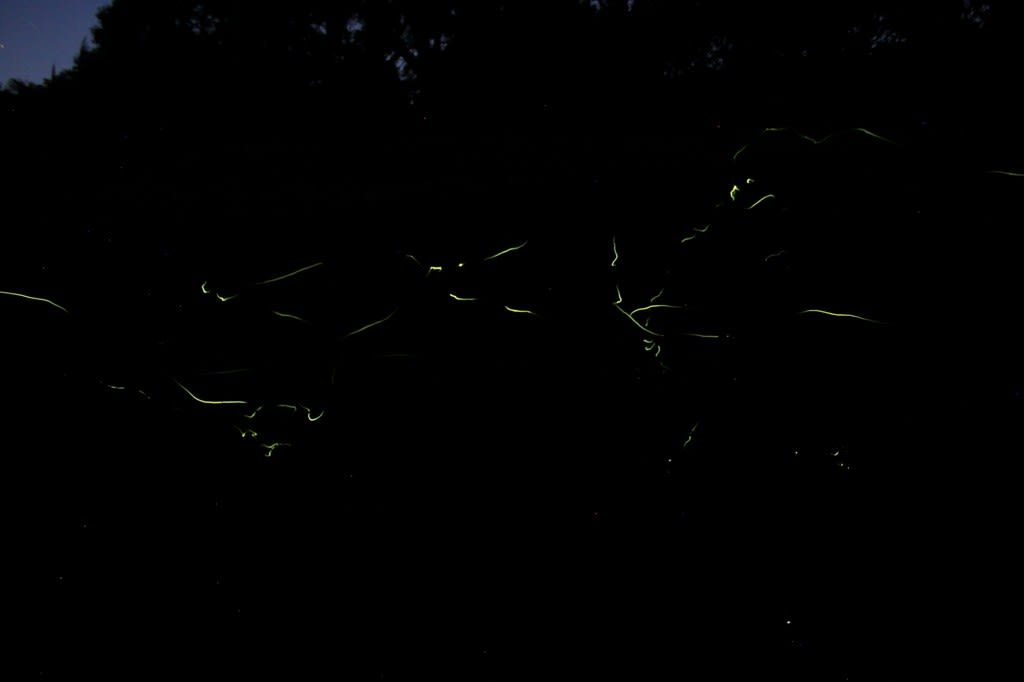今日の花


歩道の中で街路樹の植えてある根本に土の出ているスペースがありますよね。そのスペースに時々お花を植えている人がいます。
今日は、2カ月ぶりで徳山の眼科医へ目の検診に行ってきました。
昨年の秋に、突然発症した目の病気 加齢性黄班変性 の治療と検査のため10月からずっと月一で徳山の眼科医へ通っています。11月・12月・1月と三か月間治療を受けました。2月以降は月一で予後の検査を受けましたが、4月の検査ではほとんど良くなったと判断していただいたので、5月の検診はお休みにしました。所が5月の下旬ごろから軽い症状ながら黄班変性が再発している感じがありました。そんな状態なので今回の検診ではとても心配でしたが、網膜の断層写真を見ると確かに一部の網膜が基底から少しだけ離れているのが見られました。お医者さんの見立てでは出血は無いようなのでもう少し様子を見ましょうとの診断でした。執行猶予が付きましたがこの先どのように病状が進むかは分かりません。私は仕事柄野外の炎天下での仕事が多いので、お医者さんに強い紫外線はこの病気に悪影響があるのかどうか聞いてみました。出来るだけ避けた方が良いとの答えでした。どうすればいいのでしょうね。サングラスで遮るにしても色の濃い薄いは関係ないそうです。要するにどれほど紫外線をカットできるかどうかにかかっているそうです。メガネ屋さんへ行って相談しなければならないかもしれません。
家を出る時から素晴らしく良い天気だったので、小さなカメラを持って行きました。昨年の秋から気付いていたのですが、周南市はなかなか街路樹がきれいなのです。4月に行った時にはまだ新芽が出たばかりでしたが今回は緑がとてもきれいでした。昨年の暮れに大きく切りこまれた「ナンキンハゼ」はさすがにまだ回復していませんでした。銀杏並木は緑がすごくきれいでした。銀杏の実がもう大きくなっているのにはびっくりしました。
目の治療や検査には瞳孔を大きく開いて行いますので自分の運転で病院へ行くことはできません。それで毎月電車で徳山まで行きます。そして駅から病院までバスでも行けるのですが、知らない街を歩く楽しみがあるので徒歩で行きます。そして、毎回歩く経路を変えてみます。いろんな発見があって楽しいです。今日の経路では小さな子供が沢山いるのに驚きました。気が付いてみると近くに幼稚園がありました。
次の検査は7月です。きっと暑いでしょうね。
山陽線 大畠駅から徳山駅まで電車で行きます。車社会ですから普段電車にはめったに乗りません。
大畠駅にて






電車が入って来ましたが、わずか2両編成です。乗る人は私を含めてたったの3人です。
徳山に着きました
徳山駅はまだ完成していませんでした。

どの道を歩こうと悩みながら歩き始めました。






子供が多いです。

昨年の秋




ナンキンハゼは昨年の末に大きく切りこまれました。まだ十分に回復していません。

ピンクの建物は郵便局です

約20分かかってようやく眼科医院に着きました。

帰り道はほとんど同じです。


銀杏が沢山なっています。
小さな子供をよく見かけました。


徳山駅から北に延びる大通りです。植えたのがが古いのでしょう、街路樹が見事に育っています。



周南市の新しい市役所が出来上がっていました。

昨年の秋


秋の歩道
今日も楽しい街歩きでした。徳山駅に着きました。


駅に図書館ができたのです。