先日、境港の夢みなとタワーで開催されていた地球動物館(一種の出張動物園)の売店でアリが巣を作る様子を観察できるキットが売られていました。
夏休みの自由研究にするかどうかはともかく、これまでも時々息子とアリの観察はしていたのと、楽しそうだったので、その日行った地球動物館とは直接の関係はなかったのですが、購入することにしました。

これまでのアリの観察については、下記の記事を参照してください(↓)。
新見高校北校地文化祭
Many Happy Returns of the Day!!
ムシの日
ムシの日続報
アリにもいろんな種類がいるので、どんなアリで実験がしたいか尋ねたところ、大きいアリでしたいとの答えでした。
大きいアリというとよく山などにいるオオヤマアリがいます。

(写真では大きさがわからないと思いますが、新見市を北上し鳥取県堺を越えたところにある明智峠で見たオオヤマアリです)
でも、実験が終わったらまた巣に返してやるので、家のそばにいるクロヤマアリにしました。

クロヤマアリを5匹捕まえてこのキット内に入れました。

アリたちは自分たちが囚われの身になったことに気づいたようで、最初パニック状態のように容器の中を駆け回っていました。
そのうち落ち着いてお互い触覚を触れ合いながら現状確認(情報交換)をしているようでした。
一説によると、働きアリのうちしっかり働くのは2割しかいない、ということですので、その説を信じれば5匹のうちしっかりと働くのは1匹ということになります。
当初は、5匹のうち1匹が少し離れて行動をしているように感じていました。
個体区別ができないので、いつも同じ1匹が単独行動をしているのかどうかの識別はできませんでしたが、アリにも一匹狼的な存在がいるのかなと思いました。
このキットでは、オレンジの部分(いろんな色が販売されていましたが)がアリのエサとなるゼリーになっています。
だからアリは巣作りをしながら食事もできるということとなります(普段、自然界ではアリは土を食べないわけなので、その意味では自然界と全く異なる環境でアリたちを飼育することになりますが…)。
次第に、アリたちは食事兼穴掘りをしてこのような巣ができてきます。


しかし、1週間もするとアリたちはあまり動かなくなりました。
時々、換気のため蓋を少し開けてやると動き出しますが、それ以外は大体身を寄せて固まっているだけです。
それはそうでしょう。アリたちにとってもせっせと働いたり巣作りをしたりする意味がないのですから。
当初、1匹離れた状態でいることが多かったのですが、最近は5匹が固まっていることが多くなりました。
特殊な環境に置かれて、運命共同体的な意識がアリたちの行動を変えたのでしょうか?
息子がアリに興味を深めたので、アリのことを調べに図書館に行こうと誘ってみました。
まず、カウンター前のパソコンで蔵書検索をしてアリ関係の蔵書を調べてみました。
その後、書架に行き、それらの本を集め、調べてみます。
本を読んで、何か大切なことが書いてあったらノートに書き写すように息子に言ってみました。

パソコンの蔵書検索で調べたけど書架になかった本についてはカウンターの図書館員さんに尋ね閉架式のコーナーから持ってきてもらうようお願いすることも教えました。
そして、家でも読むために何冊かの本も借りてきました。
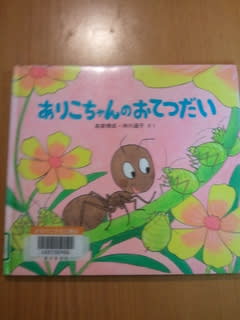
これは絵本ですがアリの生態に基づいたストーリーでよかったです。
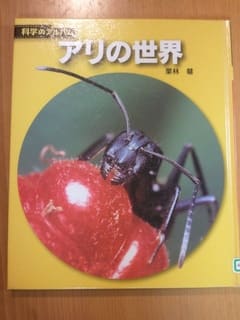
この書の旧版は僕が子どもの頃持っていたものですが(読書案内:栗林 慧(サトシ) 『アリの世界』科学のアルバム7(あかね書房, 1973)参照)、新版があったので借りてきました。
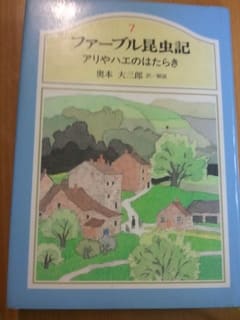
僕は小学校の5,6年生の頃、ファーブル昆虫記(やシートン動物記)はほとんど読みましたが、久しぶりに借りてみました。
小学1年生の息子には、まだちょっと難しいようでした。
ちなみにこの版は、フランス文学者で昆虫研究もされている奥本大三郎先生翻訳のものです。
奥本先生は、僕は直接教えていただいたことはありませんが、僕の母校横浜国立大学でも教鞭を取られたこともあり、僕自身は奥本先生の著書を読みお手紙を書いたことがあります。
このようにせっかく親子でアリの研究をしましたが、夏休みの自由研究としてはまとめませんでした。
また来年以降、取り組みたいと思います。
夏休みの自由研究にするかどうかはともかく、これまでも時々息子とアリの観察はしていたのと、楽しそうだったので、その日行った地球動物館とは直接の関係はなかったのですが、購入することにしました。

これまでのアリの観察については、下記の記事を参照してください(↓)。
新見高校北校地文化祭
Many Happy Returns of the Day!!
ムシの日
ムシの日続報
アリにもいろんな種類がいるので、どんなアリで実験がしたいか尋ねたところ、大きいアリでしたいとの答えでした。
大きいアリというとよく山などにいるオオヤマアリがいます。

(写真では大きさがわからないと思いますが、新見市を北上し鳥取県堺を越えたところにある明智峠で見たオオヤマアリです)
でも、実験が終わったらまた巣に返してやるので、家のそばにいるクロヤマアリにしました。

クロヤマアリを5匹捕まえてこのキット内に入れました。

アリたちは自分たちが囚われの身になったことに気づいたようで、最初パニック状態のように容器の中を駆け回っていました。
そのうち落ち着いてお互い触覚を触れ合いながら現状確認(情報交換)をしているようでした。
一説によると、働きアリのうちしっかり働くのは2割しかいない、ということですので、その説を信じれば5匹のうちしっかりと働くのは1匹ということになります。
当初は、5匹のうち1匹が少し離れて行動をしているように感じていました。
個体区別ができないので、いつも同じ1匹が単独行動をしているのかどうかの識別はできませんでしたが、アリにも一匹狼的な存在がいるのかなと思いました。
このキットでは、オレンジの部分(いろんな色が販売されていましたが)がアリのエサとなるゼリーになっています。
だからアリは巣作りをしながら食事もできるということとなります(普段、自然界ではアリは土を食べないわけなので、その意味では自然界と全く異なる環境でアリたちを飼育することになりますが…)。
次第に、アリたちは食事兼穴掘りをしてこのような巣ができてきます。


しかし、1週間もするとアリたちはあまり動かなくなりました。
時々、換気のため蓋を少し開けてやると動き出しますが、それ以外は大体身を寄せて固まっているだけです。
それはそうでしょう。アリたちにとってもせっせと働いたり巣作りをしたりする意味がないのですから。
当初、1匹離れた状態でいることが多かったのですが、最近は5匹が固まっていることが多くなりました。
特殊な環境に置かれて、運命共同体的な意識がアリたちの行動を変えたのでしょうか?
息子がアリに興味を深めたので、アリのことを調べに図書館に行こうと誘ってみました。
まず、カウンター前のパソコンで蔵書検索をしてアリ関係の蔵書を調べてみました。
その後、書架に行き、それらの本を集め、調べてみます。
本を読んで、何か大切なことが書いてあったらノートに書き写すように息子に言ってみました。

パソコンの蔵書検索で調べたけど書架になかった本についてはカウンターの図書館員さんに尋ね閉架式のコーナーから持ってきてもらうようお願いすることも教えました。
そして、家でも読むために何冊かの本も借りてきました。
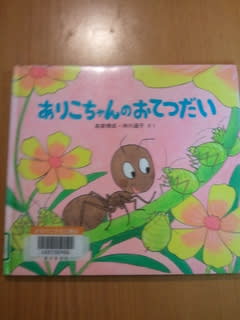
これは絵本ですがアリの生態に基づいたストーリーでよかったです。
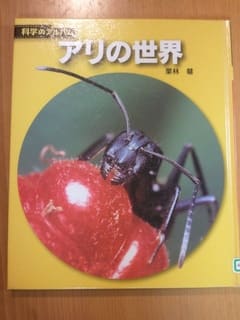
この書の旧版は僕が子どもの頃持っていたものですが(読書案内:栗林 慧(サトシ) 『アリの世界』科学のアルバム7(あかね書房, 1973)参照)、新版があったので借りてきました。
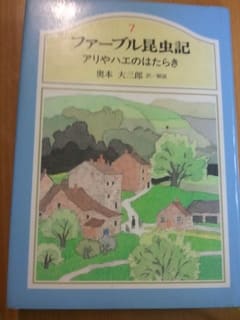
僕は小学校の5,6年生の頃、ファーブル昆虫記(やシートン動物記)はほとんど読みましたが、久しぶりに借りてみました。
小学1年生の息子には、まだちょっと難しいようでした。
ちなみにこの版は、フランス文学者で昆虫研究もされている奥本大三郎先生翻訳のものです。
奥本先生は、僕は直接教えていただいたことはありませんが、僕の母校横浜国立大学でも教鞭を取られたこともあり、僕自身は奥本先生の著書を読みお手紙を書いたことがあります。
このようにせっかく親子でアリの研究をしましたが、夏休みの自由研究としてはまとめませんでした。
また来年以降、取り組みたいと思います。















