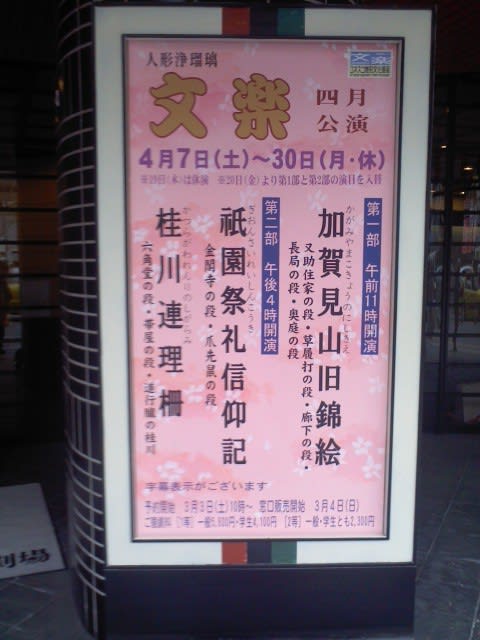前日に「荒川の佐吉」と併せて見ようと思ったが既に売り切れていたため、
次の日、改めて「渡海屋・大物浦」を見に来た。
吉右衛門の知盛が目当て。
明礬の人足の会話の後、
義経を追いかける「頼朝の家来」だという連中が「舟を出せ」と言ってくる。
そこに船問屋の主銀平が帰ってきて追い返す。
実はこれは、義経に銀平らが味方だと信頼させるための計略で、
その後銀平は知盛の正体を現す。
その後海沿いの仮御所で注進を受ける場面があり、
知盛の立ち回り、
最後は安徳帝を義経に託して碇を持って入水する。
吉右衛門は渡海屋の場面が良かった。
この場面、世話物の場面ではあるのだが、時代物のハラがベースに必要だと思う。
吉右衛門の銀平は基本的に糸に乗りつつ、
微妙に世話らしく崩すバランスが快い。
鎌倉方の侍に対し、商人っぽく下手に出る感じ、
逆に上から押さえる決め付け方、
このあたりの緩急の付け方が良かった。
それに比べると、立ち回りや恨みを持っての述懐はあまり良くないな。
安徳帝を委ねるあたりの改心の調子は良かった。
ただそれでも、渡海屋の素晴らしさに比べると不満。
身を隠してまで義経を討とうとした恨みや執念があまり感じられないせいかな。
ここが浅いと、後で安徳帝を委ねる転換も効かないし、
碇を持っての入水にしてもカタルシスが弱くなると思う。
魁春の女房はまあまあ。
この場面よりも、正体を現した後の展侍の局の高貴な雰囲気の方が良かった。
ただ、仮御所の場面ってよく分からないんだよなあ。
知盛の苦戦を紹介する、というだけのような感じ。
また、大物浦で自死するあたりも理由や目的がよく分からなかった。
別に死ななくても、安徳帝を義経に委ねることはできたのでは、と感じてしまう。
これはテキストの問題。
歌昇が襲名披露ということで、
仮御所の場面の戦物語を見せる。
いかにも若々しく、溌剌として悪くなかった。
梅玉の義経は貴種流離譚の主人公らしい品位、
思慮の深さがあって良い。
歌六の弁慶は四天王の一人、という程度の雰囲気で、
役者不足かも知れない、と感じた。
次の日、改めて「渡海屋・大物浦」を見に来た。
吉右衛門の知盛が目当て。
明礬の人足の会話の後、
義経を追いかける「頼朝の家来」だという連中が「舟を出せ」と言ってくる。
そこに船問屋の主銀平が帰ってきて追い返す。
実はこれは、義経に銀平らが味方だと信頼させるための計略で、
その後銀平は知盛の正体を現す。
その後海沿いの仮御所で注進を受ける場面があり、
知盛の立ち回り、
最後は安徳帝を義経に託して碇を持って入水する。
吉右衛門は渡海屋の場面が良かった。
この場面、世話物の場面ではあるのだが、時代物のハラがベースに必要だと思う。
吉右衛門の銀平は基本的に糸に乗りつつ、
微妙に世話らしく崩すバランスが快い。
鎌倉方の侍に対し、商人っぽく下手に出る感じ、
逆に上から押さえる決め付け方、
このあたりの緩急の付け方が良かった。
それに比べると、立ち回りや恨みを持っての述懐はあまり良くないな。
安徳帝を委ねるあたりの改心の調子は良かった。
ただそれでも、渡海屋の素晴らしさに比べると不満。
身を隠してまで義経を討とうとした恨みや執念があまり感じられないせいかな。
ここが浅いと、後で安徳帝を委ねる転換も効かないし、
碇を持っての入水にしてもカタルシスが弱くなると思う。
魁春の女房はまあまあ。
この場面よりも、正体を現した後の展侍の局の高貴な雰囲気の方が良かった。
ただ、仮御所の場面ってよく分からないんだよなあ。
知盛の苦戦を紹介する、というだけのような感じ。
また、大物浦で自死するあたりも理由や目的がよく分からなかった。
別に死ななくても、安徳帝を義経に委ねることはできたのでは、と感じてしまう。
これはテキストの問題。
歌昇が襲名披露ということで、
仮御所の場面の戦物語を見せる。
いかにも若々しく、溌剌として悪くなかった。
梅玉の義経は貴種流離譚の主人公らしい品位、
思慮の深さがあって良い。
歌六の弁慶は四天王の一人、という程度の雰囲気で、
役者不足かも知れない、と感じた。