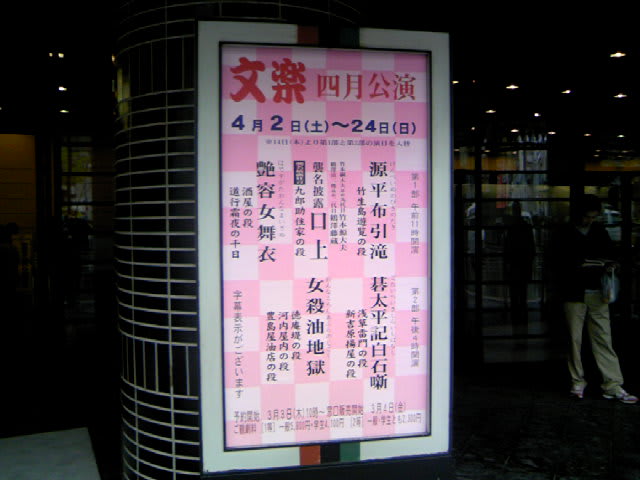先週末は、後輩が出演する芝居を見に、東下り。
それだけのために交通費を払うのも勿体ないので、
ついでに国立劇場のチケットを予約した。

真山青果の「元禄忠臣蔵」からいくつか。
確か「御浜御殿」だけ見たことがあったかな、という程度。
今回は吉右衛門とその一座メインで、梅玉や魁春が参加するような顔ぶれ。
JRの四ツ谷から歩いたが、30分はかからない。
丁度良い距離。
「江戸城の刃傷」
梅玉の浅野内匠頭。
まあ正直、どうってことはない芝居。
幕臣たちの「助けたい」と思う人々の考えや、
内匠頭が従容と切腹の場に臨むあたりは
良い感じであったが、
歌舞伎として、別に見所のあるものでもないと思う。
「御浜御殿綱豊卿」
最初の御殿遊びの場面。
女連中のうだうだは、まあ普通。
芝雀の中臈と魁春の江島が絡むのだが、
どうも芝雀が遠慮気味に見える。役の上、というより役者同士の関係で。
後の助右衛門引き入れ後はそうでもなかったのだが。
吉右衛門の綱豊卿が入ってくる。
様子、酔いの内に憂いの籠もった調子は流石。
ただ、(この場面に限らず)全体にどうも台詞が入っていないようで、
微妙な語尾の延ばし方、間が気になった。
新井勘解由(白石)への綱豊卿の問いかけ。
梅玉の新井勘解由は、以前見た左團次に比べると
「師」の落ち着き・重みが感じられた。
それでも綱豊卿の方が大きく見えてしまうのは、
役の上でやむを得ないのかな。
浪士である富森助右衛門を呼び込み、綱豊卿とやり取り。
助右衛門は又五郎。
呼び込まれる際の掛け合い、やり取りの調子など、
一本気なこの浪士の調子・雰囲気が出ていた。
声・姿など、この役に合う役者だと思う。
また、上手く吉右衛門と絡んで
お互いに調子良く進めていたと思う。
能舞台にかかる場面はごく普通。
ここ、何となく蛇足と感じてしまうんだよなあ。
「大石最後の一日」
この部分は初めて見た。
大石には「初一念」を貫き通す、がベースにある。
そこから
「義士として扱われているが、調子に乗ってはいけない、
身を清めて、死を淡々と受け入れるべき」
と考え、例えば最初の義士の会話や
細川の殿様が入ってくる際の受け入れ方に出てくる。
そんな「義理」で動く大石が、
若い男女2人を会わせて良いか、を考え、
人情を受け入れて会わせる、といったあたりが、この芝居の軸なのだろう。
錦之助の磯貝は若々しく、
前髪のこの役によく合っていたと思う。
まあ、何がどうって役でもなかろうが。
芝雀のおみの。
最初の出は「男装している」設定なんだが、
どうも最初から女性に見えてしまった。
後はまあ、普通。
特に良い、とも思えなかったが違和感はなく。
大石を説得するところは、もう少し芯の強い感じを出した方が良いかな。
磯貝の気持ちを聞いた後で、自刃するだけの覚悟を持っている訳だし。
おみのを引き合わせる、おみのの父の友人(歌六?)が
真面目な様子をきっちり描かれていて良かった。
「切腹の申し渡し」や「切腹の場に渡っていく様子」などの処理が
難しい芝居だと思う。
最後のおみのの自刃や「初一念」を通すことへの拘りを見せるために
必要な場面だとは思うが、
バランスとしては少し重い感じがする。
まあ、それは私がこの芝居の重心を
「おみのと磯貝」の絡みに掛け過ぎているためかも知れないが。
20時20分頃終演。
バスで渋谷に出た。
それだけのために交通費を払うのも勿体ないので、
ついでに国立劇場のチケットを予約した。

真山青果の「元禄忠臣蔵」からいくつか。
確か「御浜御殿」だけ見たことがあったかな、という程度。
今回は吉右衛門とその一座メインで、梅玉や魁春が参加するような顔ぶれ。
JRの四ツ谷から歩いたが、30分はかからない。
丁度良い距離。
「江戸城の刃傷」
梅玉の浅野内匠頭。
まあ正直、どうってことはない芝居。
幕臣たちの「助けたい」と思う人々の考えや、
内匠頭が従容と切腹の場に臨むあたりは
良い感じであったが、
歌舞伎として、別に見所のあるものでもないと思う。
「御浜御殿綱豊卿」
最初の御殿遊びの場面。
女連中のうだうだは、まあ普通。
芝雀の中臈と魁春の江島が絡むのだが、
どうも芝雀が遠慮気味に見える。役の上、というより役者同士の関係で。
後の助右衛門引き入れ後はそうでもなかったのだが。
吉右衛門の綱豊卿が入ってくる。
様子、酔いの内に憂いの籠もった調子は流石。
ただ、(この場面に限らず)全体にどうも台詞が入っていないようで、
微妙な語尾の延ばし方、間が気になった。
新井勘解由(白石)への綱豊卿の問いかけ。
梅玉の新井勘解由は、以前見た左團次に比べると
「師」の落ち着き・重みが感じられた。
それでも綱豊卿の方が大きく見えてしまうのは、
役の上でやむを得ないのかな。
浪士である富森助右衛門を呼び込み、綱豊卿とやり取り。
助右衛門は又五郎。
呼び込まれる際の掛け合い、やり取りの調子など、
一本気なこの浪士の調子・雰囲気が出ていた。
声・姿など、この役に合う役者だと思う。
また、上手く吉右衛門と絡んで
お互いに調子良く進めていたと思う。
能舞台にかかる場面はごく普通。
ここ、何となく蛇足と感じてしまうんだよなあ。
「大石最後の一日」
この部分は初めて見た。
大石には「初一念」を貫き通す、がベースにある。
そこから
「義士として扱われているが、調子に乗ってはいけない、
身を清めて、死を淡々と受け入れるべき」
と考え、例えば最初の義士の会話や
細川の殿様が入ってくる際の受け入れ方に出てくる。
そんな「義理」で動く大石が、
若い男女2人を会わせて良いか、を考え、
人情を受け入れて会わせる、といったあたりが、この芝居の軸なのだろう。
錦之助の磯貝は若々しく、
前髪のこの役によく合っていたと思う。
まあ、何がどうって役でもなかろうが。
芝雀のおみの。
最初の出は「男装している」設定なんだが、
どうも最初から女性に見えてしまった。
後はまあ、普通。
特に良い、とも思えなかったが違和感はなく。
大石を説得するところは、もう少し芯の強い感じを出した方が良いかな。
磯貝の気持ちを聞いた後で、自刃するだけの覚悟を持っている訳だし。
おみのを引き合わせる、おみのの父の友人(歌六?)が
真面目な様子をきっちり描かれていて良かった。
「切腹の申し渡し」や「切腹の場に渡っていく様子」などの処理が
難しい芝居だと思う。
最後のおみのの自刃や「初一念」を通すことへの拘りを見せるために
必要な場面だとは思うが、
バランスとしては少し重い感じがする。
まあ、それは私がこの芝居の重心を
「おみのと磯貝」の絡みに掛け過ぎているためかも知れないが。
20時20分頃終演。
バスで渋谷に出た。