「リーダーのためのコーチングがイチからわかる本」(あべき光司)読了。

※画像をクリックすると、「楽天」のページに飛びます
筆者は税理士で、「オーナー士業」を実践し、士業を育てるためのコンサルもやっている。
# 実は同学年で、同じ北摂出身だったりする。
「オーナー士業」というのは士業事務所を組織化し、
代表自身は実業務は減らし、可能な限り経営に専念する、という形。
この形でポイントになるのは、「いかに組織化するか」というところであり、
そのための重要なツールが「コーチング」である、ということになる。
私は実務が好きであり、また人を動かすことに苦手意識もあるので(自分でやったほうが早い病、なのだが)、
「オーナー士業」という形は少なくとも現時点では考えていないのだが、
元々「コーチング」に関心があったこともあり、
別の書籍の出版イベントで筆者の話を伺ったりしていた。
この本は、恐らく、コーチングを専門にされている方にとっては基本的なことなのだろうが、
自社やクライアントの「人」や「組織」を改善しようと考える者にとっては
俯瞰的にコーチングの意義と進め方の全体が捉えられ、良い「イチからわかる本」と感じた。
実際に始めてから、詳細の部分はより専門的な書籍で深掘りしていけば良いと思う。
印象的な部分、参考になった部分は多いのだが、
特に印象的だったのは
「上司が上から指示・命令するよりも、チーム全体で「問い」を共有するほうが組織の力が上がる」
という部分。
「「問い」を共有する」という表現が印象的で、
「理念」や「価値観」の共有はよく言われているのだが、ここで「問い」というのが興味深い。
「問い」を共有することで、皆が主体的・積極的に考え、それぞれの立場からの多様な意見が出てくる。
また、自発的に行動することに繋がる。
例えば、こんなことかな、と思った。
「お客様第一主義」という理念ではなく、
「何が今の状況では、私にとって、お客様第一主義の行動だろう?」という問いを共有する。
その「問い」を共有することで、「私は、今、○○と思う」という思いが出てくるし、
そのような行動に繋がる。
逆に「問い」が共有されていない組織だと、
「そんなこと、どうでもいいじゃない?」「私の普段の行動とは関係ない」になってしまう。
「経営理念」はあるし、皆唱和できるが、日々の行動で実践されていない。
そのような組織で「問い」を共有することは一つの方向性としてあり得ると思う。
また、そのやり取りの中でコーチングやその構成要素となるスキルは重要だろう、と改めて感じた。

※画像をクリックすると、「楽天」のページに飛びます
筆者は税理士で、「オーナー士業」を実践し、士業を育てるためのコンサルもやっている。
# 実は同学年で、同じ北摂出身だったりする。
「オーナー士業」というのは士業事務所を組織化し、
代表自身は実業務は減らし、可能な限り経営に専念する、という形。
この形でポイントになるのは、「いかに組織化するか」というところであり、
そのための重要なツールが「コーチング」である、ということになる。
私は実務が好きであり、また人を動かすことに苦手意識もあるので(自分でやったほうが早い病、なのだが)、
「オーナー士業」という形は少なくとも現時点では考えていないのだが、
元々「コーチング」に関心があったこともあり、
別の書籍の出版イベントで筆者の話を伺ったりしていた。
この本は、恐らく、コーチングを専門にされている方にとっては基本的なことなのだろうが、
自社やクライアントの「人」や「組織」を改善しようと考える者にとっては
俯瞰的にコーチングの意義と進め方の全体が捉えられ、良い「イチからわかる本」と感じた。
実際に始めてから、詳細の部分はより専門的な書籍で深掘りしていけば良いと思う。
印象的な部分、参考になった部分は多いのだが、
特に印象的だったのは
「上司が上から指示・命令するよりも、チーム全体で「問い」を共有するほうが組織の力が上がる」
という部分。
「「問い」を共有する」という表現が印象的で、
「理念」や「価値観」の共有はよく言われているのだが、ここで「問い」というのが興味深い。
「問い」を共有することで、皆が主体的・積極的に考え、それぞれの立場からの多様な意見が出てくる。
また、自発的に行動することに繋がる。
例えば、こんなことかな、と思った。
「お客様第一主義」という理念ではなく、
「何が今の状況では、私にとって、お客様第一主義の行動だろう?」という問いを共有する。
その「問い」を共有することで、「私は、今、○○と思う」という思いが出てくるし、
そのような行動に繋がる。
逆に「問い」が共有されていない組織だと、
「そんなこと、どうでもいいじゃない?」「私の普段の行動とは関係ない」になってしまう。
「経営理念」はあるし、皆唱和できるが、日々の行動で実践されていない。
そのような組織で「問い」を共有することは一つの方向性としてあり得ると思う。
また、そのやり取りの中でコーチングやその構成要素となるスキルは重要だろう、と改めて感じた。
















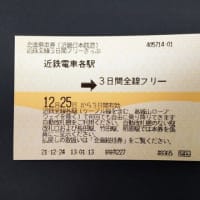
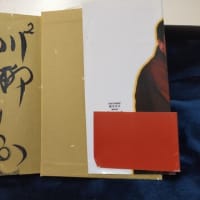

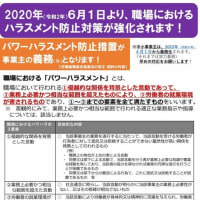







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます