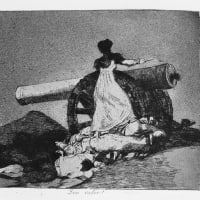NHKのBSでゴダールの『勝手にしやがれ』を観た。若い時に観たはずなのだが、印象がほとんど残っていない。いや初めて観たのだ、たぶん。記憶にあるシーンが、宣伝用のスチール写真そのものだ。わからん、老いぼれたな、俺は。
ストーリーは単純で、自動車を盗んだジャンポール・ベルモンドが、バイクで追ってきた警察官を拳銃で殺す。指名手配になるが、恋人未満(愛し合っているが、彼女の方はドライ)のジーン・セバーグと一緒に、パリの街なかを逃げまわるというもの。
美しいパリの都市景観をバックに、若い男女を配置したら、どんな映像が芸術として成立するか、ゴダールはそれだけを追求したかった・・。ゴダールを神様のように崇拝したかつての「俺」は、今となればそんな風にしか考えられない。
当時としては、60年代を先駆ける現代感覚にあふれた映画で、ヌーベルバーグの代表作といわれた。おしゃれ感とスピーディーな展開は、60年前の古くささを全く感じさせない。ただ、物語として深み、重量感はない。
警官を殺し、逃げ、撃たれて死ぬストーリーに、動機や必然性が捨象されている。カミュの『異邦人』のような、不条理感があるといえば、そんな雰囲気が漂う。主人公のやってることは、永山則夫を彷彿とさせないこともない。でも、社会的なテーマ性など微塵もない。
白黒映像の構図が美しく、シークエンスの流れが速くてポップだ。街中をふたりで闊歩するシーンでは、行き交う人々がふたりに視線を向ける、というよりカメラ目線となる。エキストラを使わずに、パリの雑踏の中にそのまま二人を放り込んだ演出。現代のユーチューバーが自撮りしたような映像が展開される(注)(具体的手法は後述)。
映画の筋とは関係ないが、ベルモンドが四六時中タバコをふかしていたこと、その煙がやたらとジーン・セバーグの顔や髪にふりそそぐのが気になってしょうがなかった。ニコチンの強い香りがたっぷりであろう、白い煙が美人の顔をつつむ。嫌な顔をまったく見せないで、女優はとーぜんの如く煙にまみれた顔を平気でさらす。時代が時代だったのだと、つくづくそう思う。
この違和感は間違いなく、タバコをやめた経験にもとづいた私の実感だ。それにしても、女たちも平気でタバコを吸っていた。セバーグ本人も煙草を吸うシーンもあったから、当時の喫煙はある種のファッションだった。
ベルモンドが、映画館に貼りだされたハンフリー・ボガードのポスターに見入り、お約束のように煙草に火をつける。場面が変わっても、煙草を口にくわえたまま新しい煙草に火をうつし、もくもくと煙を吐いている。吐き気がもよおすほどで、若いときの自分はこれをカッコいいと思っていた。
映画のポスターをネットで探したら、『勝手にしやがれ』の原題が、英語版では「BREATHLESS」だった。つまり「息を切らして」だ。主人公が四六時中タバコの煙が漂わせているのも、ストーリーの展開と相まって、観客は息がつまるような感覚になる。(追記:本国での原題は『À bout de souffle』であるが、意味はおなじく「息を切らして」としかいえない)
そもそも、なぜ『勝手にしやがれ』を見る気になったのか。トランプからバイデンへの政権移行の騒ぎのなかで、「勝手にしやがれ」のフレーズは、小生にとってけっこうインパクトあった。
「自由」の至上主義みたいなニュアンスの言葉であり、この時期としては、このコンセプトが気になってしょうがない。森本あんりの『不寛容論』を読むすすむなかで、アメリカの「自由」だけが何故か、ヨーロッパとは隔絶する、いや一線を画すような『勝手にしやがれ』を感じるのだ。
わるい癖だ、また迷宮に入り込む感じがある。いったん間をおくことにする。

『勝手にしやがれ』映画オリジナル予告編
(注)この映画がゴダールの初長編映画となる。監督・脚本はゴダールだが、原案はなんとフランソワ・トリュフォーだった。ヌーベルバーグの記念碑的作品であり、ウィキの解説によれば「時間の経過を無視して同じアングルのショットを繋ぎ合わせるジャンプカットという技法、手持ちカメラでの街頭撮影、高感度フィルムの利用、即興演出、隠し撮り、唐突なクローズアップ」などを用い、当時としては斬新な映画手法だったらしい。今となれば古色蒼然、ダサいのか、若い人から見れば・・。