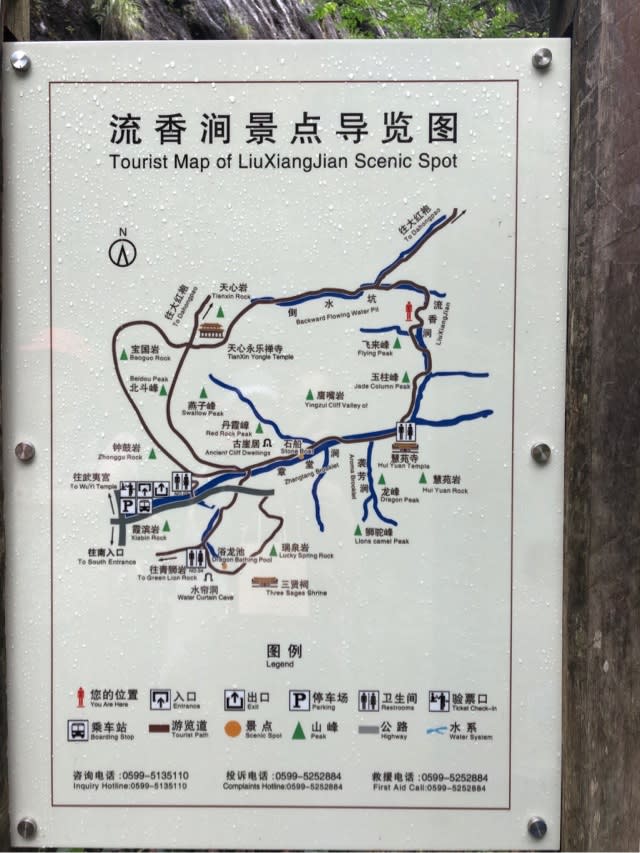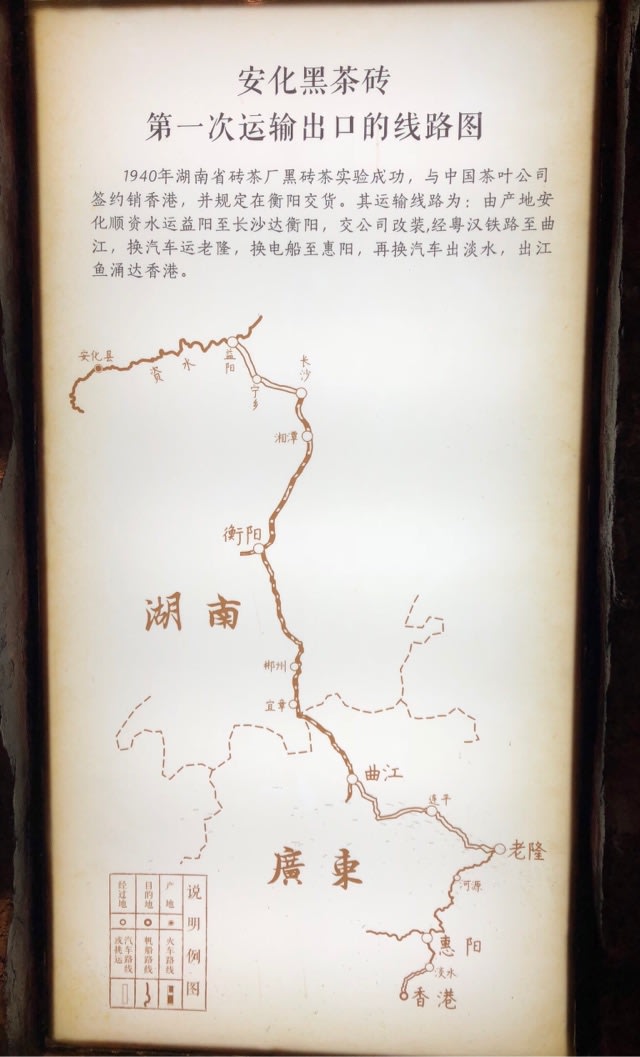武夷での製茶は
武夷岩茶の第一人者である人間国宝、王順明老師の琪明茶叶科学研究所に訪れました。

4年ぶりにお目にかかる王順明老師はお変わりなく、優しい笑顔が嬉しかったです。

今回の岩茶は不知春を製茶。
すでに工場の岩茶の製茶の時期は過ぎていましたが、私たちのために特別に茶摘みし、製茶して頂きました。

今年は3-4月に雨が多く成長が早かったため、全ての茶の茶摘みが早かったそうです。
茶摘みの時期は早生種や晩生種によってみ違いますが、一つに種類の茶摘み期間は二日間のみだそうです。

「立夏前三日は宝、立夏後三日は草」
と言われるほど、茶摘みの時期の大切さが分かります。

室外萎凋を終えて通常の室内萎凋は8-12時間ほどですが
今回のお茶は4時間。

王老師の義理の息子さんにご指導頂き
発酵を促す揺青を行いました。

最初は茶葉を落としてばかりでしたが
次第にコツをつかんで上手く揺すれるようになってきました。

求める発酵程度になったら300度の高温で10分ほど殺青を行い発酵を止めます。
燃料の木を燃やして高温にします。



殺青が終わったら茶葉を取り出します。
この方は工場長さんです。

次に揉捻機で5分ほど揉捻します。



揉捻が終わったら解塊。茶葉の塊をほぐします。


そして乾燥。途中上下を入れ替えながら90-100度で1時間。冷まして同じようにまた乾燥。水分量が17%なるまで何度か繰り返します。

琪明茶叶の出来上がった毛茶。
三ヶ月後の焙煎まで茶葉が平均に落ち着くよう寝かせられています。

袋の中の毛茶の様子。


我々の出来上がった毛茶です。
ここから茎などを取り除く抜茎をして
通常はこの50%が製品になりますが
今回は茶摘みの時期が遅かったので
20%のみ製品となります。
持ち帰り各々焙煎して
茶友との飲み比べが楽しみです。

夜は古岩正韻にて焙煎の工程を見学させて頂きました。
焙煎は伝統の焙煎方法で炭火焙煎。
60度、8-12時間したら一度冷まします。
これを2-3回繰り返します。軽い焙煎のお茶は1回のみ場合もあります。

途中上下をひっくり返し
時々試飲をして味を確かめます。

焙煎後の茶葉の温度は106度とかなり高くなっています。

茶葉を混ぜ返してまた籠に戻します。
武夷の岩茶は最後の工程のこの焙煎によって大きく味が変わるので、重要な工程であり、大変な作業であることを改めて実感しました。






















 t
t