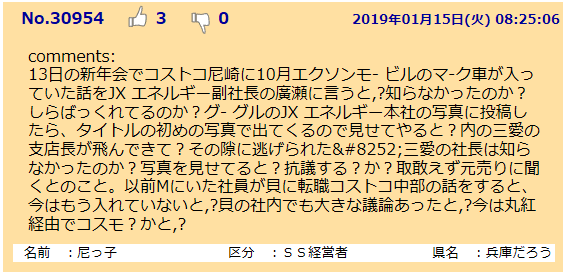これは20年前なら完全にアウト。
だけど・・・・・
今は?
もし一部の業者たちが独占しているようなら、今でもアウト。
ですが・・・・
ガソリンスタンドの減少が止まらず“、災害時の最後の砦”として地場業者のガソリンスタンドの数をこれ以上減らすことは社会インフラ崩壊の危機である今は・・・?
全ての業者での“順番制”だとしたら、場合によっては、今は大目に見る必要もあるのではないでしょうか?
(本当は全ての業者ではなく、ポリ容器1つ2つの小口配達を担っている地場業者と書きたいところですが、)
因みに当店は入札に参加したことがありません。
そもそも官公需は興味がない取引でしたし・・・
そして規制緩和以降は「近隣他店の売価が自店の仕入れ値」という状況でしたから、入札に参加することなどできるわけがありません。
***
2019年1月13日 18時49分
海上保安庁の巡視船などに使われる燃料の一般競争入札で、非公開の予定価格と全く同じ金額で落札される「100%落札」が相次いでいた問題で、海上保安庁は調査委員会を設置して実態の解明に乗り出しました。
海上保安庁の巡視船などの燃料に使われる重油や軽油の納入業者を決める一般競争入札をめぐっては、NHKが平成28年から29年にかけて行われた606件の入札を調べたところ、非公開の予定価格と全く同じ金額で落札される「100%落札」が、全体の51%にあたる307件に上っていたことが分かりました。
さらに「100%落札」が起きていた入札では、同じ顔ぶれの参加業者が、四半期や半期ごとに順番に落札するなど、あらかじめ落札業者を調整していた疑いがあることも分かりました。
これを受けて海上保安庁は、全国に11ある海上保安本部に「公正入札調査委員会」を設けて、実態の解明に乗り出しました。
調査委員会は海上保安本部の幹部らで構成し、今年度までの3年間に行われた一般競争入札を対象に事前に予定価格が外部に漏れることがなかったかや、事前に落札業者の調整が行われていなかったかなどについて、入札業務に携わる職員や参加業者から聞き取ることにしています。
海上保安庁では、ことし3月までに調査結果をまとめ、必要に応じて対策を講じることにしています。
各管区の状況は
平成28年から29年にかけて実施されたA重油と軽油の一般競争入札で、予定価格と落札価格が同じ「100%落札」が占める割合が大きかったのは、新潟県と石川県などを管轄する「第9管区」で90.6%でした。
次いで、
▽東北地方を管轄する「第2管区」で87.5%、
▽北海道を管轄する、「第1管区」で87.2%、
▽愛知県と三重県を管轄する「第4管区」で69%、
▽瀬戸内海を管轄する「第6管区」で62.1%、
▽熊本県や鹿児島県などを管轄する「第10管区」が58.1%、
▽近畿地方の一部と高知県などを管轄する「第5管区」が51.2%となり、いずれも半数以上を占めました。
一方、
▽九州北部と山口県を管轄する「第7管区」が1.4%、
▽沖縄県を管轄する「第11管区」が3.3%、
▽京都府と山陰地方などを管轄する「第8管区」が37%、
▽関東地方を管轄する「第3管区」が43.7%となっています。
あらかじめ落札業者が決まるケースも
「100%落札」が起きた入札の中には、あらかじめ落札業者が決まっていた疑いのあるケースがあることが分かりました。
NHKが入札結果を調べたところ、「100%落札」だった入札が行われた約90か所のうち、60か所余りでは、入札に参加する業者の顔ぶれが毎回全く同じで、半期または四半期ごとなどに順番に業者が落札している、もしくは、1社だけで落札しているケースがあることが分かりました。
この中には、入札に参加している4社が毎年、四半期ごとに順番に落札しているケースがありました。
100%落札となった入札に参加した東日本のある業者によりますと、複数の同業者と連携して落札業者を順番に決め、均等に落札できるように調整を行っていたということです。
この業者は「ほかの地域から入札に参加されてしまうと、価格が値崩れしてしまうので、地元の同業者だけで落札者を回して波風立てないほうがベターだ。お互いに商売の縄張りを侵さないことを考慮すればこの仕組みは必然ではないかと思う」と話しています。
一方で、この業者は、予定価格については、以前の落札価格や物価の動きなどを調べれば推測できるとしています。
海上保安庁 “100%落札”の謎を追う
2018年12月27日 20時09分
「小さな家業を存続させていく重みがのしかかる…」
ある港町で燃料販売業を営む業者から届いたはがきには、そう書かれていました。
この業者を取材したのは11月。海上保安庁の巡視船などに使う燃料をめぐる入札で、落札価格が、非公開の予定価格と全く同じになる、いわゆる「100%落札」が多発していることをつかみ、各地の港町を回りました。
そんな中で、少しずつ見えてきたのは業者間で長年続けられてきた“慣習”ともいえるシステムの存在でした。
(ネットワーク報道部記者 郡義之)
きっかけは…
「なんだこれ?」
ことし5月、私はパソコンの画面にくぎづけになっていました。
それは海上保安庁が発注した巡視船の燃料の調達に関する一般競争入札の結果が記された官報でした。国が発行する官報には、入札結果だけでなく、公布された法律や、中央官庁の人事異動など、あらゆる情報が掲載されています。
そこに書かれていたのが「落札率100%」という文字。それも1つだけではありません。あれも、これも、見る入札結果の多くが「落札率100%」でした。
通常、一般競争入札は、官庁が工事を発注したり、物品を購入したりする際に、予定価格を事前公表しない形で行い、最も低かった価格を示した業者が落札します。
つまり「落札率100%」とは、予定価格と落札価格が全く同じことを示していて、それがいくつもあるということは、極めて不自然な状況だと思いました。
「超能力者でもなければ、こんなに一致することもないのでは?」
半信半疑な思いも抱えつつ取材を始めたのです。
調べてみたら…
海上保安庁は、全国に約460隻の巡視船や巡視艇などを保有しています。それらの燃料として使われる軽油や重油などは、年間14万~15万キロリットル。その予算は、燃料単価の変動にもよりますが、この5年間を見ると100億円から160億円程度の間で推移しています。
燃料を調達するための入札は主に各港ごとに、全国に11ある海上保安本部を通じて行っています。
まず、ネット上で公開されている一つ一つの入札結果を読み込み、「100%落札」がどれだけあるか調べてみました。
その結果、平成28年から29年に行われた入札606件のうち、51%に当たる307件に上ることが分かりました。
東高西低
さらに「100%落札」だった300件余りを調べてみると、興味深い事実が見えてきました。
それは、東日本ほど「100%落札」の割合が多いということでした。
新潟県や北陸地方を管轄する「第9管区」で90.6%、東北地方を管轄する「第2管区」で87.5%、北海道を管轄する「第1管区」で87.2%などとなっています。これに対して、九州北部や山口県を管轄する「第7管区」は1%、沖縄県を管轄する「第11管区」は3%ほどでした。
ある業者の告白
落札率100%の入札は、一般的には、事前に発注側から予定価格が漏れたり、業者が談合するなどしなければできないと言われています。
そこで、この問題のポイントを整理してみました。
1は「なぜ落札率100%になるのか」、2は「談合は本当にないのか」です。
まず、全国の石油販売業者などを訪ね歩き、入札の実態を聞いてみることにしました。しかし、当事者である業者の口は重く、なかなか事情に迫る証言を得ることはできません。
そうした中、訪れた東日本にある港町で、石油販売業者の1人が思いがけず話し始めました。
「落札者はローテーションで決めている」
驚きました。公正なはずの入札を、業者間で調整して落札業者を決めていたと言うのです。
「先代、先々代の知恵。外から業者が来て入札に参加すると、値崩れを起こす。波風立てないためには、地元の業者で回した方がベターだ」
この業者によると、同じ地域の複数の会社で、半期ごとに均等に落札できるよう、話し合いで落札する業者を決めていたと言うことです。「長年の慣習」だといいます。
改めて入札調書を見てみると、いくつかの港で、入札の参加業者の顔ぶれが全く同じであることに気付きました。毎年、落札する時期と業者が全く変わっていない港もあったのです。
ただ、この業者は、なぜ100%で落札できるのかについては、「過去の落札結果や市場価格などから推測できる」と話すにとどめました。
100%の謎
しかし、事前に予定価格が公表されていないのに、百円単位までぴたりと当てることができるのか、謎は残ります。
そこで、訪ねたのが、入札制度に詳しい鈴木満弁護士です。
公正取引委員会の元調査官を務めた鈴木弁護士は、落札率が95%以上であれば、談合の可能性があるといいます。「落札率100%というのは、競争相手がいないことが分からなければ、この数字は出ない。予定価格が漏れている可能性もある」と指摘しました。
では、発注側の海上保安庁は、この入札をどうみるのか。
最も100%落札が多かった、新潟市に本部のある第9管区海上保安本部は「予定価格は、入札に参加する業者から見積もりを聞いたり、市場の調査を実施したり、今の契約金額を参考にしたりして最も低い価格を作成する。業者もそういうことは分かっているので、落札価格と同じになることはあり得る。予定価格よりも低い価格で入札されておらず、予定価格がぎりぎりの低い価格になっているので100%落札が多いと推測できる」などと説明しました。
東京・霞が関の海上保安庁は「過去の落札価格や、参考となる指標などを見れば、推測できる」と述べ、「入札は適正に行われている」との認識でした。
しかし、管区によって落札率に大きな違いがあることについては「分からない」。
そして「100%落札は確かに多い。今後何らかの分析をする必要がある」として、通常とは異なるという認識は示しました。
また、業者がローテーションで落札者を決めていたことについても「疑義があれば、ヒアリングする」と回答しました。
入札が形骸化?
今回、取材を通して感じたのは、入札自体が形骸化しているのではないかということです。
海上保安庁が言うように予定価格を“推測”できるとしても、複数の業者が参加する一般競争入札で1社だけが予定価格ぴったりに落札できるのは不自然。
予定価格を上回る価格で入札をすれば「失格」となるため、事実上、1社のみが入札に参加しているようなものです。予定価格以下で入札する業者がいれば落札率は100%を下回るからです。さらに各管区で落札率が大きく異なるのも謎です。
先述の鈴木弁護士も「燃料調達の原資は、国民の税金なので、納税者の立場から言えば、効率的に使ってほしい。だからこそ、一般競争入札のよさを引き出すために、入札参加者の範囲をより広げるなどの工夫は必要だ」と話します。
ただ、人口減少などで苦しい経営を強いられている燃料業者も少なくありません。仮に入札改革をして競争原理を活発化させるにしても、地元が多少でも優先されるような仕組みが実現できないものか。そんな複雑な思いを持ちながらも、引き続き取材を進めたいと思います。
*****
2015年8月、国は「中小企業者に対する国等の基本方針」(官公需方針)に「中小石油販売業者に対する配慮」の項目を追加しています。
が、
「最後の砦」への理解不足
正義と努力と(その2)
1月15日追記
st31掲示板より

>業転だって元売の品です。
製油所から出てくる無印のローリー
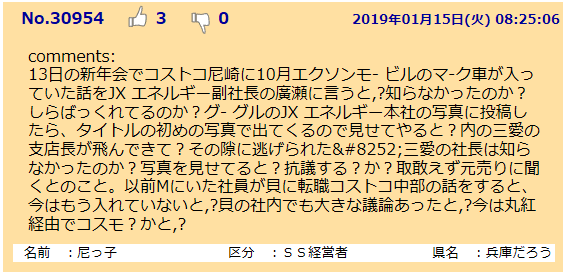
・・・
もしかして、
コストコへの供給も“元売間での順番制”ですか?
>全国の石油販売業者などを訪ね歩き、入札の実態を聞いてみることにしました。しかし、当事者である業者の口は重く、なかなか事情に迫る証言を得ることはできません。
やましいことがあるからですか?
過ちを認め、公にすることで、業界の未来は開かれ明るいものとなる。
私はそう信じています。