
みちとのそうぐ「う」→「う」ばすてやま。
姥捨て山伝説といえば、深沢七郎の『楢山節考』。
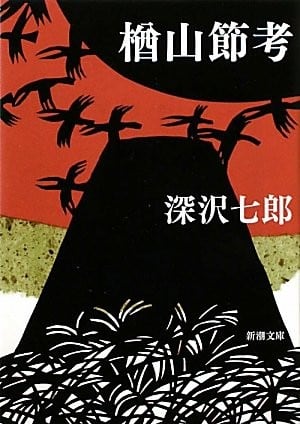
著者の代表作でしょうが、個人的にはこの単行本に収められている短編『月のアペニン山』が印象に残っていたり。
主人公の妻が静かに発狂するやつです。
それはともかく。
『楢山節考』は民間伝承の棄老伝説を素材にしているものの、あくまでも完全なるフィクション。
「そうしたことが実際にあったかどうか」ではなく、背負う子どもと背負われる母親の関係性がメインテーマとなっていて、なんともいえない読後感だったことを覚えてますね。読んだのは中学生だったかなぁ。。。
「背負う子どもと背負われる母親」という絵はひじょうにインパクトがあるため、「当然のように」2度映画化されていて、
有名なのはイマヘイによるカンヌ・パルムドール作(83)でしょう・・・
※驚いたなぁ、荻先生の解説つきで地上波もあったのか。左とん平のあの場面も流したのだろうか??
しかし原作に「より」忠実なのは、木下恵介版(58)のほうです。
イマヘイ版は、このひと特有の才気走った感じが作品を支配、たしかにクライマックスは衝撃だけれど、その直前まではひたすらセックスにまつわるアレヤコレヤが描かれるので「あれ、、、姥捨ては?」みたいな感じになっちゃうんだもの(^^;)
そもそもの話。
いや、これも嫌いじゃないですよ、
嫌いじゃないけれど、イマヘイにはほかに傑作が沢山あるにも関わらず、パルムドールに輝いた2作は(そう、『うなぎ』も)このひとの映画としてはクオリティ低めだと思うのですよね、
『楢山節考』とともにコンペに出品されていたのがオオシマの『戦場のメリークリスマス』であり、話題性からいって、パルムドールはオオシマのほうがよかったんじゃ?とさえ思います。
ただ面白いと思うのは、ここからの映画史と「親子の血」です。
イマヘイの息子さん「天願大介」(現・日本映画大学学長)も映画監督となり、2011年に小説『デンデラ』(佐藤友哉・著)を映画化、これまた主題が姥捨て山なのでした。
原作は深沢の名作を下敷きにしたものではなく、柳田国男の『遠野物語』を念頭に置いて紡がれたような物語で、どことなくパロディの趣きもあるサブカル小説として自分は解釈しました。

映画版ははっきりいって天願演出というより、浅丘ルリ子・草笛光子・倍賞美津子などによる熱演が最大の見どころ、、、ではあるのですが、
かなり「自覚して」この題材で撮るあたり、生粋の映画監督なんだなぁ!と思いますよね。
父親がそれ撮ったなら避けるひとも多いはずなのですよ、そこから逃げなかったところに天願大介のアイデンティティがあるような気さえしてきます^^
あすのしりとりは・・・
うばすてや「ま」→「ま」やく。
…………………………………………
明日のコラムは・・・
『シネマしりとり「薀蓄篇」(525)』
姥捨て山伝説といえば、深沢七郎の『楢山節考』。
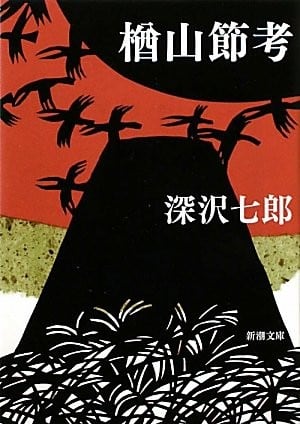
著者の代表作でしょうが、個人的にはこの単行本に収められている短編『月のアペニン山』が印象に残っていたり。
主人公の妻が静かに発狂するやつです。
それはともかく。
『楢山節考』は民間伝承の棄老伝説を素材にしているものの、あくまでも完全なるフィクション。
「そうしたことが実際にあったかどうか」ではなく、背負う子どもと背負われる母親の関係性がメインテーマとなっていて、なんともいえない読後感だったことを覚えてますね。読んだのは中学生だったかなぁ。。。
「背負う子どもと背負われる母親」という絵はひじょうにインパクトがあるため、「当然のように」2度映画化されていて、
有名なのはイマヘイによるカンヌ・パルムドール作(83)でしょう・・・
※驚いたなぁ、荻先生の解説つきで地上波もあったのか。左とん平のあの場面も流したのだろうか??
しかし原作に「より」忠実なのは、木下恵介版(58)のほうです。
イマヘイ版は、このひと特有の才気走った感じが作品を支配、たしかにクライマックスは衝撃だけれど、その直前まではひたすらセックスにまつわるアレヤコレヤが描かれるので「あれ、、、姥捨ては?」みたいな感じになっちゃうんだもの(^^;)
そもそもの話。
いや、これも嫌いじゃないですよ、
嫌いじゃないけれど、イマヘイにはほかに傑作が沢山あるにも関わらず、パルムドールに輝いた2作は(そう、『うなぎ』も)このひとの映画としてはクオリティ低めだと思うのですよね、
『楢山節考』とともにコンペに出品されていたのがオオシマの『戦場のメリークリスマス』であり、話題性からいって、パルムドールはオオシマのほうがよかったんじゃ?とさえ思います。
ただ面白いと思うのは、ここからの映画史と「親子の血」です。
イマヘイの息子さん「天願大介」(現・日本映画大学学長)も映画監督となり、2011年に小説『デンデラ』(佐藤友哉・著)を映画化、これまた主題が姥捨て山なのでした。
原作は深沢の名作を下敷きにしたものではなく、柳田国男の『遠野物語』を念頭に置いて紡がれたような物語で、どことなくパロディの趣きもあるサブカル小説として自分は解釈しました。

映画版ははっきりいって天願演出というより、浅丘ルリ子・草笛光子・倍賞美津子などによる熱演が最大の見どころ、、、ではあるのですが、
かなり「自覚して」この題材で撮るあたり、生粋の映画監督なんだなぁ!と思いますよね。
父親がそれ撮ったなら避けるひとも多いはずなのですよ、そこから逃げなかったところに天願大介のアイデンティティがあるような気さえしてきます^^
あすのしりとりは・・・
うばすてや「ま」→「ま」やく。
…………………………………………
明日のコラムは・・・
『シネマしりとり「薀蓄篇」(525)』



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます