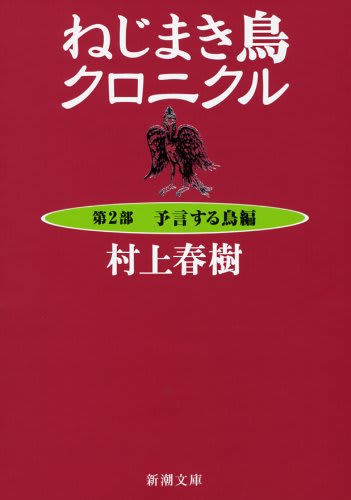1.序論
村上春樹は日本を代表する作家になった。そもそもがそれほどの作家なのかも私にはまだよくわからない。しかしおもしろい小説をたくさん書いているので、村上春樹の高い評価が固まっていくのではないかと期待できる。
その際、村上春樹のどういう点が評価されるのだろう。まだそれは明確になっていない。
村上春樹の評価が定まらない中で、教科書には載っている。しかし初期の短編がほとんどで、なんなのかよくわからない小説だらけなのだ。
「鏡」も教科書に載っている。しかしこれを教科書に載せる意味がよくわからない。村上春樹は日本を代表する作家であり、教科書に掲載することに妥当性を感じる一方で、どのように読むか指針がまるでない中で教材になることに疑問にも感じる。指導書を読んでもどのように授業で扱うべきか判然としない。そもそこ指導書の解説がきちんと読み取っているのかが疑問に感じるのだ。
今回「鏡」の読み方の一例を提示ししてみたい。
続く