ビーズアートショーの前後から、頭の中は、パールと天然石とメガネドメがぐるぐる回る生活。
結構いい感じで、色々な作品が出来上がってます。
今日も午前中は大急ぎで新作数点をアトリエのスタッフに渡し、午後からは渋谷へ・・・。
夕方、用事が終わったので、以前から気になっていた、渋谷西武でやっている、ハイメ・アジョンの世界展を覗いてきました。
ジャイメ・・・じゃなかった、ハイメ・アジョンというのはスペイン生まれのアーティスト・デザイナー。
-----
ハイメ・アジョン(Jaime Hayon)
世界を代表するデザイナーであり、リヤドロ、バカラのような一流ブランドとデザインに取り組む一方で、
昨年、Designtide Tokyo で発表した九谷焼の窯元、上出長右衛門窯との取り組みなど、その活躍の場は多岐に渡る。
(展覧会サイトより)
-----

ご本人。
結構かわいらしい方です。
プロフィールにもあるように、陶器、ガラス、家具など、デザインしているものは多岐に渡っているんだけど、
とにかく、線がイイ!キレイ!
はっとするデザインって、とにかく線が生きてるんだけど、
この人のデザインは、ものすごくシンプルに、逃げも隠れもできない中の線がイキイキしてる!
のびのびと、でも的確にひかれたラインの構成の中に、印象的な色彩。
特にスカイブルーでも無い、群青色でもない独自の青がいいなぁと思った。
* * * * *
実は渋谷西武の同じ7階には、最近私がとても気に入っている手芸材料SHOP、
サンイデー渋谷(100 IDEES)があるのだ!
渋谷に行くと必ず立ち寄っては、ビーズやら布地やら、リボンやら、ちょこまか買っちゃうお店。
そう。ちょうど今、このサンイデー池袋のアートブックショップ内で、beads cafe の作品の展示販売を行っていただいています。
かなりの量と種類を置いていただいているということなので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。
結構いい感じで、色々な作品が出来上がってます。
今日も午前中は大急ぎで新作数点をアトリエのスタッフに渡し、午後からは渋谷へ・・・。
夕方、用事が終わったので、以前から気になっていた、渋谷西武でやっている、ハイメ・アジョンの世界展を覗いてきました。
ジャイメ・・・じゃなかった、ハイメ・アジョンというのはスペイン生まれのアーティスト・デザイナー。
-----
ハイメ・アジョン(Jaime Hayon)
世界を代表するデザイナーであり、リヤドロ、バカラのような一流ブランドとデザインに取り組む一方で、
昨年、Designtide Tokyo で発表した九谷焼の窯元、上出長右衛門窯との取り組みなど、その活躍の場は多岐に渡る。
(展覧会サイトより)
-----

ご本人。
結構かわいらしい方です。

プロフィールにもあるように、陶器、ガラス、家具など、デザインしているものは多岐に渡っているんだけど、
とにかく、線がイイ!キレイ!
はっとするデザインって、とにかく線が生きてるんだけど、
この人のデザインは、ものすごくシンプルに、逃げも隠れもできない中の線がイキイキしてる!
のびのびと、でも的確にひかれたラインの構成の中に、印象的な色彩。
特にスカイブルーでも無い、群青色でもない独自の青がいいなぁと思った。
* * * * *
実は渋谷西武の同じ7階には、最近私がとても気に入っている手芸材料SHOP、
サンイデー渋谷(100 IDEES)があるのだ!
渋谷に行くと必ず立ち寄っては、ビーズやら布地やら、リボンやら、ちょこまか買っちゃうお店。
そう。ちょうど今、このサンイデー池袋のアートブックショップ内で、beads cafe の作品の展示販売を行っていただいています。
かなりの量と種類を置いていただいているということなので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。












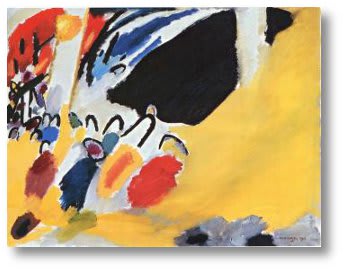 「印象 III(コンサート)」
「印象 III(コンサート)」 

 。
。 )
)
 そんな話は置いておいて、美幸さんの歌声。
そんな話は置いておいて、美幸さんの歌声。 それで、家の中の整理などもぼちぼちと・・・。
それで、家の中の整理などもぼちぼちと・・・。
 これは、モスグリーンの
これは、モスグリーンの シンプルなお猪口と浅鉢。
シンプルなお猪口と浅鉢。 そしてこれは、私専用のグラス。
そしてこれは、私専用のグラス。








 ■サンダーランド大学× BankART1929
■サンダーランド大学× BankART1929 ■J-LAF主催 日本・ベルギーレターアーツ展
■J-LAF主催 日本・ベルギーレターアーツ展

