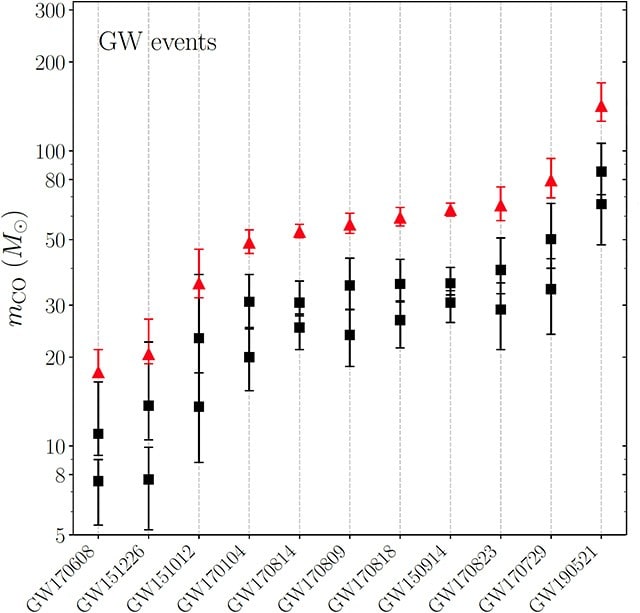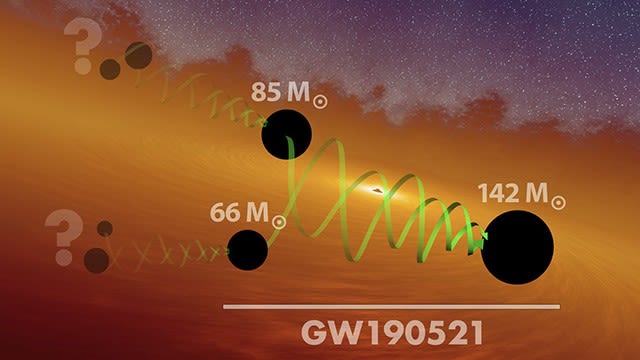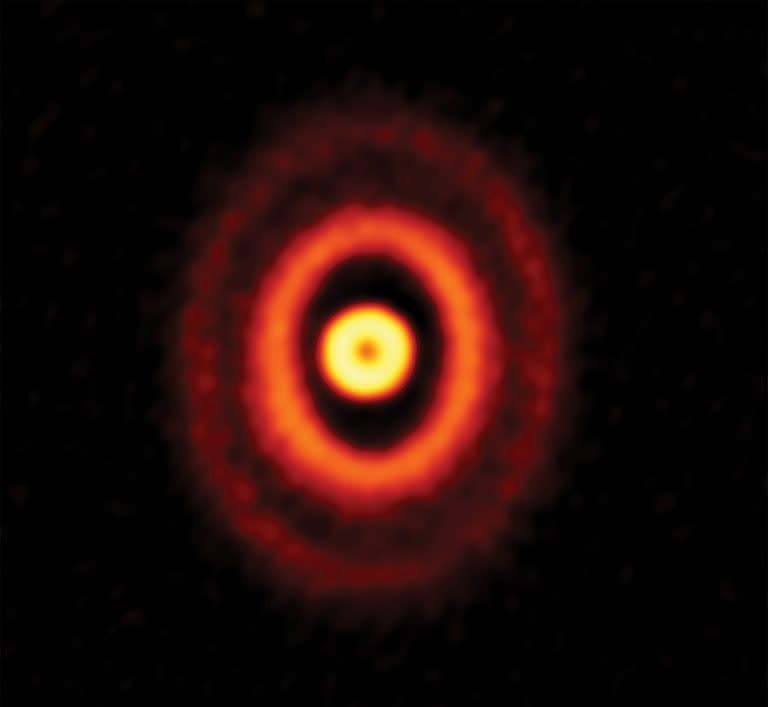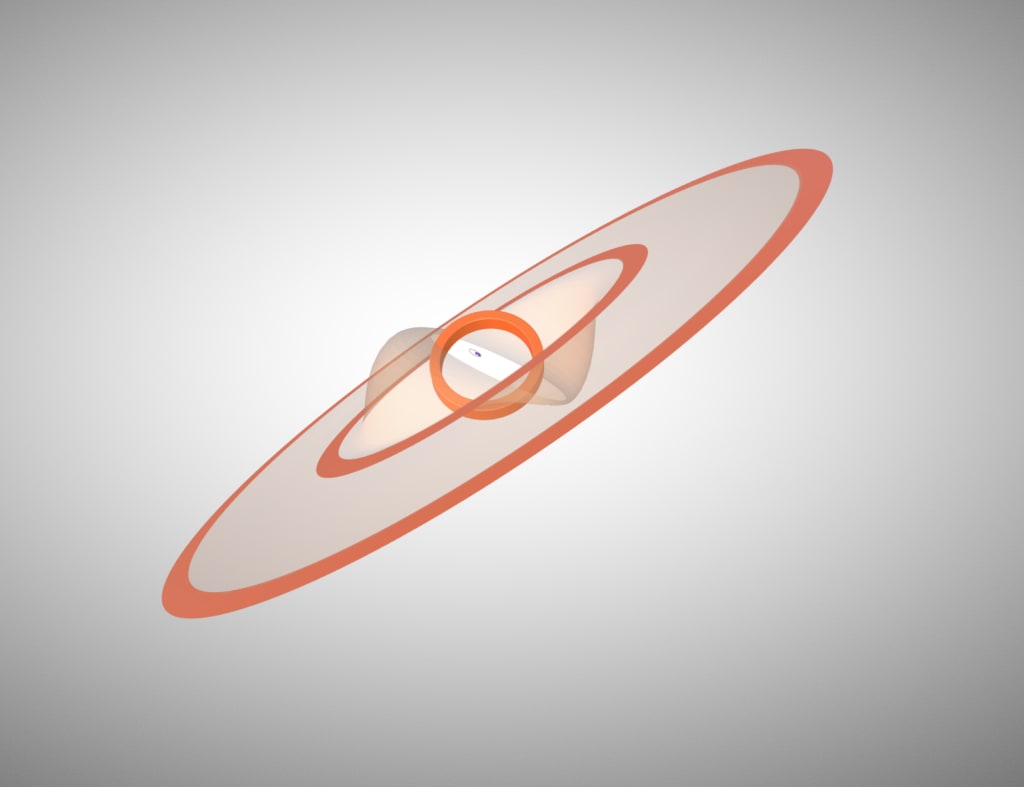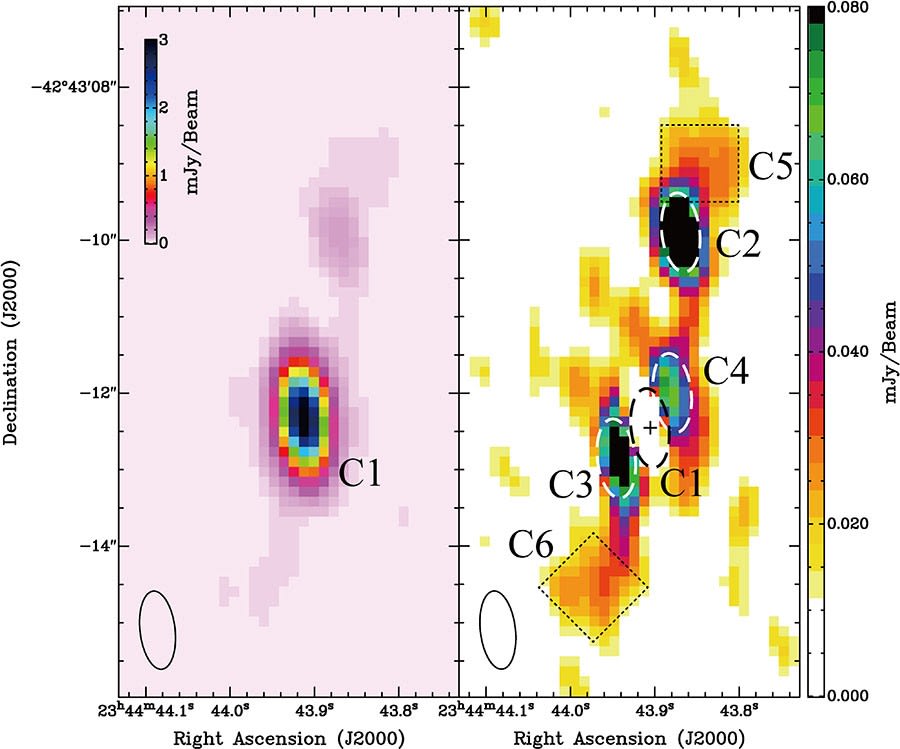アメリカの有人宇宙船というと民間宇宙企業のスペースX社が開発した“クルードラゴン”注目されがちですが、実は開発されている宇宙船はもうひとつあります。
それが、ボーイング社の新型宇宙船“スターライナー”です。
機体はスペースシャトルのような翼は持たず、アポロ宇宙船やスペースX社の“クルードラゴン”と同じカプセル型の宇宙船 。
NASAとボーイングは8月下旬、この“スターライナー”の有人飛行試験“CFT(Crew Flight Test)”を2021年6月に実施する予定だと明らかにしました。
“スターライナー”と“クルードラゴン”は、どちらもNASAの「民間企業による有人宇宙船の実用化を支援」計画のもとで開発された有人宇宙船です。
スペースX社は“クルードラゴン”の有人飛行試験“Demo-2”を今年の8月3日に終えていて、早くて今年の10月23日に最初の実運用ミッション“Crew-1”の実施を予定しています。
一方でボーイング社は、2019年12月に“スターライナー”の無人での軌道飛行試験“OFT(Orbital Flight Test)”を実施。
でも、当初予定していた軌道に入ることができず、機体は国際宇宙ステーションへのドッキングを断念して地球に帰還しています。
現在、ボーイング社とNASAでは無人で実施される2回目の軌道飛行試験“OFT-2”に向けた準備が進められています。
“OTF-2”の実施は“OTF”から1年後になる今年の12月に予定されています。
現在、ボーイング社では“OTF”のトラブルを受けて作成された改善勧告への対処を実施中。
NASAとボーイング社が共同で調査を実施し作成された改善勧告は80項目、このうちおよそ75%がすでに対策を終えています。
“CFT”は、この“OFT-2”の成功を受けて実施される飛行試験で、ボーイング社(元NASA)のクリストファー・ファーガソン宇宙飛行士、NASAのマイケル・フィンク宇宙飛行士及びニコール・マン宇宙飛行士の3名が搭乗する予定です。
ファーガソン飛行士は、2011年に実施されたスペースシャトル最後のミッションSTS-135でのコマンダー(船長)。
フィンク飛行士は、ひとつ前のSTS-134でミッションスペシャリストを務めています。
そして、マン飛行士は“CFT”が初の宇宙飛行になります。
来年6月に実施予定の“CFT”が成功すれば、半年後の2021年12月には“スターライナー”による最初の運用ミッション“Starliner-1”が予定されているそうですよ。
こちらの記事もどうぞ
それが、ボーイング社の新型宇宙船“スターライナー”です。
機体はスペースシャトルのような翼は持たず、アポロ宇宙船やスペースX社の“クルードラゴン”と同じカプセル型の宇宙船 。
NASAとボーイングは8月下旬、この“スターライナー”の有人飛行試験“CFT(Crew Flight Test)”を2021年6月に実施する予定だと明らかにしました。
“スターライナー”と“クルードラゴン”は、どちらもNASAの「民間企業による有人宇宙船の実用化を支援」計画のもとで開発された有人宇宙船です。
スペースX社は“クルードラゴン”の有人飛行試験“Demo-2”を今年の8月3日に終えていて、早くて今年の10月23日に最初の実運用ミッション“Crew-1”の実施を予定しています。
一方でボーイング社は、2019年12月に“スターライナー”の無人での軌道飛行試験“OFT(Orbital Flight Test)”を実施。
でも、当初予定していた軌道に入ることができず、機体は国際宇宙ステーションへのドッキングを断念して地球に帰還しています。
現在、ボーイング社とNASAでは無人で実施される2回目の軌道飛行試験“OFT-2”に向けた準備が進められています。
 |
| 2回目の軌道飛行試験“OFT-2”で使われる“スターライナー”のクルーモジュール。(Credit: Boeing) |
現在、ボーイング社では“OTF”のトラブルを受けて作成された改善勧告への対処を実施中。
NASAとボーイング社が共同で調査を実施し作成された改善勧告は80項目、このうちおよそ75%がすでに対策を終えています。
“CFT”は、この“OFT-2”の成功を受けて実施される飛行試験で、ボーイング社(元NASA)のクリストファー・ファーガソン宇宙飛行士、NASAのマイケル・フィンク宇宙飛行士及びニコール・マン宇宙飛行士の3名が搭乗する予定です。
 |
| 有人飛行試験“CFT”で“スターライナー”に登場する3名の宇宙飛行士。左からマン飛行士、フィンク飛行士、ファーガソン飛行士。(Credit: Boeing) |
フィンク飛行士は、ひとつ前のSTS-134でミッションスペシャリストを務めています。
そして、マン飛行士は“CFT”が初の宇宙飛行になります。
来年6月に実施予定の“CFT”が成功すれば、半年後の2021年12月には“スターライナー”による最初の運用ミッション“Starliner-1”が予定されているそうですよ。
こちらの記事もどうぞ