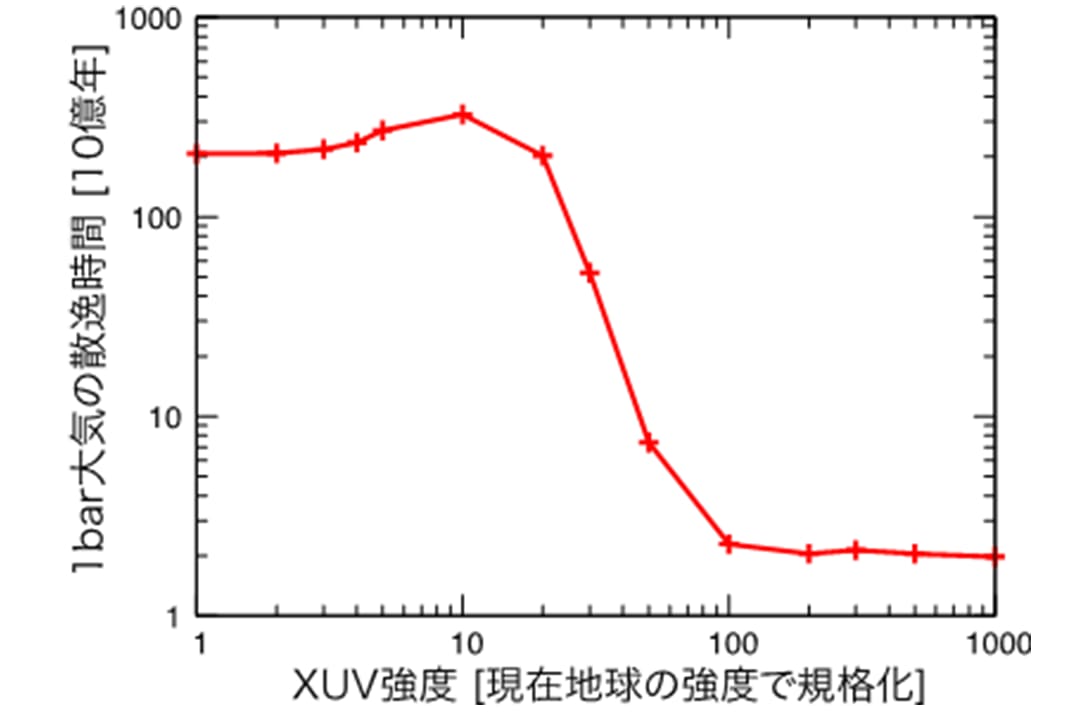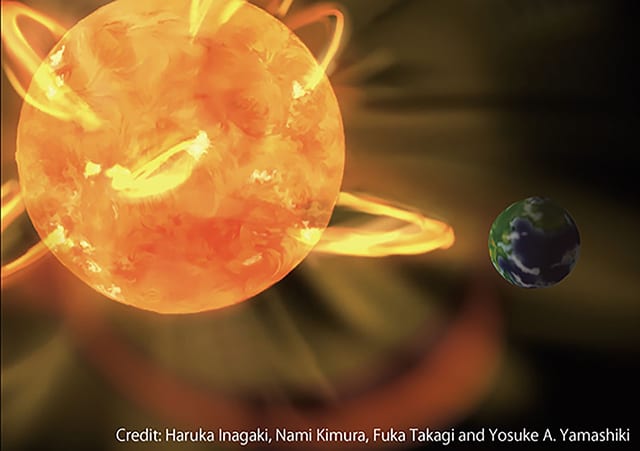恒星“ケプラー138”を公転する2つの系外惑星が、厚い水の層に覆われている可能性があるようです。
この2つの系外惑星は“ケプラー138”に近すぎるので表面の水は蒸発、高圧の深層では液体になっているのかもしれません。
私たちが知る地球の海とは全く違う環境のようです。
それは、太陽系の他の惑星と比べると、地球は広大な海という際立った特徴を持っているからです。
でも、水が地球全体の体積に占める割合は0.1%余り。
しかも、海の深さは平均で4キロ弱、一番深いところで10キロしかありません。
それでは宇宙のどこかに、もっと多くの水をたたえる惑星は存在しているのでしょうか?
太陽系外の惑星に注目する研究者たちが予測しているのは、体積の大部分が水で、深さ数百~数千キロの海に覆われた“海洋惑星(Water World, Ocean World)”の存在です。
こと座の方向約218光年彼方に位置する太陽より小さな恒星“ケプラー138”。
この恒星を公転する2つの惑星“ケプラー138c”と“ケプラー138d”は、まさにそうした海洋惑星かもしれません。
今回の研究では、NASAのハッブル宇宙望遠鏡と赤外線天文衛星“スピッツァー”で2つの惑星を観測し、それぞれの質量と体積を計算。
すると、“ケプラー138c”と“ケプラー138d”の質量はともに地球の約2倍であるのに対し、体積は3倍以上であることが分かりました。
この平均密度が低いことを説明するには、岩石の一部をもう少し軽い物質で置き換えればいいことになります。
そう、この軽い物質として一番有力なのが水になるんですねー
それは、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスなど、氷衛星と呼ばれる天体。
いずれの衛星も地球より密度が低く、岩石の中心核が厚い氷の層で覆われた構造をしていると考えられています。
大雑把に言えば、このような氷衛星をそのまま大きくして、中心星に近づければ、海洋惑星が出来上がります。
これまで私たちは、地球より少し大きな惑星は、金属と岩でできた球体だと考えていました。
それは、地球をそのまま大きくしたような天体なので“スーパーアース”と呼んできました。
ところが、今回の“ケプラー138c”と“ケプラー138d”は、スーパーアースとは性質が大きく異なり、体積のかなりの割合がおそらく水で構成されているようです。
このことは、天文学者たちが長きにわたって予測してきた海洋惑星というタイプの惑星が実在する。
っという、最も有力な証拠になるのかもしれません。
ただ、海洋惑星といっても、“ケプラー138c”と“ケプラー138d”の表面は、私たちが知る海とは全く違うはずです。
その理由は、どちらの惑星も中心星“ケプラー138”に近すぎて、温度が水の沸点を超えてしまうからです。
そのため、表面は厚い水蒸気の層で覆われていて、高い圧力がかかる深層の水は液体、または高温高圧下で気体と液体両方の性質を示す超臨界流体になっていると考えられます。
なので、“ケプラー138c”も“ケプラー138d”も海洋惑星かもしれませんが、その海に生命が存在できる可能性は低そうです。
その一方で、今回の研究では“ケプラー138”に生命の居場所が残っている可能性も示しています。
それは、4つ目の惑星“ケプラー138e”の発見にありました。
この惑星について得られているデータは少なく、分かっているのは比較的小さく、他の3つの惑星よりも中心星から遠く、38日かけて中心星を公転していること。
中心星の温度を考慮すると、この距離なら表面に液体の水が存在できるはずです。
もしかすると、“ケプラー138e”こそ、地球と同じ意味で「水の惑星」になっているのかもしれません。
こちらの記事もどうぞ
この2つの系外惑星は“ケプラー138”に近すぎるので表面の水は蒸発、高圧の深層では液体になっているのかもしれません。
私たちが知る地球の海とは全く違う環境のようです。
体積の大部分が水で構成された惑星は存在するのか
地球はよく「水の惑星」と呼ばれます。それは、太陽系の他の惑星と比べると、地球は広大な海という際立った特徴を持っているからです。
でも、水が地球全体の体積に占める割合は0.1%余り。
しかも、海の深さは平均で4キロ弱、一番深いところで10キロしかありません。
それでは宇宙のどこかに、もっと多くの水をたたえる惑星は存在しているのでしょうか?
太陽系外の惑星に注目する研究者たちが予測しているのは、体積の大部分が水で、深さ数百~数千キロの海に覆われた“海洋惑星(Water World, Ocean World)”の存在です。
こと座の方向約218光年彼方に位置する太陽より小さな恒星“ケプラー138”。
この恒星を公転する2つの惑星“ケプラー138c”と“ケプラー138d”は、まさにそうした海洋惑星かもしれません。
 |
| 赤色矮星“ケプラー138”を公転する3つの惑星(イメージ図)。右手前の“ケプラー138d”と恒星の左下に描かれた“ケプラー138c”は海洋惑星の候補。中心星を通過するシルエットは“ケプラー138b”。(Credit: NASA, ESA, and Leah Hustak (STScI)) |
すると、“ケプラー138c”と“ケプラー138d”の質量はともに地球の約2倍であるのに対し、体積は3倍以上であることが分かりました。
今回の研究を進めているのは、カナダ・モントリオール大学のCaroline Piauletさんたちの研究チームです。
つまり、岩石惑星である地球と比べて、“ケプラー138c”と“ケプラー138d”は平均密度が低いことになります。この平均密度が低いことを説明するには、岩石の一部をもう少し軽い物質で置き換えればいいことになります。
そう、この軽い物質として一番有力なのが水になるんですねー
“ケプラー138”または“KOI-314”は、地球から見て“こと座”の方向約219光年彼方に位置する赤色矮星。2022年12月時点で、周囲に3つの系外惑星が存在していることが知られていて、さらに低質量の惑星候補の存在が示されている。
中心星に近すぎる海洋惑星
実は、もっと小さなものにも注目すれば、こうした天体は太陽系にも存在しています。それは、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスなど、氷衛星と呼ばれる天体。
いずれの衛星も地球より密度が低く、岩石の中心核が厚い氷の層で覆われた構造をしていると考えられています。
大雑把に言えば、このような氷衛星をそのまま大きくして、中心星に近づければ、海洋惑星が出来上がります。
これまで私たちは、地球より少し大きな惑星は、金属と岩でできた球体だと考えていました。
それは、地球をそのまま大きくしたような天体なので“スーパーアース”と呼んできました。
ところが、今回の“ケプラー138c”と“ケプラー138d”は、スーパーアースとは性質が大きく異なり、体積のかなりの割合がおそらく水で構成されているようです。
このことは、天文学者たちが長きにわたって予測してきた海洋惑星というタイプの惑星が実在する。
っという、最も有力な証拠になるのかもしれません。
ただ、海洋惑星といっても、“ケプラー138c”と“ケプラー138d”の表面は、私たちが知る海とは全く違うはずです。
その理由は、どちらの惑星も中心星“ケプラー138”に近すぎて、温度が水の沸点を超えてしまうからです。
そのため、表面は厚い水蒸気の層で覆われていて、高い圧力がかかる深層の水は液体、または高温高圧下で気体と液体両方の性質を示す超臨界流体になっていると考えられます。
 |
| 地球と“ケプラー138d”の内部。“ケプラー138d”には体積の50%以上を占める水の層があり、その深さは約2000キロに及ぶかもしれない。(Credit: Benoit Gougeon (University of Montreal) |
その一方で、今回の研究では“ケプラー138”に生命の居場所が残っている可能性も示しています。
それは、4つ目の惑星“ケプラー138e”の発見にありました。
この惑星について得られているデータは少なく、分かっているのは比較的小さく、他の3つの惑星よりも中心星から遠く、38日かけて中心星を公転していること。
中心星の温度を考慮すると、この距離なら表面に液体の水が存在できるはずです。
もしかすると、“ケプラー138e”こそ、地球と同じ意味で「水の惑星」になっているのかもしれません。
| 今回の研究成果の紹介動画“Two Exoplanets May Be Water Worlds”(Credit: NASA Goddard Space Flight Center, Lead Producer: Paul Morris) |
こちらの記事もどうぞ