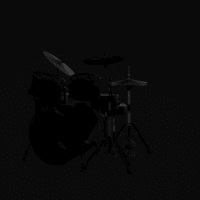今日2月14日は、“ローリング・ストーンズの日”だということです。
1990年のこの日、ストーンズが初めて来日し、東京ドームでコンサートを行いました。それにちなんで、ローリング・ストーンズの日ということになっているのです。
奇しくも2月には“ビートルズの日”もあって、このブログではそれに合わせてビートルズの記事を書きました。ビートルズだけだとバランスが悪いので、今日はストーンズについての記事も書いておこうと思います。
種本として、前回テンプターズの記事でも紹介した『ストーンズ・ジェネレーション』を参考にしたいんですが……
まず問題になるのは、この『ストーンズジェネレーション』というタイトルです。
渋谷陽一さんは、ビートルズジェネレーションなど存在しないと論じていました。
日本にはビートルズを聞いて育った世代などどこにも存在しない――と。
渋谷さんのいうようにビートルズジェネレーションが存在しないのなら、ストーンズジェネレーションはなお存在しないでしょう。
この本にはミュージシャンや音楽関係者のほか、村上龍さんといった作家なども登場しますが、彼らが口をそろえるのは、ビートルズに比べてストーンズ人気はだいぶ劣っていたということです。
まあ、それが実際のところなんでしょう。
もちろん海外ではそんなことはなく、ライブをやれば何十万人という人を集めていたわけで、『ストーンズジェネレーション』にもうそういったライブのレポートが載っています。
しかし、私なんかは、どうもそこにある種のそらぞらさを感じてしまいます。
巨大なスタジアム数十万人の観客を集めてのライブというその狂騒に、どこか虚構性を感じてしまうのです。
それは、ミック・ジャガーという人についてまわる、“計算高い商売人”というイメージによるものかもしれません。その商魂によって形成されたローリング・ストーンズという虚像が、ここまで肥大化したのか……という。
そこへいくと、むしろ日本でこそストーンズは周辺的な存在だったのではないかと思えます。
ごく一部の人間が聴くものでしかなかったために、その周縁性が際立つ……そういうところが、日本ではあったんじゃないでしょうか。
もともとは、イギリスやアメリカでもそうであったはずなのです。
ロックンロールなどというのは、大人たちに忌み嫌われ、悪ガキが夜中のラジオでひっそりと聴いているものだった。
ところが、その周縁的存在であるはずのものが、いつしかそうでなくなってしまう。周縁的であるからこそ支持されていたものが、文化の中心になってしまう。それは、単にストーンズという一アーティストだけでなく、ロックやパンクが常に抱えていた矛盾でもあるわけです。ここに、長年のファンがストーンズに接するとき複雑な距離感が生じる原因があるんじゃないでしょうか。
そういう観点で『ストーンズ・ジェネレーション』を読んでいて、じつに興味深いのは、ストーンズ来日に関する部分です。
一応背景的なことを書いておくと、この本が出された1980年代半ば、ストーンズはまだ一度も来日を果たしていませんでした。
その十数年前に来日の話があって、コンサートのチケットまで発売されていたんですが、土壇場になってメンバーの逮捕歴の問題で立ち消えになった……という経緯があります。
冒頭に書いたとおり、来日公演は1990年に実現するわけですが、それまでには来日公演をめぐるさまざまな動きがあったのです。
そういう状況だったので、『ストーンズ・ジェネレーション』では、インタビューのなかでストーンズに来日してほしいと思うかということを聞いてるんですが……おもしろいことに、そう問われた人たちのほとんどが否定的な答えを返しています。
たとえば、内田裕也。
希望からいうと、来てほしくないっていう気持ちが半分くらいあるのね。日本人っていうのは寄ってたかってすぐコケにする民族だからさ、いいもの見ると“あれはタコだ”とかさ(笑)。
あるいは、当時ファンクラブの会長をしていた池田祐司さんも、「個人的には来てほしくない」といっています。その理由は、「もう誰にも見せたくない(笑)。自分だけのものにしておきたい」から。
さらには、ファンクラブの二代目会長である越谷政義さんも、歴代会長を集めた座談会のなかで「本当言うとあまり来て欲しくないね」といっています。
ちょっと恐いというのもあるしね。ディランの場合がそうだったじゃない? 来てから淋しくなっちゃったとかさ。
この座談会には、先に名前が出てきた池田さんも参加していて、先々代にあたる越谷さんの言葉に対して池田さんはこう答えています。
ディランやチャック・ベリーの場合は来るまでに既にダメになってたと思うんだよね。テンションが落ちてたというかね。
…(中略)…
僕もストーンズは3、4回観てるし、別に来なくてもいいやとも思うけどね。ただストーンズが来て日本でどうなるかを見てみたいっていうのはある。日本のジャーナリズムが全てダメかどうかってのを確かめる1つの試金石のような感じがするな。ストーンズがいい演奏しても、ジャーナリズムってのは“やっぱり大したことなかったよ”と書きそうな気もするしさ。
最後に、われらが忌野清志郎。
この本にはキヨシローへのインタビューも掲載されていて、ストーンズ来日について問われたキヨシローは、きっぱり「来ないほうがいいですね」といっています。
その理由を問われたキヨシローは、もう一度「いやー……やっぱり来ないほうがいいですね(笑)。」と答え、さらに重ねて問われた後でこう答えます。
…………みんなが、乗っちゃいけない車ってあるでしょう? 本当に好きな人だけが乗るっていう……。
さすがキヨシローのセンスで、この言葉がストーンズファンの本心をずばり突いているんじゃないかと思えます。
文中の…の数はそれだけの沈黙があったことを表していると思うんですが、この沈黙や、(笑)といったところも含めて、それがストーンズファンの微妙な距離感だと思われるのです。
「笑っていいとも」にでも出られたら、たまったもんじゃない(笑)
とも言ってますが、つまりはそういうことでしょう。
これは80年代以前ぐらいの洋楽全般についていえることだと思うんですが、そのころの海外アーティストは、そうそう日本には来なかったし、その結果としてメディアへの露出もそう多くはなかった。そのことが、海外アーティストをある種神秘のベールで包み、神格化させる作用があったといわれています。
逆に、80年代ぐらいを境にして日本円のパワーが強くなり、海外アーティストが気軽に来日するようになる。さらにMTVなんかの発達もあって、彼らの存在がお茶の間で身近に感じられるようになると、その“神格化”作用が薄らぎ、日本人の洋楽離れを促したという見方もあるのです。
「ちょっと恐いというのもある」と池田さんはいってましたが、彼らが恐れていたのは、そういうことでしょう。
「笑っていいとも」に出てタモリにいじられる――自分達が崇める“神”のそんな姿を見たくはないわけです。
ここで、以上引用してきた言葉を私なりにまとめて解釈すると……
おそらく、ストーンズが実際に来日すると、メディアがあまり好意的な扱いをしないであろうことが、彼らにはうすうすわかっている。というよりも、かなりの高確率でそうなるだろうと思われる。そして、そうなることで、自分のなかにある“ストーンズ幻想”に傷をつけられることを彼らは恐れているのではないか……そんな気がします。
先に引用した人たちの発言には、しばしば(笑)がついていますが、「このカッコ笑い」のなかに、消化しきれない内なる葛藤めいたものが溶け込んでいるようにも感じられるのです。痛い腹をさぐられたときのごまかし笑いのような……
『ストーンズジェネレーション』には、当時東芝EMIでディレクターをやっていた三好伸一さんの文章が載っているんですが、この方は、「アメリカ公演は最悪だった」といっています。そのとき印象的だった光景として、隣にいた18歳ぐらいのアベックのことを書いています。
18歳くらいのカップルが座るなり、羊皮かなんかの水筒に入ってるアルコールかなんかをガバーッと飲んで、ガンジャをガンガンに吸うわけ。次にコークをスーッと吸うわけ(笑)。始まって2曲目くらいで“ボーリング”なんて言って帰っちゃったんだよね。僕は、半分それがわかったような気がした。なにかそういう感じを受けた。
日本のストーンズファンが恐れたのは、まさにこれだと思うんです。
“ボーリング”というのは、boring ――すなわち、退屈とかつまらないということでしょう。「王様は裸だ」といわれてしまうことが、怖かったんじゃないでしょうか。
ここで問題になるのは、本当に王様は裸なのかということです。
つまり、ストーンズなんて本当はまったく中身がないのに、その名前だけが売れてしまっている裸の王様にすぎないのか。
あるいは、件のアベックの趣味があわなかっただけなのか――
そこはもう、個人の好みとしか言いようがない部分ではありますが、先の三好さんは、ストーンズが悪いわけではなくて、アメリカのオーディエンス全体がそういう雰囲気を作っていたということをいっています。実際、イギリス公演ではそんなことはなかった、と。
ただ、ストーンズが実体を超えて肥大化してしまっているという部分は否定できないと私個人は思います。
それはたぶん、ストーンズファンの人もある程度同意するんじゃないでしょうか。
ここで、以前紹介した『ロックミュージック進化論』から、渋谷陽一さんがストーンズについて論じた箇所を引用しましょう。
ストーンズを褒めるやつに会うと何となくちゃちゃを入れたくなるし、ストーンズをけなすやつに会うとぶん殴りたくなるし、非常に元ビートルズ派の私としては、複雑な心境なんですけれども。安易な批判も絶対許したくないけれども、やはり不気味だよね、あの東京ドーム。あんなにたくさんの人が入るという、日本で売れているレコードの何倍もの人がなぜか来ちゃうという。
ここで言っている「あの東京ドーム」というのは、もちろん1990年の初来日公演のことです。
実際やってみると、やっぱり多くの人がストーンズのライブに詰めかけました。
こういった現象に関して渋谷さんは「すごい巨大化したシンボルとして機能せざるを得ないというか、僕を含めてそういう幻想を何が何でもストーンズにおっかぶせてしまう。今ロックのシンボルがないからね」といっています。
これはやはり、渋谷さんがビートルズに関してもいっていた“欠落”の論理で、その欠落のゆえにストーンズの存在が肥大化してしまっているということでしょう。
では、その肥大化した部分を捨象した、ストーンズの実態はどうなのか。
これはやはり、先にいったように、もう個々のリスナーの好みの問題です。
……というわけで、最後にストーンズの動画を。
まずは、キヨシローもインタビューで曲名を挙げていた「黒くぬれ!」
The Rolling Stones - Paint It Black - Live OFFICIAL (Chapter 4/5)
これはもう巨大ステージということになるわけですが、次のような動画もありました。
Muddy Waters & The Rolling Stones - Baby Please Don't Go - Live At Checkerboard Lounge
ローリング・ストーンズのバンド名の由来である Rollin' Stone を歌ったシカゴブルースの巨人、マディ・ウォーターズとのコラボ。
最初は客席で飲んでいたストーンズの面々が、マディ・ウォーターズに呼ばれて一人一人ステージに上がっていくという趣向です。
こういう等身大のステージにこそ、虚飾ぬきのストーンズが見られるんじゃないでしょうか。