あいちトリエンナーレの企画展“表現の不自由展・その後”が話題になっています。
脅迫による中止からの再開、文化庁からの補助金不交付、そして市長の“座り込み”……
今回は、この一連の騒動について、思うところを書いてみようと思います。
ただし、個別の作品については、あれこれいいません。
私はそれらを自分の目で見ていないので、何もいえないのです。
私がこれまでこの件についてこのブログで何も書いてこなかったのも、ひとえにそのためです。
この件について、ツイッターなどでは、激しいやりとりが交わされたりもしていますが……そのなかには、伝聞情報にもとづくものも少なくないようです。不正確だったり、一部だけを切り取った情報に基づいた言説に対し、それを指摘する書き込みなども多く見られます。
展示内容を批判するのは無論自由ですが、批判する人も、せめて作品を自分の目で見てからにするべきではないかと私は思ってます。
かくいう私も、実際の展示を見てはいないわけなので……この記事で、個別の作品の解釈などについては書きません。
あくまでも、今回のような問題について一般論としての感想を述べるにとどめたいと思います。
一応、表現者という立場にある人間として、この件について一言いっておかなければならないのではないかと考えたので……
まず、公金を受けていることによって内容が制限されるというのは、あってはならないことだと思います。
展示内容になんらかの問題があって(たとえば差別的であるとか、個人のプライバシーを侵害しているとか)これはよくないということはありうるでしょうが、公的な援助を受けているということがその判断に影響を与えるべきではないでしょう。そのようなことをしていれば、否応なしに権力に近いかどうかが判断の基準になってくることは避けられません。
また、展示作品がある人に不快感を与えるものであったとしても、それ自体は問題ではないと考えます。
“芸術”と呼ばれるものは、なにも心地よさだけを与えなければならないわけではないでしょう。
音楽でも文学でも映画でもそうだと思いますが、ときには不快感を催すような手法をあえて使うこともあります。
そして、時代性がそこにからんでくるときには、思わず目をそむけたくなるような表現を突きつけてくることもあるでしょう。
たとえば、昨日の記事でも名前が出てきたバンクシーはどうか。
バンクシーの作品は、風刺的な意味合いを持つものが多いといわれます。それらはおそらく、風刺の対象となった人たちからすれば不快なものでしょう。
彼の作品は、多数の人が気づかずにいる――あるいは、気づいていても見ないふりをしている――問題を突きつけてきます。
“芸術”と“政治性”という問題では、よくピカソのゲルニカの例が出されますが……
ピカソがゲルニカを描いたときに、官憲がピカソのところにやってきて「この絵を描いたのはお前か」と尋ねたところ、ピカソは「いや、あなたたちだ」といったという逸話があります。
この皮肉のきいた返答には、すぐれたアートは媒介であるということが示されています。
制作者は、ある意味では媒介に過ぎない。どうしてそういう作品がいまそこに存在しているのか。そのことを考えさせられるのが、芸術作品と呼ばれるものの一つの意味ではないでしょうか。
ゲルニカに関しては、アメリカがイラク戦争にむけて国連で演説をする際に、幕であの絵を覆い隠したという話があります。今から戦争をはじめようというときに、戦争の惨禍を描いた絵なんかけしからんというわけですが……こんなふうに、周囲がその作品に対してどういうアクションを示すかということも含めてアートということなんでしょう。
その意味では、今回の騒動は、いまの日本社会を鮮やかに映し出しているのだと思います。










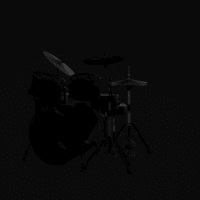









そして、我が家では表現の不自由展への評価は「カネ出して見る程のものか?」で一致(ちなみに、当方も、母上も、別々の流派の画家から絵を習っていました)。
制作者の自己満足で終わるものは、芸術ではない。只のゴミです。
ゴミ箱をいくら擁護したところで、芸術も表現の自由も擁護できない。勿論、適正手続も。
作品の内容と、展示会運営における手続きの瑕疵とは、まったく関係ない別の問題のはずです。それが並べて論じられていることに違和感をおぼえずにいられません。
(いや、違和感というか、むしろ「ああ、やっぱりそうなんだな」という納得感なんですが……)
展示を見た人がそれをゴミと評するのはまったく自由ですし、「手続き面で問題があるから資金を出さない」というのは、ああ、そうなんですね、としかいいようがありませんが、この二つが水面下でつながっているのだとしたら、それには非常に問題があるでしょう。
つまり実際は、「作品の内容が気に食わない」→「でも、直接そのことで負担金を停止するのは問題がある」→「よし、手続き面の問題を取り上げて、それを口実にしよう」ということですよね?
リンク記事のタイトルにある「滅多に使わない道具」というのはそういう意味合いですよね?
まさにそこが「表現の不自由展」をめぐる騒動の最大の問題点だと思います。
手続き面に問題があるからお金を出さないというんであれば、その手続きの瑕疵を論じればいいのであって、展示の内容について言及する必要もないはずです。
その観点から、いただいたコメントを読むと、「美術の世界は、鑑賞者と資金提供者からの評価が要」とタイトルでうたいながら、本文は手続き面の話から入っているというところがどうにも……ああ、やっぱりそうなんだな、と思えてしまいます。