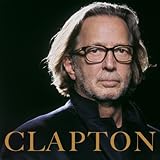大学入試改革において、英語民間試験に続き、記述式試験も導入が見送られることとなりました。
およそ50万人の答案を統一基準で公正に採点するのは不可能、まして、学生アルバイトが採点するなど論外、受験者の正確な自己採点も困難――とさまざまな問題点が指摘され、それなら自己採点の結果如何で受験先を決定するような場合には記述問題は使わないとかいう話になり、じゃあ何のための記述試験なの、という……もうグダグダで、どうやっても取り繕うことができなくなったわけでしょう。
前にツイッターで見たんですが、国会議員らによる官僚たちへの聴き取りで、「本当にできると思ってるのか」と野党議員が問うと、はっきりできると答える者は一人もいなかったということです。無理だということは本心ではわかってるけど、上からいわれていることなので止めることができない……現場の官僚たちは、そういう感覚だったといいます。
民間試験や記述試験の導入それ自体が自己目的化してしまい、本来の目的はそっちのけになる。いったい彼らは、誰のために働いているのか。本当に学生のことやこの国の未来のことを考えているのか……そう問わずにいられません。
ツイッターを見ているとわかりますが、記述式試験にひそむ問題点はもうずいぶん前から指摘されていました。
英語民間試験もそうですが、もっと早く止めることはできたはずなんです。
なのに、それをしなかった。できなかった。
その原因として指摘されるのは、入試改革を受け持つ教育再生実行会議の担当大臣を文部科学大臣が兼務していたということです。
遂行性が重視された結果、欠陥のある提案が十分に見直されることなく進んでいってしまったという側面があるようです。遂行性が高いというのは、逆にいえばブレーキがないということであり……それがむしろ、ぎりぎりになるまで止められないという事態につながったと考えられます。
もう一つ問題と思ったのは、この件に関して「特定の誰かの責任ではない」という荻生田文科相の発言ですね。
責任が分散され、薄められ、結果として誰も責任をとらない……という日本的無責任体質の問題です。
たしかに、今回の問題は誰か一人の責任ということではないでしょう。萩生田大臣に直接の責任があるわけではないかもしれません。
しかしこの「上にいるものほど責任をとらない」というあり方が、日本型組織の非常に悪いところだと私は思ってます。それが結局、同じ過ちを繰り返すことにつながってるんではないかと。
責任を声高に追及するのはどこか“人民裁判”のように見えてしまうかもしれませんが、こと政治に関しては、問題が生じたなら責任の所在を明らかにして、けじめはつけるべきだと思います。まして今回のケースは、教育という国の根幹にかかわる問題ですからなおさらでしょう。
まあ、無茶を承知で強引に突き進まず、ぎりぎりのところで中断しただけでもまだマシなんでしょうが……とにかく、この国の残念なところが凝縮されたような一件でした。
今回は、ゲーム記事です。
そういえば、このブログにはゲームというカテゴリーもあったということを思い出したので……ひさびさにゲームについての記事を書こうと思いました。
このブログでは、ゴジラシリーズの映画についてずっと書いているので、ゲーム記事もそこにあわせていこう……ということで、紹介するのは『ゴジラ トレーディングバトル』です。
カードバトル方式の陣取りゲームですね。
初代プレステ仕様のゲームで、第二期までのゴジラシリーズ(第一作『ゴジラ』~『ゴジラ対デストロイア』)に登場するほぼすべての怪獣とメカ兵器が登場。のみならず、ドゴラやサンダ、ガイラといった、ゴジラシリーズには出てこない東宝特撮怪獣や、このゲームのオリジナル怪獣も参戦。プレイヤーはこれらの怪獣を操ってデュエルするのです。ストーリーモードが2つ用意されているほか、対戦モードも。対戦モードではコンピューター相手の対戦もできて、X星人やブラックホール第三惑星人などと対戦できます。
こういうキャラ物のゲームはだいたいゲームとしてはあまり面白くないことが多いと思いますが、この作品はゲームとしてもなかなかよくできているといっていいでしょう。
怪獣それぞれの特殊能力があるだけでなく、「シャーベット計画」や「Tプロジェクト」など東宝特撮映画に登場したあれこれがカードになっていて、戦略性を高めています。これらのカードを適宜発動させることで、単に力勝負ではないゲームとなるのです。
グラフィック的な部分でも、昭和ゴジラ風のレトロな怪獣映画の感じを出しているのが楽しめます。たとえばジェットジャガーはあのジェットジャガーのチープさを表現しているのがいいですね。
私は、結構このゲームをやりこんでました。
あるとき、CDの盤面に傷でもついたのか、特定の怪獣が出てくるとフリーズするようになってしまい、プレイできなくなり……ゲームなんかやってる時間がそうとれなくなってきたこともあり、それからやらなくなってしまいました。そして、初代プレステのゲームなので、今となってはもはやゲームディスクを新たに入手したとしてもプレイが困難な状況です……
もしPSストアでオンラインで手に入るようになったら、ひさびさにやってみようかな、とも思ってます。そうなると、プレステのセーブデータは使えないのでデッキを一から構築していくことになりますが……それもまたカードゲームの楽しみでしょう。