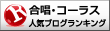歌を志す人の多くが、「力み」という悪癖に取り付かれて悩みます。その中でも、初心者に最も多いのが「舌根の力み」です。声を出そうとするたびに舌根に力が入り音声の通り道を塞いでしまう現象です。「音声の通り道を塞ぐ」と聞いただけでも「悪癖」であることが理解できます。音声の通り道は、常に出来るだけ広く、ソフトに開いているのが理想です。横隔膜で支えられた呼気に音声が混じり、腹の底から湧き出てくるようにその通り道を通って共鳴腔で鳴り響くのです。共鳴腔についてはこの稿では特に詳述はしないが、発声法の中で大変重要な要素です。広い意味では、身体全体が共鳴腔といえるが、主となるのは胸から上の空間であり、特に、口腔、鼻腔、頭腔における共鳴が重要視されます。
「悪癖」を除去するためにはどうするか?普段の練習がそのための時間であり、その中で行うしか方法はありません。基礎・基本に関するチエックポイントを意識し、練習の中で繰り返し練習することで克服してゆくのです。その過程では、先生の指導を受けたり、仲間同士で意見交換をしたり、声を聴きあったりすることも必要です。自分の声を、姿を他者に聞いてもらう、観てもらうということも大変重要なことです。別冊編でNさんが指摘していたように、自分の声を客観的に聞いてもらう、あるいは自分で聞いてみることは練習過程での必須事項であります。姿勢についても同様です。人に見てもらうこと、自分で確認すること、そのためには前述した鏡も登場します。全身を写す鏡で姿勢や表情を確認することがベストですが、口形や口中を点検するための手鏡は必ず携帯する必要があります。
自分の声を自分で聞くためには、録音機材の活用があります。これについてもNさんのアドヴァイスがありました。基礎練習をやりながら、あるいは合唱曲の練習をしながら、絶えず自らの音声、歌声を自分の耳で確認し、長所、短所を発見することです。短所に気づき、次の練習で矯正をする、あるいは、先生や仲間に直接聞いてもらい指摘を受ける。このような自発的、能動的な練習を続けると、必ず成果が現れます。ただ、簡単には会得できないことのほうが多いので、功を急がないこと、焦らないことです。信じて粘ることです!
「悪癖」を除去するためにはどうするか?普段の練習がそのための時間であり、その中で行うしか方法はありません。基礎・基本に関するチエックポイントを意識し、練習の中で繰り返し練習することで克服してゆくのです。その過程では、先生の指導を受けたり、仲間同士で意見交換をしたり、声を聴きあったりすることも必要です。自分の声を、姿を他者に聞いてもらう、観てもらうということも大変重要なことです。別冊編でNさんが指摘していたように、自分の声を客観的に聞いてもらう、あるいは自分で聞いてみることは練習過程での必須事項であります。姿勢についても同様です。人に見てもらうこと、自分で確認すること、そのためには前述した鏡も登場します。全身を写す鏡で姿勢や表情を確認することがベストですが、口形や口中を点検するための手鏡は必ず携帯する必要があります。
自分の声を自分で聞くためには、録音機材の活用があります。これについてもNさんのアドヴァイスがありました。基礎練習をやりながら、あるいは合唱曲の練習をしながら、絶えず自らの音声、歌声を自分の耳で確認し、長所、短所を発見することです。短所に気づき、次の練習で矯正をする、あるいは、先生や仲間に直接聞いてもらい指摘を受ける。このような自発的、能動的な練習を続けると、必ず成果が現れます。ただ、簡単には会得できないことのほうが多いので、功を急がないこと、焦らないことです。信じて粘ることです!