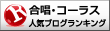「初心者の人へ」を書き終えて数日後、自分が初心者であったころのことを考えた。そして、合唱を始めてから今日までの道のりは、年数を数えると大変な時(約50年)を刻んできたのだが、実感としてはそれほど遠い昔のことではないようにも思える。しかし、現実には50年という年月は長くもあり、半世紀という区切りでもあることを思い、「初心者の人へ」の続編としてははなはだ唐突ではあるが「わが合唱歴」を書いてみることにした。
本編は、どの程度の回数(長さ)になるかは未定である。あるいは、早々とネタが尽きて終わってしまうもしれないし、意外にも長編に及ぶかもしれない。正直、今のところは自分でも予測はつかないのだが、8703の場合はスタートが遅く小・中・高生時代の合唱歴はほとんど無いので、それほど長編にはならないのではなかろうかとも思っている。
冒頭にお断りしておきたいことがある。それは、記述する内容からして、教えを受けた方々や、共に合唱をした方々など、相当数の人の実名が登場することである。もちろん、実名の記述がまずい場合には避けるが、原則実名記述をお許しいただきたい。
本編は、どの程度の回数(長さ)になるかは未定である。あるいは、早々とネタが尽きて終わってしまうもしれないし、意外にも長編に及ぶかもしれない。正直、今のところは自分でも予測はつかないのだが、8703の場合はスタートが遅く小・中・高生時代の合唱歴はほとんど無いので、それほど長編にはならないのではなかろうかとも思っている。
冒頭にお断りしておきたいことがある。それは、記述する内容からして、教えを受けた方々や、共に合唱をした方々など、相当数の人の実名が登場することである。もちろん、実名の記述がまずい場合には避けるが、原則実名記述をお許しいただきたい。