

西じゃどうかはしらねども、ここら北関東では、益子焼といえば有名。(ほかに、笠間焼などが有名・・・こちらは江戸中期辺りが発祥年らしい)
益子は江戸末期・・・たぶん、憶測だが、笠間焼を習って、益子が始まったんではなかろうか?
蕎麦屋なんぞに行くと、そばじょこが明らかに益子焼だったりする・・・
ぽてっとした、野暮ったいイメージだが・・・・

猥雑な共販センターなどすごして、北へ向かうと、美しい里山の風景になる。
何度も益子には来ているけど、こんな場所があったのかと・・・

「益子参考館」・・・濱田庄司の自邸と陶芸窯(工房)跡にある栃木県の登録博物館だ。
参考?・・・・世界各地で濱田が出会った民芸品・・「これには僕の作品は負けた」と、思ったものを彼は収集したらしく、それらの品々が、「作家たちの作陶の参考になれば」と思ったという。
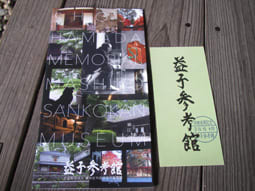


濱田 庄司(はまだ しょうじ、1894年(明治27年)12月9日 - 1978年(昭和53年)1月5日、本名象二)は、主に昭和に活躍した日本の陶芸家。僕はこの世界にまったく詳しいわけではない。
「神奈川県橘樹郡高津村(現在の川崎市)溝ノ口の母の実家で生まれる。東京府立一中(現東京都立日比谷高等学校)を経て、1913年(大正2年)、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科に入学、板谷波山に師事し、窯業の基礎科学面を学ぶ。1916年(大正5年)同校を卒業後は、2年先輩の河井寛次郎と共に京都市立陶芸試験場にて主に釉薬の研究を行う。
殆ど手轆轤のみを使用するシンプルな造形と、釉薬の流描による大胆な模様を得意とした。戦後、1955年(昭和30年)2月15日には第1回の重要無形文化財保持者(人間国宝)(工芸技術部門陶芸民芸陶器)に認定された・・・」などと、ウィキには書いてある。

民芸運動(みんげいうんどう)とは、1926年(大正15年)、「日本民芸美術館設立趣意書」の発刊により開始された、日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品の中に「用の美」を見出し、活用する日本独自の運動。21世紀の現在でも活動が続けられている。「民芸」とは、民衆的工芸の意。とも・・・書いてある。
民芸という、この言葉を僕が認識し、頭の片隅に残ったのは、沖縄・・・やはり陶芸の人間国宝「金城次郎」からだった。
「日本民藝館の創設者であり民芸運動の中心人物でもある柳宗悦は、日本各地の焼き物、染織、漆器、木竹工など、無名の工人の作になる日用雑器、朝鮮王朝時代の美術工芸品、江戸時代の遊行僧・木喰(もくじき)の仏像など、それまでの美術史が正当に評価してこなかった、西洋的な意味でのファインアートでもなく高価な古美術品でもない、無名の職人による民衆的美術工芸の美を発掘し、世に紹介することに努めた。」ともあるが、この柳宗悦さんが、金城次郎の名が全国に知れ渡るのに貢献したとも、沖縄で学んだ。そして、こちら濱田庄司とともに、民芸運動ってのは、一世を風靡するようである。


博物館級の品々が堪能できる。

展示の蔵がいくつかって、仕事場が保存され、登り窯が保存され・・・・広い敷地のたたずまいは、美しい。
静かな時間が流れ、ベンチで休憩するのも贅沢だった。

あの3.11でかなりの被害にあい、蔵は壊れ、作品が割れたらしいが、全国からの寄付で、修復が行われたようだ。


いいねぇ・・・登り窯。


案内の最後は、濱田庄司の作品を見ることができる。
益子・・・行くならここは来ないと!
いや?ここ目指して、まだ益子など未体験の方も、せひ行ってみてはどうだろうか?
良かったぜ!ここ。















