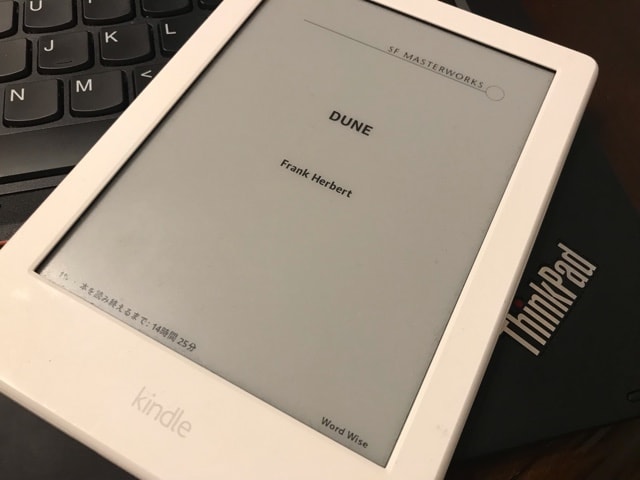今晩は山下公園で閾値走の予定でしたが、
午後5時頃横浜港を見渡すとピカピカドッカーン!
稲妻が垂直に走っていました。
当然、人間は走るの中止。
明日から少し涼しくなるって言うし、
ここで焦ることないよね?
と言い聞かせつつ半月近くが過ぎました。
本当にこれで今シーズン走れるだろうか?
仕事もじわりと忙しくなり、
あれれれれ、19時過ぎにオフィス離脱が難しい
時もある。
多少遅くても覚悟して走るしかないかな。
まずはMペースで平日帰宅ラン、週末ハーフ走。
そしてキロ4分となるべく長く友だちになる。
今は10km走れるかも怪しい。
驚くべきことに去年の9月は毎週末、
サブ3~キロ4分でハーフ走してました。
気温が今年より数度低かったからできたんだと
信じたい。
もう一つの悩みは最近、Kindleで読書にはまって
しまったこと。
何気に読了まで14時間25分だって。
この時間があれば、150kmくらい走れるんじゃない?
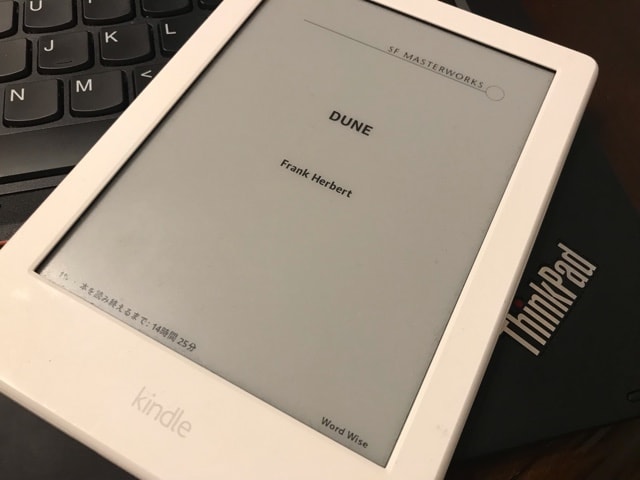
午後5時頃横浜港を見渡すとピカピカドッカーン!
稲妻が垂直に走っていました。
当然、人間は走るの中止。
明日から少し涼しくなるって言うし、
ここで焦ることないよね?
と言い聞かせつつ半月近くが過ぎました。
本当にこれで今シーズン走れるだろうか?
仕事もじわりと忙しくなり、
あれれれれ、19時過ぎにオフィス離脱が難しい
時もある。
多少遅くても覚悟して走るしかないかな。
まずはMペースで平日帰宅ラン、週末ハーフ走。
そしてキロ4分となるべく長く友だちになる。
今は10km走れるかも怪しい。
驚くべきことに去年の9月は毎週末、
サブ3~キロ4分でハーフ走してました。
気温が今年より数度低かったからできたんだと
信じたい。
もう一つの悩みは最近、Kindleで読書にはまって
しまったこと。
何気に読了まで14時間25分だって。
この時間があれば、150kmくらい走れるんじゃない?